[特集インタビュー]
オリンピックの代わりの大会を――
スポーツの意味を問う交渉小説
一九三八年、日中戦争が長期化するなかで、四〇年に予定されていた東京オリンピックの開催返上が決まった。翌三九年には、東京大会に代わって行われることになったヘルシンキ大会も、ドイツのポーランド侵攻を受けて中止が決定。忍び寄る戦争の足音を感じながら、それでも、スポーツの火を消してはならないと闘い続ける人々がいた。“オリンピックの代わりに大きな大会を開こう”と。 今年、デビュー二〇周年を迎えた堂場瞬一さんの新刊『幻の旗の下に』は、実際に一九四〇年に行われた「東亜競技大会」を軸に描かれる歴史小説です。元野球選手のふたりの若者が、大会の実現と参加に向けて奔走し、タフな交渉を重ねていきます。 スポーツは何のためにあるのか。スポーツと政治の力学、世代間の衝突と継承、日系人の苦悩とアイデンティティ、そして野球のすばらしさ。今日的なテーマが盛り込まれた歴史小説の刊行を前に、お話を伺いました。
聞き手・構成=宮田文久/撮影=chihiro.

オリンピックが“飛んだ”ふたつの年
―― とても戦前の話とは思えない、“今”のリアリティーに溢れた作品です。
アイデアがわいたのは、昨年三月に東京オリンピック・パラリンピックの開催延期が決まった後でした。一九四〇年に予定されていた東京五輪の開催が返上されたときと比べると、それぞれの背景は戦争とコロナということで、もちろんまったく異なります。ただ、“飛んだ”という点においては同じですよね。それで前回“飛んだ”時期のことを調べていったところ、「東亜競技大会」を初めて知ることになったんです。一九四〇年六月、東京五輪の代わりのように日本で行われた大会で、しかも意外と規模が大きいんですよね。
―― NHKがウェブ公開している記録映像を見ると、たしかにかなり大きな大会だったことがわかります。日本、満州(現・中国東北部)、中国を中心に、競技により他の国も参加するというものでした。
「この大会について書いたら、今、目の前で起きていることにかんしても新しい角度で考えられるんじゃないか」と思って、調べを進めていったんです。ただ、ほとんど資料は残っていなかったんですけど……。
―― 作中でも語られますが、政局を考えると、開催自体が奇跡です。日本による中国での軍事行動にアメリカが反発。日米通商航海条約を廃棄、国内の新聞各紙も非難している状況という……。
翌一九四一年には、太平洋戦争勃発ですからね。スポーツ大会だなんていっていられない状況は、目の前まで迫っていた。そうした大変な状況のなかでも前向きに動いていた人たちがいたという、少し明るい話を書きたかったんですね。
―― 主人公はふたり。大日本体育協会理事長の若手秘書・石崎
完全に創作です。いや、たとえばハワイ朝日というチームは実在したし、東亜競技大会で野球を実施するにあたって彼らが招かれたということも、記録として残っています。そうした若干の資料はあるのですが、ではなぜ大会側は、この難しい政局のときにハワイのチームを呼んだのか……そうした経緯にかんする詳細は、結局摑めませんでした。
―― 作中では、野球の母国であるアメリカを招くのは難しいがハワイなら、と事が運びます。
実在しない人物を設定して、思いっきり話をつくる余地があったということでもあります。そうやってストーリーはふくらませながらも、実在の人物も含めて周囲は固めていきました。たとえば、大日本体育協会の理事長である
―― 体育協会のスタッフに、野球チームのマネージャーと、アスリートではなく裏方の人物ふたりを中心においたのはなぜですか。
東京オリ・パラの裏方の人たちは、いったい何をしているのだろうな……という若干の疑問や皮肉めいたものがあったのは事実ですが、基本的には、東亜競技大会の裏方の人たちの大変さを描いてみたかったんですね。五輪が開催返上となった後、いきなりゼロからつくりあげていったわけですから。
裏方を描くにも、やはり資料は少なかったので、想像でふくらませていきました。実はお金まわりの話などは、資料で残っているんですよ。ただ、その周囲で誰がどんなふうに動き、どのような策謀が繰り広げられたのかという資料は、皆無に等しかった。
―― そこに小説の面白さがありますね。日本とハワイをまたいだ物語の展開も楽しいです。
野球が、十九世紀から日本とアメリカをつないできたスポーツであることは、間違いありません。そのつながりの象徴として、どうしても使ってみたかった。
隔たりをこえて人々が動いていく小説は、私の得意とするところでして。ハワイ朝日が参加している事実を知ったとき、「これでいけるな」という予感があった。なんでしょうね、遠くにいる友人との話とか、離れていても気持ちは通じるというような話が、大好きなんですよ。もし恋愛小説を書くとしたら、たぶん遠距離恋愛を描くんじゃないですかね(笑)。
これは正面突破の交渉小説
―― 遠く離れた石崎と澤山が、国と国の懸け橋たらんとする小説ですね。石崎は開催に反対する軍部と対峙する一方、五輪でも競技種目に入っていない野球を大会に組み込もうとする。澤山は日米の狭間にいる日系人という立場の難しさや、ホテルの仕事との両立という課題に苦慮します。ハワイ朝日が地元リーグを欠場すると入場料収入が減少するとして、反対する地元関係者たちもいて、頭を悩ませる。
私は『幻の旗の下に』を、“交渉小説”と呼んでいます。ネゴシエーターたちの小説だと。しかもふたりとも正面突破で、「お願いします!」とガンガンぶつかっていく。普通、こうした世界は裏で工作して状況を打開していくわけですが、そうした裏が何にもない小説にしたかったんです。裏でゴニョゴニョやらず、とにかくドーンと当たっていく。そういう意味の交渉小説であり、正面突破小説なんですよ。書いていて、爽快でしたね。
なおかつ、そうした正面からの交渉を行う主人公は、若者であってほしかったわけです。若い人が自分たちで頑張ってやりました、というふうにしたかったんですね。
―― 末弘が石崎にかける言葉がありますね。「スポーツは、君たち若人のものなんだ。上から押しつけられた仕事をこなすだけではなく、自分で考えて企画していかないといけない」
あの頃、末弘さんは五十歳くらい。以前から水上(水泳)競技連盟の会長としても活躍してきた人ですが、そうした説得力ある言葉を持つ人に、“次の世代に託す”役目を負ってもらいました。別の表現をすれば押しつけているのかもしれませんが、しかしやはり、若い連中に任せるということは大事です。順送りで世代が次から次へと入れ替わっていくような話にしたかった。年配者がいつまでも上の立場にしがみついているのは嫌だな、と。
―― 女性アスリートの姿が描かれるのも印象的です。大会の全容が固まる前、石崎が協力を頼みにいくのが、元水泳選手の女性。一九三六年、ベルリン五輪で実際に金メダルをとった前畑秀子の後輩にして好敵手であり、故障で五輪に出られず引退したという設定です。
前面には出していませんが、実は女子スポーツというのは今作の裏テーマのひとつです。近代オリンピックとしては一九〇〇年の第二回から女性が参加していますが、なぜか東亜競技大会では参加がなかったんですよ。なぜなのか、本当に謎なんです。だからこそ、架空の選手を通じて、当時の女性アスリートの姿を描いておきたかったんですよね。
―― 石崎の旧友であり、当時発足直後の職業野球(プロ野球)の道に進んだ立花博明も、架空の人ながら重要ですね。徴兵され、野球人生が危ぶまれるほどの重傷を負って中国から帰還します。
立花は、時代のひとつの象徴として登場させたかったんです。スポーツの話であまりケガ人は出したくないんですが、当時はああいう形で夢を絶たれてしまった選手や、それこそ戦死した選手もいたわけですから。石崎にしても澤山にしてもビクビクしながら生きていた部分はあったはずですし、自分が暮らしている社会の同調圧力も強く感じるようになりはじめていた時期だと思います。
―― 戦前のハワイの日系社会を描く難しさは?
苦労したのは、会話ですね。一九四〇年頃の英語、もしくは日系人の日本語、しかも話し言葉ということになると、正確な情報はほとんどないわけです。仮にあったとしても、それをそのまま私たちが今読む小説に落とし込んだら、たぶん読めない。日系一世の人は日本の感覚がまだ多く残っているだろうけれど、二世以降はよりアメリカの感覚に近いわけだから、使う言語も世代間で
ハワイパートでの会話文に悩んだ私が今回とった策は、“翻訳調”にやや近い日本語で書く、ということでした。スムーズに読めるんだけど、よく見ると少しだけぎくしゃくしたところがある、というような感じですね。
―― なるほど、そうしたディテールから時代や社会の匂いが漂ってくるのは面白いですね。ハワイにいる澤山が「日本にいた時はポテトチップを食べたことがなかったな」と思い出すのもまた、当時の空気が伝わってくる場面です。
日本に住む我々が今、当たり前だと思っているものが、当時は意外となかった、ということですよね。私はこれまで“飯を食う”という描写は、人の心情や、その人物の行動のありようを表現するのに最もわかりやすいものなんだ、ということをよく言ってきました。そのうえで最近、やや昔の話を書くことが増えてきて、食は“時代の象徴”にもなるんだなということが、改めてよくわかってきたんです。あの頃はすごく流行したけど、その後は見かけなくなったな……というような食の流行り
スポーツ大会に、誰もが納得する理由はない
―― 読み進めていくと、冒頭で触れたような現代的なリアリティーに溢れているのもまた、興味深いです。社会的な一大イベントとしてスポーツ大会を行うことにかんして、当時も今も、意義や理由を明確に語る言葉を誰ひとり持ち得ていないのだな、と感じます。
まさに、そういうことなんですよ。みんないろいろと理屈は言えるのだけれど、万人が納得する言葉というのはないんですよね。東亜競技大会だって、あえていえば、別に無理にやる必要はなかったわけですから。
―― 石崎たちは紀元二千六百年記念行事として大会を企画しますが、国力を戦争に傾注すべしとする軍部から反対されます。それに対して持ち出されるのは、スポーツ大会は健全な若者を育てるとか、国威発揚につながるといった理屈ですが、そう述べている石崎自身が納得できていません。
スポーツに対してはいろんな動機づけがありうるからこそ難しい、ということですよね。石崎が混乱する様子は、ある意味でスポーツに対する私自身の混乱がそのまま
―― スポーツのことが大好きな堂場さんだからこそ、その魅力と難しさの間で、いろいろと感じておられるのではないでしょうか。
オリンピックにかんしていえば、デカくなりすぎたんでしょうね。あまりにも多くの国と企業と金が絡んでいるがゆえに、いろんな人がくちばしを突っ込んでくるようになってしまった。もちろんそうやって注目を浴びるスポーツ界だからこそ、今の選手たちは努力や成果に見合ったステータスや報酬を手にすることができるわけですが、何かモヤモヤしたものが心に残るのは事実です。もう少し小さく、こぢんまりした規模で開催できれば、ここまで多方面からの影響は受けないはずですから。
―― 誰もが納得する理屈はないからこそ、本作ではそれぞれの価値観が相対化されているのが印象的です。ハワイ朝日には、中国と戦争している日本の大会に参加することで、政治利用されたくないとこぼす選手もいます。
何かが行われようとするときに、ノーと言う人は絶対に出てくるはずなんですよね。だからこれは、イエス・ノーのせめぎあいが起きるという、当たり前の話を書いているだけなんです。ノーだと言ってもスルーされてしまって、誰も聞いていない今が、不思議な世界なんですよ。
―― 登場人物みんな、きちんと議論しますよね。
そうなんですよ。今の世の中からは、ちゃんとした議論というものが消えていっているという感触があります。みんな忙しくて時間もないだろうけれど、もうちょっと前向きな議論をやるべきではないかな、というのは、書きながら考えていたことですね。
―― まさに交渉小説たるゆえんですね。だからこそ、ハワイから大阪タイガース入りし活躍した実在の日系人選手、愛称“ボゾ”で知られる若林忠志の言葉が刺さります。自分は野球人であるからこそ、「日本とアメリカの懸け橋になれると思っている」と。
野球に限らずスポーツは言葉が要らないからこそ、世界中どこで行われてもみんなが理解できる。そういう意味で、懸け橋になるのに最も適した営みではあると、やはり思うのです。特にボゾはいろいろと複雑な経験をしている人ですから、世界をつなぐ意識はあったでしょう。そうだ、『幻の旗の下に』を書きながら、ボゾでもう一本書けるなと感じたんですよ(笑)。いずれ書くかもしれないですね。
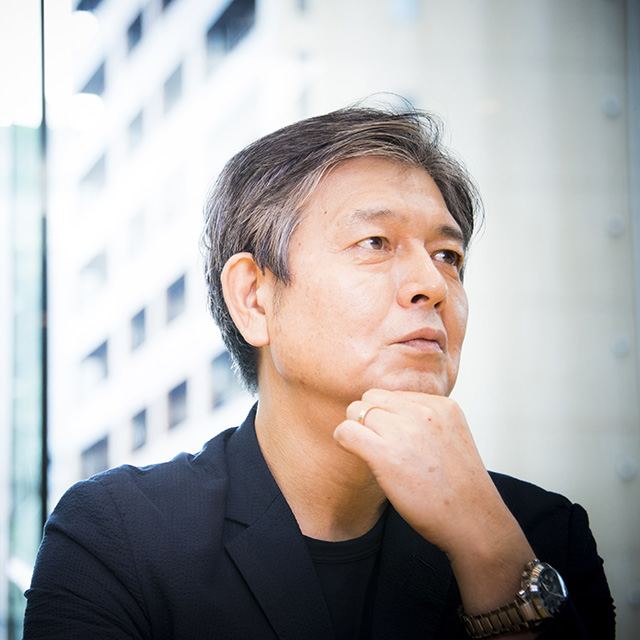
堂場瞬一
どうば・しゅんいち●作家。
1963年茨城県生まれ。青山学院大学卒業。会社勤務のかたわら執筆した「8年」で第13回小説すばる新人賞受賞。スポーツ青春小説、警察小説の分野で活躍中。著書に『いつか白球は海へ』『検証捜査』『複合捜査』『解』『共犯捜査』『警察回りの夏』『オトコの一理』『時限捜査』『グレイ』『蛮政の秋』『凍結捜査』『社長室の冬』等多数。








