[連載]
第6回 テクノ・ジャポニズム
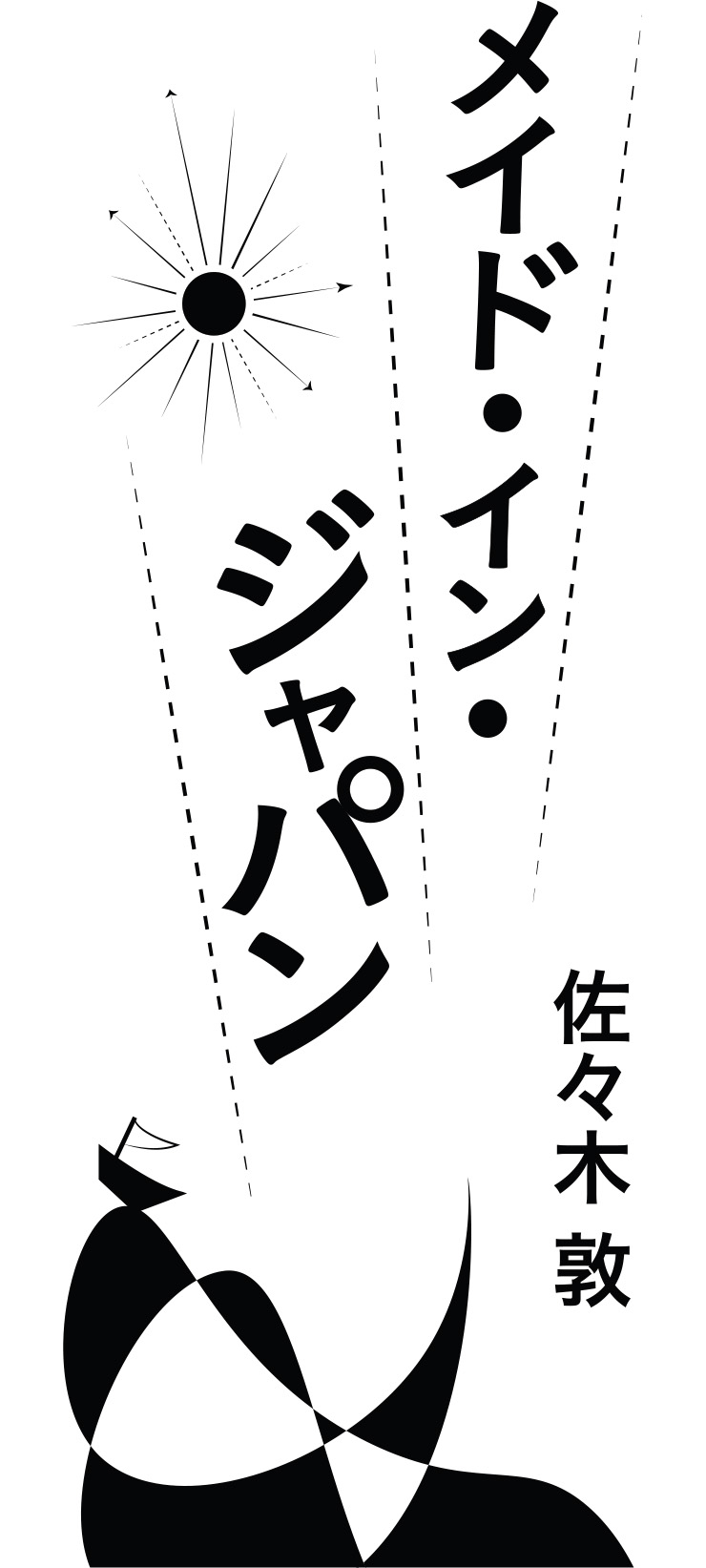
テクノ(ロジー)の国ニッポン
本連載第三回で、私はイエロー・マジック・オーケストラ(YMO)が海外でブレイクした(そしてその「逆輸入」によって日本でも大ブレイクした)理由について、彼らが登場した70年代末の時点で、日本はもちろん世界においても「YMOほどテクノ(ロジー)を音楽性と密接に結びつけたバンドは未だかつてなかった」こととともに、「人民服」や「テクノカット」など「西欧から見た東洋のステレオタイプな表象(日本も中国も区別がつかない)を戦略的に戯画化することによって、YMOはオリエンタリズムを戦略的に利用し、アジアのはずれに位置する島国ニッポンから突如として現れた「黄色い魔術=テクノポップ」というイメージを自己演出してみせたのです」と述べておきました。この二点は密接に繫がっています。当時、そして80年代を通じて日本は世界最先端の「テクノロジーの国」だったからです。その筆頭はYMOとも浅からぬ縁だったSONYですが、SONYに限らず日本企業は主として電子的(このワードもほとんど死語ですが)な先端技術によって世界から注目され、次々と海外進出を果たしていきました。イエローマジックとは端的にテクノロジーのことだったのです。アジアの端っこに位置する小さな島国でありながら、魔法のようなテクノ(ロジー)を生み出す、どこか謎めいた国ニッポンというイメージは、少なくともある時期までは世界的に流通していました。
たとえばそれは、映画『ブレードランナー』(1982年)が、舞台は2019年のロサンジェルスでありながら、リドリー・スコット監督がテクノロジーと猥雑さが混在する歓楽街のイメージを東京の歌舞伎町(と香港)から得ていたこと(この映画の原作はフィリップ・K・ディックの『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』(1968年)ですが、小説にはそのような描写は存在していません)や、世界的な大ヒットとなった『ブレードランナー』の世界観を引き継ぐように勃興したSF小説のサブジャンル「サイバーパンク」の
ブレードランナー/サイバーパンクのテクノ・ジャポニズム的イメージのモデルのひとつは歌舞伎町ですが、その中でも代表的なのは新宿ゴールデン街でしょう。人がすれ違うことも難しいほどの狭い路地が入り組んだ一帯に小さな吞み屋が密集するゴールデン街は、現在も外国人観光客が行きたがる東京の人気スポットです。いかにもアジア的なゴミゴミした
が、しかし、実は現実の日本/東京ではかなり異なったイメージが醸成されていました。一言で言えば、それはイエローもジャポニズムも脱色した純粋な「テクノ(ロジー)」の礼賛です。アジアのニッポンのトーキョーという特性─それはアドヴァンテージにもディスアドヴァンテージにもなりえる─をカッコに括って、無国籍的で無機質なテクノポリス/サイバーシティを標榜する、ということです。
スパイラルというトポス
現在も表参道の国道246号線沿いに存在するスパイラルは、女性用下着販売を主力商品とする衣料品メーカー、ワコールが1985年にオープンした複合文化ビルです。コンセプトは「生活とアートの融合」。ワコールはこのために100%出資の子会社ワコールアートセンターを設立し、スパイラルを拠点として多角的な文化事業を展開してきました。ビル内には、カフェ(スパイラル・カフェ)、名称の由来である螺旋状のギャラリー(スパイラル・ガーデン)、生活雑貨ショップ(スパイラル・マーケット)、多目的ホール(スパイラル・ホール)などさまざまな施設/店舗があり、地下にはライブも出来るレストラン&バーのCAYがありました(同店は2020年に閉店、リニューアルを経て現在はRobinClub表参道として営業)。建物の設計は槇文彦によるもので、80年代のポストモダン建築を代表する作品のひとつと言われています。
個人的な思い出話で恐縮ですが、私は若かりし頃、はじめてスパイラルに入ってみた時、強烈に「TOKIO」を実感しました。まず印象的だったのは、無菌室的と呼んでもいいような極めてクリーンな空間と、デコラティブとは真逆のシンプルイズベストな雰囲気です(普通はバロック的なムードを醸し出すはずのスパイラル=螺旋でさえ簡素で洒脱なイメージに寄与していました)。ショップには趣味の良いデザインの品が余裕を持ったレイアウトで並べられていました。施設全体が白系統のモノトーンで統一されており、どぎつい極彩色は完全に排除されていました。そしてビル内にはピアノやシンセサイザーによるアンビエント・ミュージックがゆったりと静かに流れていました。つまり『ブレードランナー』とは正反対です。ある意味でスパイラルは、イエローマジック/テクノ・ジャポニズム的な日本観/東京観に対する異議申し立てにさえ見えたのです。
スパイラルの簡潔かつ清潔、モノトナスでありながらオシャレなセンスは、セゾングループが1980年に田中一光の発案でブランド化した「無印良品」─スパイラルに先行して1983年に青山に路面店がオープンしていました─と共通していました。また、80年代以降に世界を席巻していった日本のファッションブランド、川久保玲(コム・デ・ギャルソン)や山本耀司(ワイズ/ヨウジヤマモト)のいわゆる「黒の衝撃」─どちらも1981年のパリコレクションで衝撃的な世界デビューを飾りました─とも「モノトナスがオシャレ」という点で繫がっています。これら80年代のニッポンの「生活とアートの融合」には禅の教えや侘び寂びを美徳とする日本の伝統的な芸術─茶道や華道、骨董や民芸などからの影響と、すこぶる現代的(ポストモダン的)と言ってよい、今の言葉を使うならミニマリスト的な機能美の追求が共存しています。そしてそのインフラは高度経済成長からバブル景気へと邁進していた日本経済であり、そのエンジンは何よりもまず日本企業の技術開発力=テクノロジーだった、というわけです。いうなればテクノ・ミニマリズムです。
スパイラルは、このようないわば「反ブレードランナー的」な日本観/東京観の代表ともいうべき場所でした(もちろん実際には「テクノ・ジャポニズム」と「テクノ・ミニマリズム」は「テクノ(ロジー)」という共通項によって繫がっていて、単純な二項対立ではなく、両方を兼ね備えたアーティスト─たとえば坂本龍一─も沢山いました)。
そして90年代に入ってから、スパイラル・ホールでユニークなパフォーマンス作品を発表し、世界的な注目を浴びていったアート集団がいます。京都を拠点としたダムタイプです。
ダムタイプの登場
ダムタイプは1984年に京都市立芸術大学の学生を中心として結成された「マルチメディア・アート・パフォーマンス・グループ」です。ダンス、演劇、音楽、映像、アート、デザイン、建築など、さまざまな分野の若手アーティストが集まって共同制作によって上演や展示をクリエイトするスタイルは、当時としては非常に新しかったと言えます。メンバーはプロジェクトごとに流動的で、いわゆる「リーダー」も置かない方針を採っていましたが、コンセプトとディレクションは主に前身の「劇団カルマ」時代からのメンバーである古橋
ダムタイプシアター名義のパフォーマンス『庭園の黄昏‐Every Dog Has His Day』(1985年)と『睡眠の計画‐Plan For Sleep』( 1 9 8 6 年) を経て、1 9 8 8 年の『Pleasure Life』で東京初進出、会場は原宿クエストホールでした。そして1990年、スパイラル・ホールで初演された作品が、ダムタイプの代表作のひとつとなる『pH』です。原宿クエストからスパイラルに移った経緯はわかりませんが、ワコールが京都の企業であることも関係があったのかもしれません。「pH=ペーハー」は水素イオン濃度を表す指数(power of hydrogen)のことですが、ダムタイプはこの作品でさまざまな二項対立─問い/答え、イメージ/言葉、事実/虚構、公/私、現実/非現実など─を扱った13の場面を断続的に繫げることで一編の上演を構成しました。身体と言語と映像と音楽/音響と美術と照明がスタイリッシュにミックスされた「マルチメディア」パフォーマンスは国内外で高く評価され、次作『S/N』は1994年、オーストラリア、アデレードの国際フェスティバルで世界初演されました。ダムタイプは以前から小規模な海外公演は行なっていましたが、これ以後、世界の名だたるアート・フェスや舞台芸術祭から次々と声が掛かるようになっていきます。『S/N』の日本初演の会場もスパイラル・ホールでした。
「S/N」とは「シグナル/ノイズ」の略で、オーディオ用語の「S/N比(信号と雑音の比)」でも知られています。二項対立への問題意識(それは単純な意味での「二項対立」というよりも、むしろ「排除」と「包摂」の関係性と呼ぶべきかもしれません)は『pH』を引き継ぐものですが、ここではよりアクチュアルな、現在の視点から見ても極めて先駆的なテーマ群─アイデンティティ、ジェンダー、セクシュアリティ─にフォーカスしています。そして、この作品がスパイラルで上演された1995年、10 月29日に、それまでのダムタイプの全作品で構成・演出を手掛け、自らパフォーマーのひとりとして出演してきた古橋悌二が、エイズによる敗血症で亡くなります。古橋は『pH』以後に、ゲイであることとHIVキャリアであることを公表していました。古橋が末期の床にある中、ダムタイプと『S/N』は世界ツアーを行なっていました。享年35。あまりにも早過ぎる死でした。古橋の没後、ダムタイプのディレクションは長年映像を担当してきた高谷史郎が引き継ぎ、古橋悌二が残したコンセプトノートを基にした『OR』(1997年)、『memorandum』(1999年)などのパフォーマンス/インスタレーションを日本に先駆けて世界各国で発表していくことになります。
ダムタイプがスパイラルで上演したのは『pH』と『S/N』ですが、この二作は彼らの出世作であるだけでなく、90年代の日本におけるアートとテクノロジーの融合(=メディアアート)の高度な達成として、またそのオリジナリティとクオリティを海外のアート・シーンに知らしめた傑作として極めて重要です。スパイラル・ホールは多目的仕様なので通常の劇場よりも設営の自由度が高く、基本的に立方体の空間なので舞台装置を作り込むダムタイプには向いていました。何よりもスパイラルというビル全体が持つどこか超然とした空気感がダムタイプにぴったりでした。こうしてスパイラル・ホールは最先端のパフォーマンス(演劇、ダンス)が観られる都内随一のスペースとして認知されていきました。いわばダムタイプはスパイラル(螺旋)に乗って世界に羽ばたいていったわけです。
ダムタイプは幾つかの点で、YMOの後継者と見ることができます。登場時期はほぼ十年ずれており、音楽と舞台芸術/アートという違いはありますが、どちらもテクノロジーを駆使し(またそれを標榜し)、海外で注目/評価され、コンセプチュアルでスタイリッシュ。坂本龍一の長年の友人(知恵袋)となる浅田彰は京都の人であり、ダムタイプの活動にも初期からさまざまなかたちで関わっていました。おそらく浅田を介して坂本はダムタイプと知り合い、高谷史郎を自身のインターネットオペラ『LIFE』(1999年)の映像に起用し、その後も数々のコラボレーション作品を発表、晩年はダムタイプのメンバーにも名を連ねました。いうなればダムタイプは90年代のテクノポップだったのです。しかしその「ポップ」には80年代とは異なる幾つもの─よりシリアスな─問題意識が装塡されていました。
インターコミュニケーション
『S/N』に続くダムタイプの舞台作品は、スパイラルではなく、『OR』(1997年)はパークタワーホール、『memorandum』(2000年)は新国立劇場で上演されました。『S/N』と『OR』の間に、その後のダムタイプの活動にとって、そして日本のメディアアートにとって非常に重要となる施設が誕生しています。1997年に初台の東京オペラシティ内にオープンしたNTTインターコミュニケーション・センター(ICC)です。ICCはNTTが日本の電話事業100周年(1990年)の記念事業として立ち上げたもので(1985年に日本電信電話公社が民営化されてNTTが誕生してからまだ5年しか経っていません)、その出発点は1991年に開催されたNTTインターコミュニケーション'91『電話網の中の見えないミュージアム』です。もちろんインターネットはまだ普及していません。現在もICCのウェブサイトで読むことが出来る開催記録には、こうあります。「最も身近なコミュニケーション・ツールである電話網をミュージアムに見立て,電話やファクシミリ,コンピュータを通じてアクセスし,約100人のアーティストや作家,文化人等の作品やメッセージを鑑賞するという実験的イヴェント.アクセス対象としては対談や朗読,音楽や小説・コミックなど5ジャンルが用意されました.アクセス方法は,電話機,ファクシミリ,パソコンを使用し,作品のジャンルごとに設けられた特設の短縮ダイヤルをプッシュするのみ.拡大するサイバースペースの世界を予感させるイヴェントとなりました」。この企画を伊藤俊治、彦坂裕とともに担っていたのが浅田彰です。もちろん「約100人」の中には坂本龍一の名前もあります。
『電話網の中の見えないミュージアム』から約6年を経て、当初は「見えない」コンセプトだった「インターコミュニケーション」を可視化/実体化する美術館としてICCは生まれたわけです。ダムタイプの『OR』には「協力」としてICCがクレジットされていますし、『memorandum』の上演会場である新国立劇場はICCが入っている東京オペラシティの隣です(というより「オペラシティ」ありきの命名)。ICCは基本的に大小複数のスペースに分かれたギャラリー/ミュージアムなので大がかりな演劇やパフォーマンスにはあまり適していません。『memorandum』はフランスで行なわれた世界初演も劇場であり、シアターピース的な傾向が強いので新国立劇場が合っていたと言えますが、そうでなければICCで上演されていた可能性もあったのかもしれません。『memorandum』に続くダムタイプの作品『Voyage』(2002年)もパフォーマンスの初演はフランスですが、インスタレーション版はICCで展示されました。その後もICCはダムタイプや高谷史郎(+坂本龍一)のインスタレーションや上映を継続的に行ない現在に至っています。ICCは研究機関や作品所蔵/アーカイヴの機能も持っており、日本(アジア)のメディアアーティストの登竜門としても重要な存在です。
1990年代~2000年代初頭は日本のアート(&テクノロジー/メディアアート)の環境が整備されていった時代です。スパイラルやICCの他にも、キヤノン株式会社が「アートとテクノロジーの融合」を掲げた文化支援プロジェクト(メセナ)として行なっていた「キヤノン・アートラボ」(1991年~2001年)や、キリンホールディングスが同じくメセナとして開催していた「キリンアートアワード」(1990年~2005年)などは現代アートシーンの重要アーティストを輩出しました。また、1999年に東京藝術大学美術学部の新設学科として先端芸術表現科が、2001年には岐阜県大垣市に情報科学芸術大学院大学(IAMAS)が、2003年には山口県山口市に山口情報芸術センター(YCAM)が誕生しています。これらは芸術的な志向も人脈的にも緩やかに繫がっており(もちろん違いはありますが)、いささか身も蓋もない言い方をすれば、藝大の先端からIAMASに行ってYCAMやICCで展示をする、というのが日本のメディアアーティストのひとつのサクセスモデルになっていきました。先端やIAMASには留学生も多く、国際的に活躍するメディアアートのトップランナーたちの個展やグループ展をいちはやく開催するYCAMやICCのオープニングには海外からも多くの招待客がやってくる。このような回路によって、日本人アーティストも世界から注目を浴びる可能性が飛躍的に高まりました。そしてそのパイオニアがダムタイプであったことは疑いを入れません。
池田亮司からRyoji Ikedaへ
ダムタイプの音楽は結成以来、山中透が担当していましたが、『OR』から新たに参加したのが池田亮司です。池田はスパイラルの音楽レーベルNEWSICから1993年にリリースされたコンピレーション・アルバム『サイレンス~未来への静かな提言』のプロデューサーで、私が彼と知り合ったのもこのアルバムがきっかけでした(私はこの時期、音楽ライターとして、『サイレンス』のゼネラル・プロデューサーでもある尾島
やや記憶が曖昧ですが、このアルバムの取材時に、プロデューサーの池田から彼自身のソロ・アルバムとして手渡されたのが『1000fragments』でした。これはNEWSICではなく池田の個人レーベルCCIレコーディングスからのリリースで、要するに自主制作でしたが、一聴して私は音楽家としての池田の才能を確信しました。池田がダムタイプに加入した経緯を私は知りませんが、1997年にイギリスの名門実験音楽レーベルTOUCHからリリースされた、90年代の電子音楽/電子音響シーンの方向性を決定づけたセカンド・アルバム『+/-』(この歴史的傑作については拙著『テクノイズ・マテリアリズム』を参照してください)の時点では、彼はすでにダムタイプに入っていたと記憶しています。『1000fragments』はミュージックコンクレート/サウンドコラージュやノイズの要素の色濃い作品でしたが、『+/-』は極度にミニマルな電子音のストイックな配列のみで組み立てられた「テクノの極限値」ともいうべきアルバムで、リスナーに衝撃を与えました。
以後、池田はダムタイプとソロ活動を並行させつつ、アーティストとしての国際的なプレゼンスを高めていきました。音楽だけでなく映像もシンクロさせたオーディオ・ヴィジュアル・パフォーマンスやインスタレーション、その全てに一貫する物理学や数学に裏打ちされたウルトラ・ミニマルな美学はアートの世界でも高く評価され、近年はフランスを拠点として国際的な活躍をしています。海外人気の方が日本より先行している印象もありましたが、最近は定期的に帰国してライヴや個展を行なっています。
本連載の第一回で、私は「ニッポン人になるか? ガイジンになるか?」という二択を提示しました。「日本的なるもの」を意識的に身に纏ってみせるか、あるいは「脱日本化」するか。池田亮司は言うまでもなく後者です。彼の作品は知覚(聴覚と視覚)に直接働きかけるものであり、言語が使用されている場合も(おそらく意図して)日本語が排除されています。池田の表現は、一見/一聴する限り、アジア的でも日本的でもありません。今では彼は「池田亮司」よりも「Ryoji Ikeda」と呼ばれることの方が多いはずです。
しかしそれでも、ダムタイプも、池田亮司も、テクノ・ジャポニズムと無関係ではありません。それはテクノ(ロジー)化されたジャポニズムということです。ダムタイプを天井棧敷や山海塾のテクノロジカルなアップデートとして受け取る海外の観客はいると思いますし、池田亮司を禅と結びつけて語る外国人もいるでしょう。そしてそれは必ずしも間違いとは言えず、それゆえの肯定的な評価もありえる。
これは由々しき、かなり厄介な問題です。事実として日本人である以上、たとえそんなことはないと言い張ってみても、日本人ではない者たちに「日本的なるもの」を見出されることを防ぐことは出来ないし、否定もし切れない。でも、これって国や人種を変えれば、私たちにも思い当たることがあるのではないでしょうか?
佐々木敦
ささき・あつし●思考家/批評家/文筆家。
1964年愛知県生まれ。音楽レーベルHEADZ主宰。映画美学校言語表現コース「ことばの学校」主任講師。芸術文化のさまざまな分野で活動。著書に『「教授」と呼ばれた男──坂本龍一とその時代』『ニッポンの思想 増補新版』『増補・決定版 ニッポンの音楽』『映画よさようなら』『それを小説と呼ぶ』『この映画を視ているのは誰か?』『新しい小説のために』『未知との遭遇【完全版】』『ニッポンの文学』『ゴダール原論』、小説『半睡』ほか多数。




