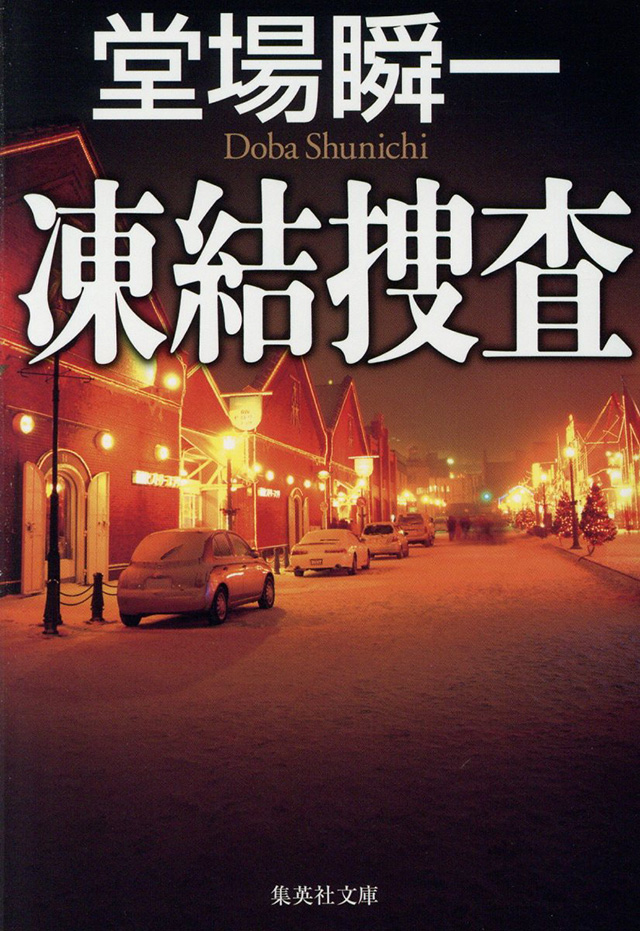[インタビュー]
『検証捜査』から芽生えた
「予測不能」の警察ミステリ
北海道、函館。そこからほど近い大沼国定公園で雪に埋もれた死体が発見された。殺されたのは三十三歳の男性会社員。凶器には銃が使われ、マフィアの処刑を思わせる残忍な殺され方だった。その翌日、その男性が起こした婦女暴行事件の被害者が失踪を遂げる。
『凍結捜査』は、『検証捜査』の登場人物たちが事件に関わっていく長篇小説の第五弾。函館中央署に勤務する保井凜(やすいりん)と、警視庁の神谷悟郎(かみやごろう)が事件解決に挑んでいく。『検証捜査』の登場人物たちは、これまでも『複合捜査』『共犯捜査』『時限捜査』で活躍してきたが、堂場さんはこれらの作品を「シリーズ」ではなく、『検証捜査』から始まったスピンオフだと語ってきた。シリーズばやりのエンタテインメント小説の世界で、あえて「シリーズ」と銘打たないのはなぜなのか。『凍結捜査』の魅力と、一連の作品との関係についてお話をうかがいました。
聞き手・構成=タカザワケンジ/撮影=山口真由子

─ 『検証捜査』は、神奈川県警の誤認逮捕の真相を捜査するために全国から刑事たちが集められ、即席のチームを組むという作品でした。その後、彼らの地元である埼玉(『複合捜査』)、福岡(『共犯捜査』)、大阪(『時限捜査』)がそれぞれ舞台になり、今回は北海道ですね。
保井凜の地元、北海道で事件が起きるということは決まっていたので、そこから考え始めました。今回はタイトルがわりとすぐに決まったので書き出しは楽でしたね。北海道だから『凍結』だ、と。タイトルが先に決まっているとあまり迷わずに書けるんですよ。
─ 冒頭でさっそく死体が発見されますが、次の場面は『検証捜査』の主人公だった警視庁の神谷悟郎が、一緒に捜査した北海道警の保井凜の部屋でともに朝を迎えています。これまでの作品を読んできた読者には、ちょっとした衝撃というか。
少しずつ時間が進んでいるんです。その間に人間関係にもいろいろ変化がありますよ、ということです。
─ 『検証捜査』では道警本部所属だった凜が函館中央署に異動していて、殺人事件の報を聞いて、非番にもかかわらず現場に行く。神谷に「君は、絶滅寸前のワーカホリックか?」とからかわれます。
昔は仕事一辺倒の刑事でもよかったんだけど、今はワーク・ライフ・バランスの問題を無視できませんよね。最近、よく言われている働き方改革が気になるんです。警察官って、部署にもよるんですけど、意外に残業していないんです。公務員だからもともと働き方にはうるさいんですよ。それがさらに細かくいろいろ言われるようになり、事件捜査の現場でどうするの、みたいなことが起こりうる。小説でいえば、本筋ばかり追っていると、この人は私生活がないのかという疑問が出てくる。ただ、私生活をリアルに書けば書くほど、本筋が進まなくなって読者を退屈させてしまうかもしれない。そのあんばいは難儀です。この作品に限らず悩むところですね。
もやもやしている主人公たち
─ 神谷は休暇を利用して函館まで凜に会いに来ているのですが、殺人事件と聞いて、首を突っ込みたそうなそぶりを見せる。凜に絶句されますけど。二人の関係は遠距離恋愛でもあり、多忙な刑事同士でもある。その不安定な関係の行方も気になるところです。
基本はもやもやしている人たちなんですよ。仕事でも人間関係でも。特に今回、神谷は前半は何もできません。北海道の事件に警視庁の刑事が口は出せませんから。これは『検証捜査』から始まった作品に共通する特徴の一つで、ある県で起きた事件に、ほかの県で起きた事件がからんでくる。『検証捜査』の時の仲間だという意識で何とかしたい。でも、公式的には関わる権限はない。そういうもやもや感がずっとありますね。
─ 協力はしたいけれど、表だってはできない。神谷と凜との関係も、つきあってはいるけれど将来を約束しているわけではない。どちらももやもやします(笑)。凜が非番を返上して現場に行ってしまったので、神谷が一人で函館をぶらぶらするんですけど、その手持ち無沙汰ぶりといったら。
おっさんはだめですね。観光地に一人でいってもやることがない。実は今回、前半は神谷の情けなさ、仕事に明け暮れてきた中年男の生活能力のなさをちょっと出してやろうと思ったんです。後半がんばってくれるので、その対比として。
─ 神谷が包丁を使わずに海鮮丼をつくるところが切ないというか、いじらしい。
あれがおっさんの限界です。これまで神谷の生活臭ってそんなに出ていなかった。離婚して一人暮らしで、仕事しかない。だから、今回プライベートな部分を書いてみました。それがうまくこの次につながればいいなと思っているんですけど。
─ 二人の私的な部分に読者の関心が向かう一方で、殺人事件のほうは捜査がなかなか進みません。殺され方は銃を使った処刑のようなやり方で日本では珍しいし、殺された男の経歴にもよくわからないところがある。しかも、殺された男が生前に起こした暴行事件の被害者が姿を消してしまいます。
事件の不可解さを際立たせるために、日常をきちんと書いておくのはミステリではよくある手。コントラストですね。今回は異常性を際立たせるという意味もあって、神谷に海鮮丼をつくってもらいました。
─ つくる料理が海鮮丼、というあたりに北海道らしさがうかがえます。ほかにも北海道や函館についての描写がありますね。
北海道の地理的条件とか広さとか、そういうのをうまく出したかったというのはあります。北海道といっても今回は函館に限定していますけど、函館だけでも十分広いですからね。市街地は狭いですが、山がかなりある。いかにも北海道らしい土地柄だと思います。
観光地、函館で起きる殺人事件
─ 函館は以前からよくご存じなんですか。
いや、まったく縁がなかったですね。今回に限らず、知らないところに行って取材して書くとおもしろいんじゃないかというのはありますね。札幌とどっちにしようか迷ったんですが。
─ 『検証捜査』の時に凜が勤務していたのは札幌の道警本部でしたね。
札幌は街が大きすぎると思ったんです。人口二百万都市でしょう。名古屋を舞台に書くのと同じぐらいの規模感になる。もうちょっとコンパクトなところを舞台にしたいと思った時に函館が出てきました。北海道で三番目に人口が多くて、約二十六万人。そのぐらいの規模の街が書きやすいんです。二番目は約三十三万人の旭川ですが、冬を舞台にするつもりだったので旭川は寒そうだなと(笑)。それで函館にしたんです。
─ 函館のグルメや観光地がさりげなく織り込まれていて、ちょっとした旅行気分が味わえました。
函館は基本的には観光地ですからね。でも、観光地って書きづらいんですよ。街が表のきれいなところを推しているから、その裏側にある生活に根づいた部分は意外に書きにくい。観光地は非日常な場所ですから、そこに一見、日常に起こりそうな事件を入れ込むのが難しい。軽く見えてしまいそうになるんですね。それで、全体的に雰囲気を凍結させたんです。冷たい雰囲気を漂わせるしかなかったわけです。
─ たしかにこの作品からは「温度」を感じます。たとえば凜が仕事帰りにコンビニで女性誌を立ち読みしているところに、いわくありげな女性が現れる場面。「風と雪が吹きつけ、凜は思わず首をすくめた。相手は心底寒そうにしている。このまま凍りつかせてやろうか、と思った。」というくだりなど、凍(い)てついた空気と、正体不明の女性との会見の緊張感がとても印象的です。
この作品だけでなく、気温と気候にはすごく気をつけています。場面の雰囲気を左右しますから。私の小説は暑い夏か、寒い冬が多いんですよ。梅雨どきの話とかあんまり書いていないんですよね。雨が嫌いだから。じめじめした話が嫌いだということもあるし(笑)。
「シリーズではない」強み
─ 主人公は女性刑事である凜。堂場さんの作品は男性が主人公というイメージがありますが、珍しいのではないでしょうか。
女性をここまで書いたことはないですね。それが今回の一番のチャレンジだったかもしれない。女性読者にどう読まれるかがちょっと心配なところでもありますね。
─ 『共犯捜査』では誘拐事件、『時限捜査』では連続爆破事件と大阪駅立て籠こ もり事件。派手な事件が続きましたが、今回は一見、普通の事件に見えて実は、という裏があるタイプの事件ですね。
『共犯捜査』や『時限捜査』はタイムリミットを設けてハラハラドキドキしてもらえるようなエンタメ色の強い作品をめざしました。今回は裏に何かあるんだろうけど、それがよくわからないミステリ。そういう意味では『検証捜査』と対をなすかたちの話になっているのかなと思いますね。
─ 何かが引っかかる。でも、それが何かわからない。そのもどかしさが後半、一気に解消されていく快感は、たしかに『検証捜査』に通じます。加えて、『検証捜査』で集められた刑事たちが、各地に散り、戦友のような関係になっている。直接に手助けをするということがなくても、ちらっと近況が出てきたりする。その関係性も魅力です。
濃い経験をともにしたけれど、その後は薄くつながっているみたいな感じ。それがこの作品群全体の特徴ではないかと思います。同じ課でかたまって事件を解決するような、いわゆるシリーズものの警察小説とは違います。あくまで寄せ集めだから、チームとはいえないですし。こういう関係ってちょっとうらやましいですけどね。ふだんは交流がなくても、何か声をかけると、あまり文句も言わずにすすっと動いてくれるみたいなのって。なかなかないですから、実際には。
─ 以前、『複合捜査』の時にインタビュー(本誌二〇一五年一月号掲載)させていただきましたが「シリーズではなくスピンオフ」だと強調されていましたね。シリーズものとの違いについてあらためてうかがいたいのですが。
シリーズという縛りがないと、ちょっと違う色の出し方ができる。それぞれ毛色が違うものを書けますから。それはシリーズではないメリットだと思います。
─ シリーズではない、ということで、出版社は「姉妹編」「兄弟編」とうたっています。説明が難しい(笑)。
あんまり聞かない話ですよね、こういうのって。実際、それぞれの作品に事件などのつながりはないんですよ。共通した登場人物が少し出てくるというだけで。
─ たしかにそうですね。『検証捜査』のメンバーが必ずしも主人公になるわけでもないですし。
一応、神谷は全部に出ているけれど、神谷が主役だったのって『検証捜査』だけなんです。あとは脇に回っている。最後においしいところだけ持っていったりもしますけどね。彼は出てくるけど、主役ではない。だから、やっぱりシリーズとは言えないですね。
─ 堂場さんが以前おっしゃっていた、『検証捜査』が根っこで、そこから芽が出てくる感じ、というたとえがしっくりきますね。
だから、スピンオフという言い方もおかしいのかもしれない。何なんでしょう。何か説明しにくい感じのものを書いてしまいました。シリーズで普通に書くほうがよっぽど楽ですよ。毎回メインキャラクターが同じなわけだから。
─ 神谷が主人公のシリーズにはしたくなかったということなんでしょうか。
おもしろくないでしょう、それじゃ。よくあるパターンだから。そうじゃなくて、何か別のかたちで展開できないかというのはありました。シリーズは必ず主人公が一貫しているのがお約束だから、そういう点をちょっと外したかったんです。
─ それぞれ舞台となる街も、主人公も違う。サスペンス色が強いものもあれば、ミステリ色が強いものもある。今回は刑事の日常も登場します。読者の立場としてはどんな作品なのか予想がつかない。贅沢だなと思います。
ただ、ゆるやかなつながりはあって、時間も進行しているので、最後に風呂敷をどう閉じるかが問題になってきました。次の六作目がその最後になります。それもメンバーの中で一番影の薄い永井高志(ながいたかし)で書かなきゃいけないという課題が残ってしまった。
─ 永井は『検証捜査』では警察庁刑事局の理事官でした。いわゆるキャリアで神谷たちとは立場が違う。そして、『凍結捜査』では広域捜査課長として登場し、物語後半に大きく関わってきます。この流れからすると、次の作品はかなりスケールの大きなものになりそうですね。
それが今一番悩みの種なんですよ。今年の十月ぐらいに書くつもりですが、タイトルがまだ浮かんでいないので、難儀すると思います。
─ 「シリーズではない」異色の物語がどのように完結するか楽しみに待ちたいと思います。

堂場瞬一
どうば・しゅんいち●作家。
1963年茨城県生まれ。新聞社勤務のかたわら小説の執筆を始め、2000年に「8年」で小説すばる新人賞を受賞。警察小説、スポーツ小説を中心に幅広いジャンルで活躍。著書に『検証捜査』『グレイ』『警察(サツ)回りの夏』『複合捜査』『蛮政の秋』『共犯捜査』『社長室の冬』『時限捜査』『宴の前』等多数。