[連載]
第5回GAKKO!・白塗り・ノスタルジー
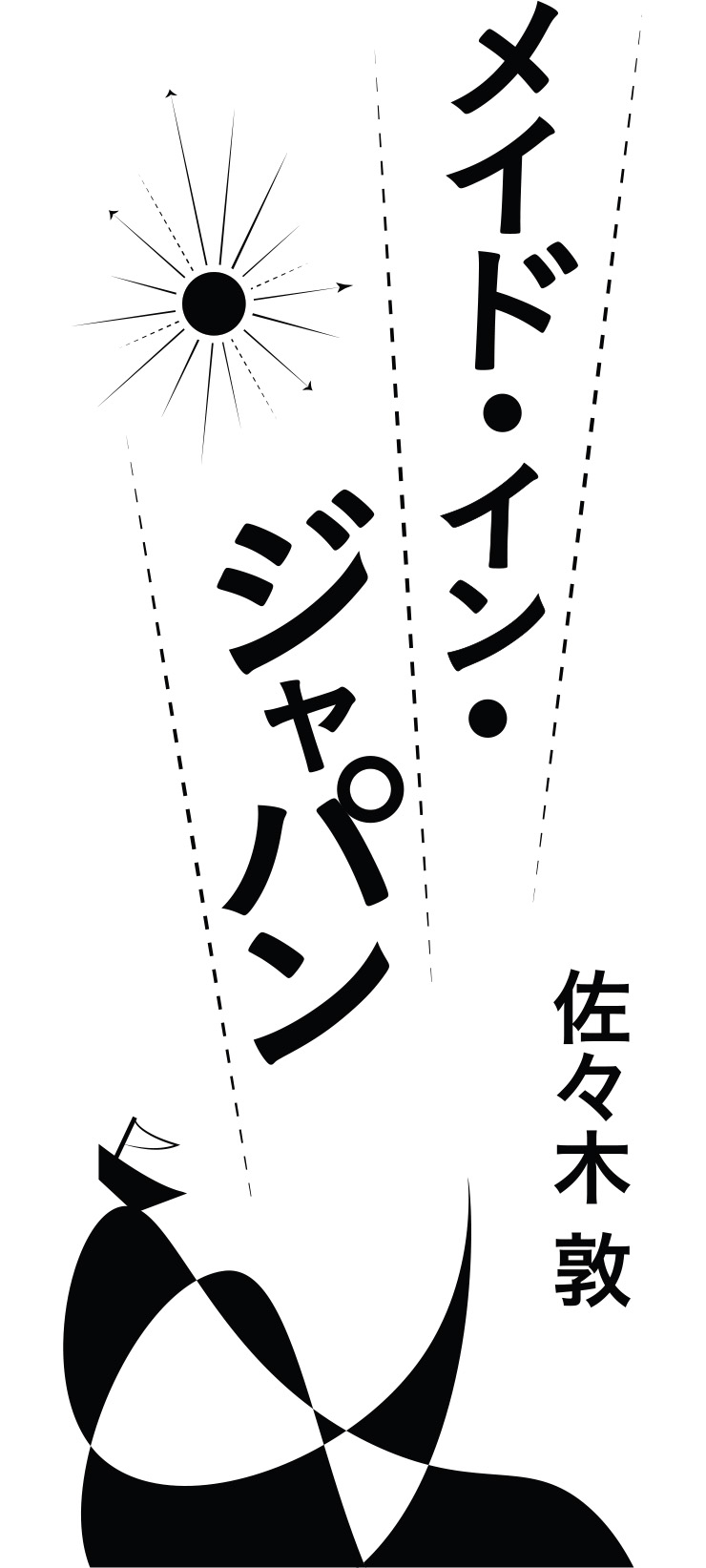
「新しい学校」はなぜブレイクしたのか?
新しい学校のリーダーズは、2015年に結成された4人組女性グループです。中田ヤスタカ、きゃりーぱみゅぱみゅ、現在のアイドルシーンで最も上り調子と言われているFRUITS ZIPPERを擁するアソビシステム、IP(知的財産)を活用したマーケティング会社として知られるTWIN PLANET、テレビ朝日ミュージックの三社合同マネージメントで、2017年にメジャーデビュー、セーラー服を着てアクロバティックに踊りまくりながら歌う(のは主にSUZUKAだけですが)ユニーク極まりないステージングと、アッパーでキャッチーな音楽性、メンバーの個性的なキャラクターによって、まず日本国内で話題を呼び、前回述べたように、2020年にアジア系ミュージシャンを支援するアメリカのプロモーション会社88risingと契約、「ATARASHII GAKKO!」として海外デビューし、以後は日本の地上波テレビ番組から米国の大型音楽フェスティバルまで幅広く出演し、知名度と人気を得ています。
私は新しい学校のリーダーズには初期から注目していたのですが(特に彼女たちのYouTubeチャンネルのファンでした)、それにしても最近の活躍ぶりには驚かされます。特に海外でこれほどウケるとは思っていませんでした。その受容のされ方は、世界進出を果たした過去の日本のミュージシャンとも、XGとも、YOASOBIとも違っています。海外デビュー後も英語曲や英語ヴァージョンは出しておらず、使用言語は日本語のまま、日本と海外で活動スタイルを分けていません。ATARASHII GAKKO!と新しい学校のリーダーズは、名前以外はまったく同じです。向こう側に多少とも「寄せる」のではなく、彼女たちの強烈な個性と魅力が英語圏でもそのまま通用している。
しかし考えてみれば、新しい学校のリーダーズが所属するアソビシステムには、きゃりーぱみゅぱみゅという先行者がいるのでした。きゃりーは東京原宿発祥のいわゆる「Kawaii」文化のアイコンとして、2010年代から海外でも絶大な人気を得ており、ATARASHII GAKKO!やYOASOBIに先んじて世界最大の音楽フェスティバル「コーチェラ」にも出演しています。打ち出しているイメージはかなり違いますが、音楽性だけではない、トータルコーディネートされた「異文化としてのジャパン・カルチャー」を武器にしているという意味で、ATARASHII GAKKO!はきゃりーぱみゅぱみゅ(KPP)という成功例を踏襲していると言えます。
では、なぜATARASHII GAKKO!は海外でも人気を博したのでしょうか? もちろんその答えはひとつではありません。しかし、ここで特に挙げておきたいのは、セーラー服という衣装の特殊効果です。まもなく結成から10年を迎え、メンバーはすでに20代の半ばなので、一種のコスプレなのですが、「学校=GAKKO!」というコンセプトとセーラー服は切り離せません。日本の女子学生の制服は独特な進化を遂げており、アジア各国にも影響を与えていますが(K-POPのアイドルも日本のハイスクール風の衣装を着用することがよくあります)、新しい学校のリーダーズが着ているのは非常にオーソドックスな古いタイプのセーラー服のように見えます(最近はアレンジが加わってきましたが)。つまり彼女たちのセーラー服は、現在形のものというより、ある種のノスタルジーを備えています。令和のリアルな学校ではなく、昭和や平成の古き良き「学校」を思わせる。「新しい学校」なのに、いでたちはむしろ新しくない、というギャップ。このことは日本人である私たちはすぐに見て取れますが、西欧人にはそれほどヴィヴィッドには伝わらないかもしれません。しかしセーラー服というユニフォーム(=単一の形態)が醸し出す、どこか旧態依然とした、敢えて強い表現を使うと奇抜なイメージが、海外での人気にもポジティヴに作用していることは確かだと思います。学生服を見慣れていない西欧の視線にとって、セーラー服は実際、いささか奇妙なものに映るはずです。清楚や貞淑といった西欧男性が日本人女性に見出しがちな属性を想起させる、色彩を欠いたモノトーンの地味な制服を着込んだ女の子4人が、見た目に反して激しく目まぐるしくダンスするさまが、海外の観客に大きなインパクトを与えたであろうことは想像に難くありません。彼らにとって「セーラー服」は「ニッポンのハイスクール」という現実とは異なったイメージの象徴であるわけです。KPPの「Kawaii」がATARASHII GAKKO!の「GAKKO!」だということです。
さて、実は、新しい学校のリーダーズに続けとばかりに「ニッポンのハイスクール」の「制服」を身に纏ったダンスグループが、海外を騒がせています。アバンギャルディです。
アバンギャルディの登場
アバンギャルディは、コレオグラファー(振付師)のakaneがプロデュースするダンスユニットで、2022年に結成されました。akaneはプロの振付師として活動するかたわら、ダンスの名門として知られる大阪府立登美丘高等学校ダンス部を日本高校ダンス部選手権で連覇に導き、同校の卒業生を含む自らのダンスチーム「アカネキカク」のメンバーから選抜して誕生したのがアバンギャルディです。結成当初は20人編成でしたが、メンバーの入れ替わりがあり、2024年10月現在は17人で活動しています。メンバーは19歳から29歳までと、かなり年齢の幅があるのですが、全員が黒髪のおかっぱ(ウィッグ)で、こちらはセーラー服ではなく白のブラウスに紺or青のジャンパースカートで統一しています。アバンギャルディの衣装は実際には特注のブランドものだそうですが、日本人であれば誰もがなんとなく見覚えがあるような気がする、セーラー服ほどではないですが「ニッポンのハイスクール」感、トラディショナルな「GAKKO!=学校」を思わせるものになっています。新しい学校のリーダーズはセーラー服以外はヘアスタイルもメイクも今風ですが、アバンギャルディは年齢や容姿、背格好を超えて遠目には全員がそっくりに見えます。「謎の制服おかっぱ集団」がキャッチフレーズ。多様性の時代だからこその、敢えての統一感、これは重要なキーワードです。
アバンギャルディの特徴はルックスだけではありません。ダンスに特化したグループなので楽曲は既存の有名曲から選んでいて、YOASOBIの「アイドル」やCreepy Nutsの「Bling‐Bang‐Bang‐Born」といった海外でバズった大ヒット曲も踊っているのですが、彼女たちのブレイクの最大の要因は、「昭和歌謡」を採用したことだと思われます。これはグループ誕生のきっかけになった日本のテレビ局のダンスコンペ番組が使用曲は邦楽のみというルールであったため、akaneが愛聴していた往年の歌謡曲を選んだのでした。2023年6月、アメリカNBCの超有名オーディション番組「アメリカズ・ゴット・タレント(America's Got Talent)」(この番組は後の回にも出てきます)にアバンギャルディは出場し、1978年にリリースされた岩崎宏美のヒット曲「シンデレラ・ハネムーン」に合わせてマスゲームばりの一糸乱れぬダンスを披露、観客の大喝采と審査員の絶賛を浴びました。この時の様子はYouTubeで観ることが出来ます。オリジナルはなにしろ昔の曲なのでテンポが遅く、アバンギャルディは少し速度を上げて踊っています。先にも述べたように最近のJ-POPや洋楽(ABBAなど)も使用していますが、アバンギャルディのトータルイメージとしては、やはり「昭和」あるいは「平成」の音楽とのマッチングが良いと思います。「シンデレラ・ハネムーン」の他には、渡辺真知子「迷い道」(1977年)と「かもめが翔んだ日」(1978年)、荻野目洋子「ダンシング・ヒーロー(Eat You Up)」(1985年)、井上陽水「少年時代」(1990年)、大黒摩季「あなただけ見つめてる」(1993年)などで踊っています。これらの曲は、日本人にとっても、ある年齢以上なら懐かしさを、若い層には今のJ-POPにはない「歌謡曲」のレトロフューチャー的な新鮮さを感じさせるものだと思いますが、akaneとアバンギャルディは全米ネットのオーディション番組に敢えて全面的に「昭和(平成)ノスタルジー」で武装(!)して臨んだわけです。そしてそれは大成功しました。アバンギャルディは今や国内外で引っ張りだこになっており、メンバーはTikTokやInstagramで「制服おかっぱ」を脱いだ普段の姿も見せています。
白塗りという発明
ここまで見てきたように、新しい学校のリーダーズとアバンギャルディには、多くの共通点があります。制服(正確には学生服)、ノスタルジーとアナクロニズム、統一感と個性のギャップなど、日本では懐かしさを、海外では新奇さを喚起する手法も似ています。しかし「輸出」という観点で言うならば、やはり最大のポイントは、皆が同じ学生服を着ていることなのではないかと思います。アメリカのハイスクールには基本的に制服が存在しないので、全員がほぼ同じ服装をしていること自体が物珍しいのに、その制服が没個性的で地味であるという。実際には日本の女子学生の制服文化はファッショナブルな発展を遂げているようですが、意図的に古式ゆかしきデザインを採用している。これは趣味の範疇ではなく、明らかに一種のマーケティングだと言えます。そしてそれはめざましい成功を収めている。
ところで、アバンギャルディのシュールでチャーミングなダンス動画を観ていて、私はふと、いささか妙な連想をしてしまいました。この感じは何かを思い出させる……アングラ演劇と暗黒舞踏だ!
アングラ演劇と総称されているのは、今年亡くなった唐十郎(状況劇場→唐組)、1983年に没した寺山修司(天井棧敷)、現在も活動中の鈴木忠志(早稲田小劇場→SCOT)、佐藤
特に寺山修司の作品には、学生服がよく出てきます。彼は自らの劇団、天井棧敷の舞台以外に映画もたくさん作りましたが、そこにも学生服姿がたびたび登場します。詰襟の学ランに学生帽(学帽)の少年は、物語や場面の主体であるよりも、傍観者のような役割であることが多く、かと思えばすでに見るからに大人になっているのに、いまだ学ラン学帽のままの不気味な男が現れることもあります。そしてそんな「学生」は、どういうわけか顔を白く塗っている、いわゆる白塗りをしていることが多い。白塗りはアングラ演劇に特徴的なイメージと言えますが、ここで先に挙げたもうひとつ、アングラ演劇と時代的に並走する暗黒舞踏について述べておく必要があります。
暗黒舞踏(バレエなどの「舞踊」と差異化するために「舞踏」とされている)は、1986年に57歳の若さで逝った
暗黒舞踏もアングラ演劇同様、その作品世界は舞踏家によってさまざまなヴァリエーションがあるのですが、ベーシックなイメージは、剃髪と白塗りだと思います。実際にはそれも時代とともに変化していますが、特に大駱駝艦と山海塾(今年の3月に天児牛大が亡くなり、今後の活動は不明ですが)は、このイメージが今も強い。創始者である土方巽に由来するものですが、必ずしも白塗りが必須ということではありません。しかし暗黒舞踏と言われて真っ先に思い浮かぶのは、禿頭と局部のみを覆った裸体で全身真っ白の踊り手たちがゆっくりと身を
しかし、ここで注目すべきなのは、白塗りの由来や理由ではなく、その効果です。髪を剃り上げ、顔を白く塗ってしまうと、本来の容貌がなかば消失し、みんな同じ顔に見えてくる。特に群舞になると、踊り手ひとりひとりの個人性、個体性は限りなく減衰し、誰が誰だかわからなくなり、総じて人間味を喪って、ひとかたまりの蠢く白い肉と化してしまう。確かに、西欧でもピエロ(道化師)は白塗りをしていますが(暗黒舞踏の白塗りのひとつの影響源はマルセル・マルソーなどのパントマイムにあるのではないかと思います)、受ける印象はかなり違います。要するに、白塗りという仮装、扮装、化粧には、舞台に立つ複数の踊り手たちのかたちを一つにする(ユニ・フォーム)効果があるわけです。もうおわかりのように、これはアバンギャルディの制服おかっぱが
もうひとつ、アングラ演劇と暗黒舞踏の交点を示していたとも言えるユニークな集団について述べておきましょう。維新派です。演出家の松本雄吉が主宰していた劇団で、1970年に結成、独創的な舞台表現によって国内で数多くの賞を受賞し、2000年以降は海外ツアーや国際舞台芸術祭への出演も相次ぎ、日本を代表する前衛劇団として名を馳せましたが、2016年に松本が69歳で病没し、現在は活動休止状態が続いています。
維新派の舞台は「ヂャンヂャン☆オペラ」と称されるように、台詞の大半を五七調に分解し、音楽担当のギタリスト内橋和久が指揮するリズミカルな演奏に乗せて俳優たちが発話・唱和するという、擬似オペラのような独特なスタイルを持っています。公演規模は人気と評価が高まるにつれて次第に巨大化し、後期には壮大な野外劇の様相を呈していました。維新派の作品の舞台は、日本から大量の移民が旅立った南米であったり、大日本帝国時代の植民地であったり、東欧であったり、日本の「路地」であったりと、いずれも現在とは時間的、地理的な「遠さ」を持っており、そこでノスタルジックでありながら、徐々に「日本」に対する厳しく辛辣な眼差しを露わにする物語が展開します(これは他のアングラ演劇の基調音とも共通しています)。純真無垢な少年少女が狂言回しに置かれていることが多いのも特徴です。そして、その「ヂャンヂャン☆オペラ」の役者たちは皆、白塗りなのです。学生服もよく出てきますし、年齢的にはアングラ演劇のパイオニアの次の世代に当たる松本は、当然ながら天井棧敷や状況劇場から影響を受けていたと思います。維新派の革新性は、アングラ演劇の「演劇」の要素に「音楽」をほぼ全面的に貼り付けてしまい、更にマスゲーム的な群舞を大胆に取り入れることによって、限りなく「ダンス」に接近してみせた、ということです。その世界は唯一無二であり、松本の早すぎた死が残念でなりません。
維新派の舞台のほとんどは大人数が出演するものですが、主役級の役者の見せ場はあるものの、印象的なのはやはり、白塗りの没個性的な、まるで操り人形のような人物たちが大勢で同じ振付で動きながら五七調の文言を発するという異様にして魅惑的な光景です。そして、スケールも、テーマも、アティチュードも、何もかもが大きく異なっているのにもかかわらず、アバンギャルディは、どこか維新派を思わせるのです。規模は桁違いですが、海外の観客に初見で大きなインパクトを与えたであろうことも同じです。天井棧敷も、山海塾も、維新派も、かつて海外公演で一世を
仮想としてのノスタルジー
もう一点、見逃せないのは、ノスタルジーあるいは時代錯誤(アナクロニズム)という問題です。新しい学校のリーダーズのセーラー服はけっして新しくはなく、アバンギャルディの方法論はまったくアバンギャルド(前衛)ではない。だが、それはアングラ演劇や暗黒舞踏といった何十年も昔の「前衛」の(おそらくは無自覚な)引用もしくは回帰なのであり、そこには海外の、すなわちノスタルジーを共有していないはずの観客や聴衆からのポジティヴな反応の秘密が見え隠れしている。
言ってしまえば、それは単なるジャポニズム、相も変わらぬオリエンタリズムということなのかもしれません。しかしここには、それだけで簡単には片付けられない、本連載にとっての重要な鍵のようなものがあるのではないかとも思えるのです。あるいはジャポニズム、オリエンタリズムと迷惑げに呼んできたものの内にこそ、まだ汲み尽くされていない水源、鉱脈のような何かが潜んでいるのではないか?
ひとまず、ここで述べておきたいのは、体験したこともなく、記憶の中にも存在していない過去へのノスタルジー、明確で正確な時間意識や歴史感覚を伴わない時代錯誤=アナクロニズムが、どうやらどこかで作動しているのではないか、ということです。あるいはもっと素朴に、私たちに「古さ」や「懐かしさ」を感じさせる何かは、それを古いとも懐かしいとも感じない他者にとってもまったく別の回路で受容されているのではなく、仮想的なノスタルジーというか、メタなアナクロニズムというか、ああ、どうやらこれはあなたがたにとってはたぶん(良い意味で)「古い」ものなのだな、何かしら「懐かしい」ことなのだな、いま現在に有効なものではないのかもしれないが、かつては現在形の、「今ここ」にある輝きを、確固たる存在意義を放っており、その記憶と事実性ともども、ここで提示されているのであるらしい、という曖昧だがけっして錯覚とは言えない感覚が、海の向こうの人々にも、何らかのかたちで伝わっているのではないか。
たとえばそれは、私たちが『風と共に去りぬ』を読んだり観たりした際に勝手に抱いてしまう「南北戦争下のアメリカ」への根拠のないノスタルジー(とは本当は呼べない感覚)に似ていますが、もっとはるかに近過去が対象になっている。航空技術やインターネットの発達によって、物理的にも情報伝達的にも、地球上の距離感覚が飛躍的に縮減されたことも、おそらく関係がある。実際の時間的(空間的)な懸隔はよくわかっていないのだが、むしろそれゆえに生じる、「古い」ではなく「ちょっと古いらしい」、「懐かしい」というより「懐かしいのだろう」という、ワンクッション置いた、だが「古くない」とも「懐かしくない」とも違う、思い込みと呼んでしまえばそれまでの、どうにも不可思議な、だがおそらく今ではごくありふれた感興。
新しい学校のリーダーズのセーラー服、アバンギャルディの制服は、おそらく現在の日本の高校ではほぼ見ることができないものだと思います。それは「昔」、昭和や平成と呼ばれた時代への、本物なのかどうかもわからないノスタルジーを呼び起こすユニ(・) フォームなのであり、しかし「昔々」ではない。つまりそれは、たかだか数十年前、十数年前に過ぎない過去を、私たちが「昔」だと思っているということでもあります。そして、このどこか倒錯的な「昔」という感覚は伝染する。海の向こうの誰かにも。(つづく)
佐々木敦
ささき・あつし●思考家/批評家/文筆家。
1964年愛知県生まれ。音楽レーベルHEADZ主宰。映画美学校言語表現コース「ことばの学校」主任講師。芸術文化のさまざまな分野で活動。著書に『「教授」と呼ばれた男──坂本龍一とその時代』『ニッポンの思想 増補新版』『増補・決定版 ニッポンの音楽』『映画よさようなら』『それを小説と呼ぶ』『この映画を視ているのは誰か?』『新しい小説のために』『未知との遭遇【完全版】』『ニッポンの文学』『ゴダール原論』、小説『半睡』ほか多数。




