[特集インタビュー]
鬼は誰の心にも棲んでいる
死者の姿が見える赤い瞳の“
聞き手・構成=朝宮運河/撮影=山口真由子
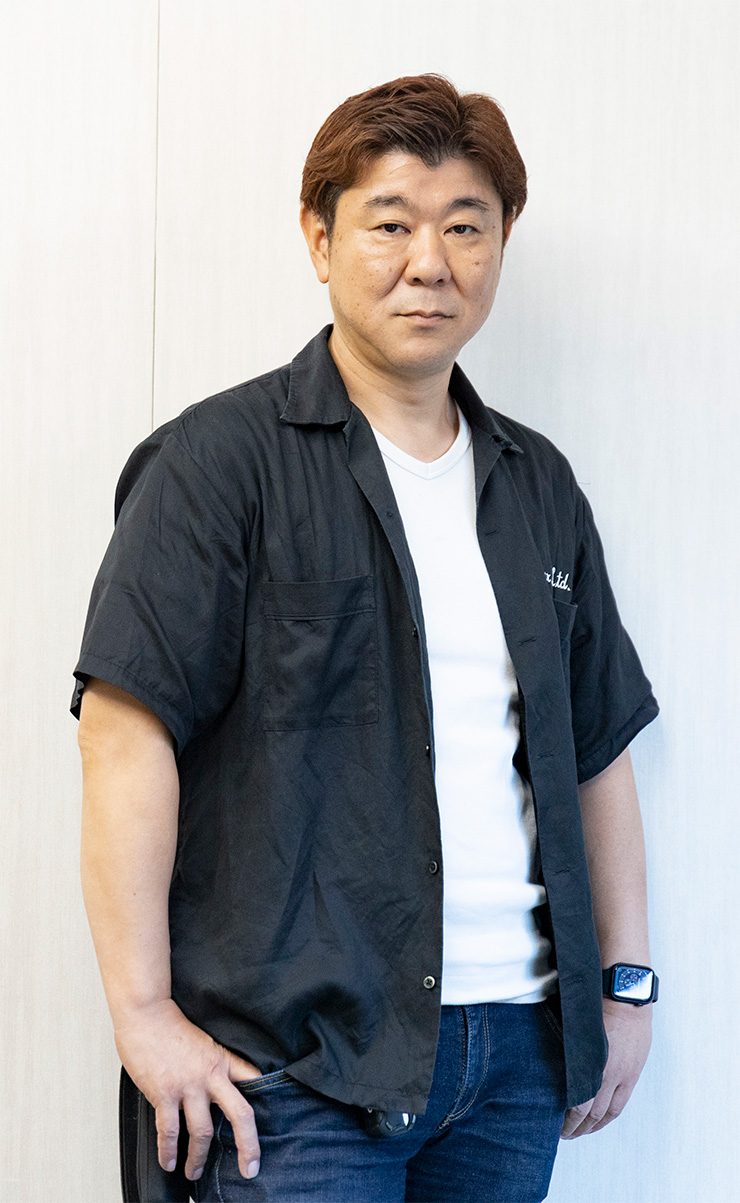
―― 自らの運命に決着をつけるため、ついに京都を目指して旅立った浮雲。江戸から東海道を上る旅は、最新作『邪鬼の泪 浮雲心霊奇譚』で岡崎宿(現在の愛知県岡崎市)まで到達しました。
前々作は川崎、前作は箱根、三島、吉原が舞台でした。今回なんとか岡崎までたどり着いたので、やっとゴールが見えてきたという感じですね。これまでのように宿泊先で誰かに出会って怪しい事件に遭遇して……というパターンをくり返すことはできるのですが、それだと京都に着くのが遅くなってしまう。次巻で一気に話を進めようと思っています。今回はそのための準備段階のような巻になっています。
―― 旅の仲間は、薬売りとして生計を立てつつ
一巻から六巻までのファーストシーズンは、自分の運命から逃げてちゃらんぽらんな生き方をしていた浮雲が、自分の運命と向き合う決心をするまでを描いた物語でした。浮雲がそう思えるようになったのは、
―― 遼太郎の正体は若き日の徳川
幕末の歴史において、徳川慶喜という人は異彩を放っているんですよね。敵前逃亡したとか否定的な評価もありますが、実は日本全体のことを一番よく考えていたのは慶喜かもしれない。今の政治を見ていてもそうですが、人は権力を握るとそれを自分や自分の属する組織のために使いたくなるじゃないですか。でも慶喜のとった一連の行動は、そうした私利私欲とはかけ離れている。そんな選択がどうしてできたのかといえば、若い頃に浮雲や土方と旅をして、いろんな人の生き様に触れたからかもしれない、という発想です。自分が子育てしていてつくづく実感しますが、人を変えるのはお説教やアドバイスではありません。むしろ何気なく目にした光景だったり、耳にした言葉だったりすることが多い。このシリーズでは遼太郎が、徳川慶喜としてなすべきことを見つけ出す、というところまで繫げていきたいと思っています。
土方歳三はなぜ「鬼の副長」になったのか
―― 毎回、さまざまな妖怪・怪異を扱ってきたこのシリーズ。今回のテーマは〈鬼〉です。茶屋に入った浮雲たちは、宿場町に人を喰らう鬼が出るという噂を耳にします。
鬼についてはいろいろな捉え方がありますよね。たとえば昔の人が外国人を見てそう思ったんじゃないか、とか。そうした鬼の正体みたいな話とは別に、鬼とは何ぞや、ということをあらためて考えてみたいと思いました。作中で浮雲が言っていますが、誰の心の中にも鬼が棲んでいる。そうした〝概念としての鬼〟を、さまざまな視点から書いてみたいなと。毎回扱う怪異はできるだけ物語と深く絡めたいと思っています。
―― ごろつきに追われている寺の小僧を救うことになった浮雲たちは、鬼の面を祀っているというお寺・滝川寺に向かいます。一方、別行動をとっていた土方と宗次郎は、神社で子供の惨殺された死体を目撃。町の人によれば、「滝川寺の鬼がやった」というのですが……。
鬼について調べてみると、二つのイメージがあるんですね。ひとつは皆さんがイメージする、残酷で乱暴で、人を捕まえて喰う鬼。そしてもうひとつが邪悪なものを追い払ってくれる、守り神のような存在です。名前は変えましたけど、実際滝川寺のように鬼を祀っているお寺もあるんですよ。つまり見る人によってイメージが変わる。その両極端の鬼の姿を、物語にも落とし込みました。
―― 鬼に子や孫を奪われた人たちの話を聞いた土方と宗次郎は、鬼が出るという廃屋に足を向けます。そこで出会ったのは川崎宿の一件(『火車の残花 浮雲心霊奇譚』)で土方と深い関わりを持った、若き暗殺者・
セカンドシーズンでは土方をメインに据えようと考えていました。若い頃は多摩のバラガキ(乱暴者)と呼ばれていた土方が、
―― 廃屋を訪れた土方が、「まるで、おれが鬼のようだな」と考えるシーンがあります。
近藤勇は大義のために戦った人だと思うんです。でも土方の人生を見ていると、純粋に戦いのために戦っていたという気がするんですよ。彼の中には暴力性があったんだろうなと思います。それが幕末という人の命が簡単に奪われる時代と出会ったことで、目覚めることになったんじゃないか、というのが僕の仮説ですね。もしかしたら現代に生きていたら、土方も普通にサラリーマンをしていたかもしれない。そんな運命のいたずらも感じます。
現代社会とも響き合う、
自分とは違うものへの偏見
―― 幼い頃の千代は、人と異なる外見のために鬼の子として差別されていました。また浮雲たちが滞在する滝川寺の僧侶たちは、鬼に怯える村人たちによって嫌がらせを受けています。現代とも通じるような、マイノリティへの差別や偏見の構図が浮き彫りにされていきます。
まさに現代にも置き換えられる話ですよね。SNSでもこの人は叩いていい相手だとなったら、すごい勢いで攻撃が集中するじゃないですか。人と違うことに対する拒絶感がすごい。昔の村社会もこんな感じだったんだろうなと思います。これは朝井リョウさんの『正欲』に書かれていてなるほどと思ったんですが、「あいつやばいよね」「そうだよね」と言い合うことは一種の確認作業なんでしょうね。自分は正しい側にいるんだと確認することで、安心したいという気持ちの表れです。
―― 千代への差別を知った宗次郎の「変なの」という反応が印象的です。宗次郎にとって重要なのは相手が強いか強くないか。見た目の違いはまったく関係ない。しかし宗次郎のように、偏見から自由になるのは難しいですね。
この作品の
―― このシリーズには黒幕的なキャラクターが二人登場します。幕府側に立ってさまざまな策を弄する呪術師・
これまでは両方と距離を取ってきましたが、それが許される状況ではなくなってくる。それは土方だけじゃなく、遼太郎にしてもそうですよね。ゆくゆくは自分の立場を明らかにして、敵味方をはっきりさせないといけない。その意味でやっぱり浮雲という主人公は異色なんですよ。信念を持って「どっちつかず」を貫いているので。それは卑怯ともいえるんですが、人を殺すのを徹底して避けるというのもひとつの生き方ですよね。ある意味、現代っぽい価値観ともいえる。人の命が簡単に奪われた時代だからこそ、そんな浮雲の存在感が際立つのかなとも思います。
―― やがて宿場町を騒がせていた鬼の正体が判明。浮雲によって明かされる事件の真相は、この時代ならではのトリックが使われていて、シリーズ内でもかなり本格ミステリー度が高いものになっています。
ミステリー的な技術については、新潮社で『ラザロの迷宮』を書いた時に新井さん(新井久幸氏。新潮社の編集者として多くのミステリー作品を手がける)にかなり鍛えられましたから(笑)。手がかりは前の方に置かないといけないとか、伏線は分かるように書くべきだとか。その教えが残っているので、ミステリーとしての精度はこれまで以上に上がっていると思います。今回は物語よりも先にトリックができていましたね。鬼に子供が襲われているという状況を使って、何ができるんだろうと考えて、あの部分の仕掛けを思いつきました。現代では成立しないトリックなので、このシリーズらしい真相になったなと思っています。
―― トリックもそうですが、動機の部分がかなり衝撃的ですね。人が一線を踏み越えて、鬼になってしまう怖さや悲しさが伝わってきます。今回はいつにも増して、人間のさまざまな
それこそ京極夏彦先生みたいに、事件から登場人物の心理、物語のテーマまですべてをひとつの妖怪に象徴させて、なおかつ読者の認識をぐるっと変えてしまうような小説が理想です。あそこまで完璧なものはできなくとも、鬼を扱った必然性やそこから生まれる感情、情念みたいなものはしっかり込めるように意識しました。今回の反省点があるとすれば、いつもよりシリアスになってしまったこと。重たい事件ですし、土方メインの話なので仕方がないとはいえ、もうちょっと浮雲に軽口を叩かせてもよかったかもしれない。浮雲と土方の軽妙な掛けあいもこのシリーズの楽しさだと思っているので、次回はもう少し増やしたいですね。
物語も佳境、次巻ではいよいよ京都へ
―― 物語のクライマックスでは、〝狼〟と呼ばれていた土方が〝鬼〟になる瞬間が訪れます。シリーズにとっても、またその後の日本の歴史にとっても大きな転換点ともなるシーンです。
このシーンはずっと前から考えていました。土方がある人物を守るために、とうとう一線を越えてしまう。書きたかったシーンが書けて満足しています。それと関連して遼太郎の変化も描くことができました。これまでは逃げ回っているばかりでしたが、次期将軍になるほどの人ですから当然剣術指南も受けていて、戦っても強いはずなんです。これまでと大きく変わった土方と遼太郎が、次の巻でいよいよ大きなうねりの中に飛び込んでいくことになります。
―― 神永さんは代表作の「心霊探偵八雲」をはじめ、多くのシリーズを併行してお書きになっていますが、「浮雲心霊奇譚」にしかない魅力といえばどこになるでしょうか。
時代が持つ熱量やダイナミックさは、現代劇では絶対に出せない部分ですよね。侍が刀を下げて歩いていて、罪人の斬首が庶民のエンターテインメントだった時代ですから、現代とは倫理観も価値観もまったく違います。それは物語のテイストにも絶対影響しますよね。携帯電話や警察の科学捜査がないというのも大きいです。「心霊探偵八雲」ではいつもその部分の整合性で苦労していますが(笑)、「浮雲心霊奇譚」はいい意味でアバウトでも許される。そこが力強さを生んでいるのかなと思います。
―― 次巻はついに京都編でしょうか。浮雲、土方、遼太郎がどんな事件に巻き込まれ、幕末の京都でどんな役割を演じるのか。今から楽しみです。
今回は地域色をあまり出せませんでしたが、京都には京都ならではの怪異が山ほどあるでしょうからね。京都に根付いた怪異や事件を取り上げたいと思います。まだまだこのシリーズは面白くできる、という手応えがあるんですよ。毎回インタビューを受けるたびに同じような話をしていますが、もっと上を目指したい。他の作家さんの書いた面白い小説を読むと、刺激を受けますし、負けていられないと思います。最近は連城三紀彦先生の作品を読んで、さりげない文章の向こうに広がる情念の世界に圧倒されています。普通、デビュー二十年を迎えると作風が安定するものらしいですが(笑)、僕はまだまだ変わるつもりですし、進化できるとも信じています。

神永 学
かみなが・まなぶ●作家。
1974年山梨県生まれ。日本映画学校卒。2003年『赤い隻眼』を自費出版。同作を大幅改稿した『心霊探偵八雲 赤い瞳は知っている』で04年プロデビュー。代表作「心霊探偵八雲」をはじめ、「天命探偵」「怪盗探偵山猫」「確率捜査官 御子柴岳人」「浮雲心霊奇譚」「殺生伝」「革命のリベリオン」「悪魔と呼ばれた男」などシリーズ作品を多数展開。他に『コンダクター』『イノセントブルー 記憶の旅人』『ガラスの城壁』『ラザロの迷宮』がある。https://kaminagamanabu.com/





