[連載]
第3回ニッポンの音楽は「世界 」を目指す
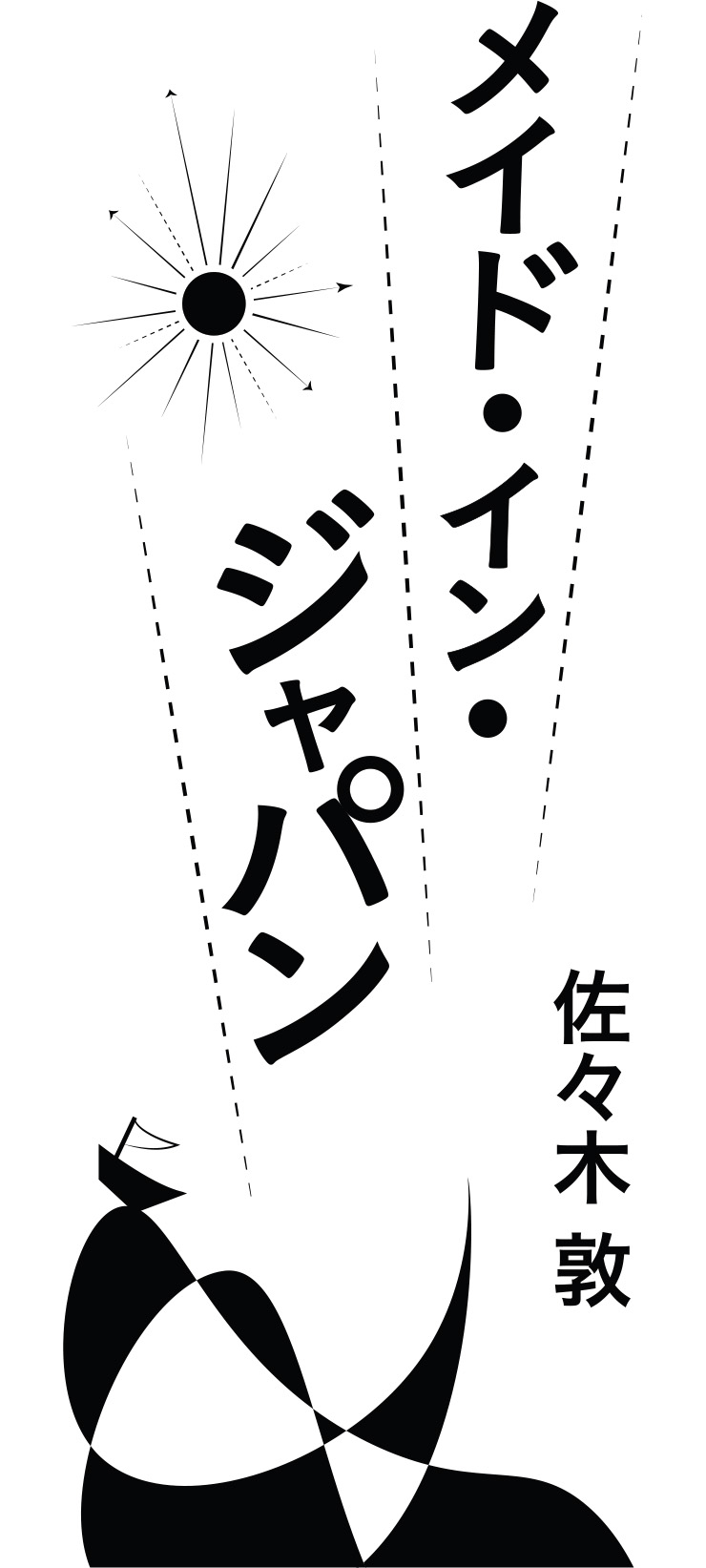
スキヤキ、食べますか?
前回、BTSの米国ビルボード・チャートでの快進撃がK‐POPのグローバル戦略のブースターになったと述べました。「アメリカで非英語詞の曲が売れることは極めて稀なこと」であるからです。しかしご存知の方も多いと思いますが、BTSより半世紀以上も前に、日本の歌手が日本語で歌った曲がビルボードで1位になったことがあります。坂本九の「上を向いて歩こう」です。「上を向いて歩こう」は、永六輔の作詞、中村八大の作曲で、もともと中村が1961年7月に開催された彼自身のリサイタルのために準備した曲でしたが、そこで歌唱を担当した坂本九のシングル曲として発売されることになりました。坂本は当時19歳で、すでに若手ロカビリー歌手としてアイドル的な人気を誇っていました。ミドルテンポでウェットな雰囲気のこの曲を歌うことは坂本にとっても挑戦だったようです。
しかし結果として「上を向いて歩こう」は大衆に広く受け入れられ、まず日本国内で大ヒットしました。オリコン・チャートはまだ存在していませんでしたが(1968年に開始)、発売3ヶ月で30万枚を突破、坂本はこの曲で1961年の「NHK紅白歌合戦」に初出場を果たしました。
翌年(1962年)、イギリスのケニー・ボール楽団が「上を向いて歩こう」を「SUKIYAKI」と改題して歌抜きのインストゥルメンタル曲としてカヴァーし、全英チャートでベストテン入りする大ヒットになります。同楽団はトランペッターのケニー・ボールが率いる、デキシーランド・ジャズを基調とするグループです。現在ならば間違いなく大炎上しているだろう「スキヤキ」という国辱的(?)な曲名は、ボールの所属レコード会社の社長が、出張先の日本から持ち帰ったシングル盤の中にあった「上を向いて歩こう」を大変気に入り、イギリスでジャズとしてリリースしようと思いついたものの、当然ながらタイトルが日本語でしか記されておらず、仕方なく自分の知っている数少ない日本語から「SUKIYAKI」という単語を選んで命名した、ということのようです(日本のすき焼きに舌鼓を打った思い出があったのかもしれません)。同様のことはヨーロッパの他の国でも起きていて、たとえばベルギーでは「Unforgettable Geisha Baby(忘れられないゲイシャベイビー)」(これも相当ひどい曲名ですが)と改題されて発売されました。
イギリスでのヒットを受けて、ケニー・ボール楽団の「SUKIYAKI」はアメリカでも発売されましたが、さほど話題にはなりませんでした。しかしアメリカのローカル・ラジオ番組にリスナーが日本のペンフレンドから貰ったレコードとしてオリジナルの「上を向いて歩こう」を送ってきて、「SUKIYAKISONG」として番組でオンエアされると、当時のアメリカのポップスにはなかった独特なメロディと坂本九の情感のこもった歌唱が忽ち評判を呼び、1963年5月に名門キャピトル・レコードから正式に全米リリースされました。するとビルボードの「HOT100」で3週連続1位、年間チャートでも13位を記録するなど、外国語曲としては極めて異例(それ以前はイタリア語のポップスが1位になったことがあるのみ)の大ヒットになったのです。情報伝達が現在とは比較にならないほど遅かったのでリアルタイムというわけにはいきませんでしたが、全米1位獲得というニュースは程なく日本にも伝わり、国内でも更なるヒットに繫がりました。坂本九は渡米し、人気テレビ番組にも出演、その効果もあって「SUKIYAKI」はアメリカ国内セールスが100万枚を突破し、外国人で初の全米レコード協会ゴールドディスク賞を受賞するに至りました。
「SUKIYAKI(上を向いて歩こう)」の海外での大成功には幾つかの偶然と幸運が作用していたと言えますが、歴史的な大ヒットになったのは大きく二つの要因があったのではないかと思います。ひとつは、単純に良い曲だったからということです。中村八大のメロディには、国や人種や言語を超えた普遍的な魅力が備わっていた。この曲にはオリジナルの英語詞と「SUKIYAKI」以外の曲名も含む複数の英語ヴァージョンがありますが、ソロシンガーだけでなく、ドゥーワップの男性コーラスグループやディスコ系の女性デュオによるカヴァーも知られています。最近ではブルーノ・マーズが2022年の来日コンサートで日本語と英語をミックスして歌っていました。アレンジや伴奏によって音楽のジャンルさえ違って聴こえるウェルメイドな旋律は、全世界共通の良質なセンチメントを備えています。最初のカヴァーがインストだったのも、メロディの良さによるものだったと言えるでしょう。
もうひとつは、1点目とは反対に、やはりこの曲が「日本製」だったからだと思います。実はキャピトルは坂本九に英語で歌わせることも検討したのですが、最終的にその案は見送られ、オリジナルそのままの全米リリースとなりました。1963年といえば、戦後20年も経っていません。多くのアメリカ国民にとって日本は未知の国だった。スキヤキは、フジヤマやゲイシャと同じく、ニッポンのステレオタイプを表す記号です。たとえ歌詞の内容とはまったく関係なかったとしても、ある意味でこの曲名は日本を知らないアメリカの人々のアテンションを呼び込むことに貢献したと言えるかもしれません。キャピトルは当初、すでにヨーロッパで使われていた「SUKIYAKI」を更にもじってKYUS
一見正反対にも思われる、普遍性と特殊性、翻訳/翻案(アダプテーション)に堪える弾力性とジャポニズム(オリエンタリズム)の合わせ技が「SUKIYAKI」の成功要因だったと、ひとまずは述べてよいように思います。そして、このことは極めて重要です。しかし、ここは話を先に進めましょう。
ピンク・レディーの挑戦
坂本九「上を向いて歩こう=SUKIYAKI」のアメリカでの大ヒットは、日本の音楽業界にとって、いわば伝説の成功モデルとなりました。その後、日本国内で頂点を極めた歌手たち、少なくともその一部は、次の目標として海外デビュー、もっとはっきり言えばアメリカ進出を夢見るようになった。なにしろ一度はビルボードで1位を獲っているのですから、絶対に不可能というわけではないことは証明されている。ここではまずピンク・レディーの挑戦について見てみようと思います。
ピンク・レディーはミー(現在の芸名は未唯mie)とケイ(現在は本名の増田惠子で活動)の二人組で、70年代に大きな影響力を持った日本テレビ系列のオーディション番組『スター誕生!』に合格し、1976年8月にシングル「ペッパー警部」でデビューしました。ティーンアイドル(デビュー時点で二人は18歳)としてはかなり珍しかった露出過多の衣装と、思わず真似したくなるようなユニークな振付け、阿久悠と都倉俊一の作詞作曲コンビによる斬新な楽曲によって、同曲は新人のデビュー曲としては異例の大ヒットとなり、ピンク・レディーは一躍スターダムに躍り出ます。セカンド・シングル「S・O・S」で初のオリコン1位、以後、「カルメン'77」「渚のシンドバッド」「ウォンテッド(指名手配)」「UFO」「サウスポー」と次々とスマッシュ・ヒットを飛ばし、70年代後半の芸能界を席巻します。私は1964年生まれなのでいうなれば直撃世代であり、2歳年下の妹が家の中でピンク・レディーを歌い踊っていたことをよく覚えています。テレビで彼女たちの姿を見ない日はなく(それどころか1日に何度も出ていました)、人気絶頂期の異常とも思える「不眠神話(睡眠時間があまりにも少なくて当時の記憶がない)」は、のちに物議を醸すことになります。
ピンク・レディーは1979年、アメリカのワーナーブラザースと契約し、シングル「Kiss In The Dark」で世界40ヶ国でのデビューを果たしました。海外進出に至る経緯は詳らかになっていませんが(レコードデビューに先立ち1978年4月にラスベガスでの公演を実現させています)、前年に「UFO」で悲願だった日本レコード大賞を受賞し(この曲はピンク・レディー最大のヒット曲であり、オリコンで10週連続1位を記録しました)、続く「サウスポー」(初のオリコン初登場1位)以降、セールスにやや陰りが見えてきていたことから、世界に向かうことで国内人気を復活させる狙いもあったのかもしれません。「Kiss In The Dark」に続き、同曲を含むアルバム『PINK LADY』もワーナーからリリースされました(『ピンク・レディー・イン・USA』として日本でも発売)。
「Kiss In The Dark」は、ショーン・キャシディやレイフ・ギャレットなど人気ティーンアイドルの楽曲を手がけていたマイケル・ロイドの作詞作曲で、完全な英語曲です。軽快なディスコのリズムと流麗なストリングスをバックにミーとケイがノリノリで歌うキャッチーな曲で、ビルボードの「HOT100」で最高37位まで上昇、ピンク・レディーは「SUKIYAKI」以来の快挙を成し遂げました。とはいえ、「Kiss In The Dark」は以前のピンク・レディーの曲とは全くと言っていいほどテイストが異なっており、アメリカ側が、それまでにピンク・レディーが日本で培ってきたイメージとはほぼ無関係に彼女たちを売り出そうとしたことは明らかです。1980年にはアメリカ3大ネットワークのひとつであるNBCでコメディアンのジェフ・アルトマンとピンク・レディーがパーソナリティを務める歌謡バラエティ番組「Pink Lady and Jeff」が全5回にわたって放送されましたが、たびたびミーとケイはビキニの水着姿にさせられており、ジェフの早口のジョークへの受け答え(主にミーが担当)は英語台本を暗記してこなしているように見えます。つまり、かなり露骨にお色気路線を強いられていて、そこには「ジャパニーズ・ガール」への即物的な欲望も感じ取れます。もちろん、この頃のアメリカでの若い女性タレントの扱いも似たようなものだったのかもしれませんが、ピンク・レディーの場合はそこにジャポニズム/オリエンタリズムもあからさまに入っている。「Pink Lady and Jeff」は動画サイトを探せば今も観ることができますが、空疎な笑いに潜む差別的な視線は、現在の感覚からすると、かなり厳しいものがあります。
そのせいなのかはわかりませんが、ピンク・レディーは1980年春にアメリカから帰国し、再び日本で活動することになりますが、同年9月に七ヶ月後の解散を宣言、1981年に解散に至ります(その後、二人はソロ歌手/俳優に転向、何度かピンク・レディーを再結成した後、2010年に解散を完全に撤回して、それ以後はマイペースで活動しています)。
ピンク・レディーのアメリカ進出は、セールスやプレゼンスという面では一定の成功を収めたと言えるでしょうが、いかにもありがちなパターンに嵌ってしまった感は拭えません。「SUKIYAKI」との決定的な違いは、もちろん英語で歌わざるを得なかったということです。先に述べたように坂本九も英語詞で歌い直すことになる可能性もあった。そうなっていたら果たしてあれほどの結果になっていたでしょうか? 「Kiss In The Dark」もけっして悪くはないのですが、「SUKIYAKI」のように曲がひとり歩きして大ブレイクするという流れにはならず、なりようもなかった。それにピンク・レディーの場合、日本側もアメリカ側も「日本」を意識し過ぎたと言えます。それが売りだと、それこそ(それだけ)がセールスポイントだと思ってしまった。確かにそれはそうなのですが、ここには考えるべき逆説(?)が宿っているように思います。
ピンク・レディーの例に限らず、カルチャーにおける「日本の日本性」は両義的であり、それを頼りにするしかないとも言えるし、しかし頼りにし過ぎると罠に落ちてしまう。戦略的に振る舞おうとしても、うまく機能しない場合もあれば、向こうの勝手な誤解や偏見が、思わぬ結果を導き出すこともある。
イエロー・マジックとは何か?
この意味で語っておかなくてはならないのは、もちろんイエロー・マジック・オーケストラ(YMO)です。ただし、私は過去に『ニッポンの音楽』(2014年、講談社現代新書→増補・決定版、2022年、扶桑社文庫)および『「教授」と呼ばれた男─坂本龍一とその時代』(2024年、筑摩書房)でYMOについて詳述しているので、ここでは出来るだけ簡潔に要点をまとめてみます。
イエロー・マジック・オーケストラは、細野晴臣が70年代後半に発表した一連のソロ作、いわゆる「トロピカル三部作」─『トロピカル・ダンディー』『泰安洋行』『はらいそ』─の延長線上のコンセプトを持つプロジェクトとして1978年に結成したバンドです。言わずもがなですが、他のメンバーは坂本龍一と高橋幸宏、残念ながらすでに二人とも故人です。大瀧詠一、松本隆、鈴木茂と組んでいたはっぴいえんどや最初のソロ・アルバム『HOSONO HOUSE』では基本的に「英米のロックの日本(語)化」を試みていた細野は「トロピカル三部作」において、その名の通り、熱帯地方(ハワイや沖縄など)の音楽を下敷きにしたエキゾチック(その種の音楽は「エキゾチカ」とも呼ばれました)なサウンドを追求しました。細野に決定的な影響を与えたのは、『EXOTICA』という連作アルバムもある50年代の作曲家マーティン・デニーと、はっぴいえんどのラスト・アルバムに収録された「さよならアメリカ さよならニッポン」の共作者であり、細野とは長年の親交を持つヴァン・ダイク・パークスです。
マーティン・デニーが打ち出した、いかにも南国の楽園的な雰囲気のムード・ミュージックは、実は現実とは何の関係もなく、南島に行ったことさえなかったデニーがでっち上げた想像上の音楽でした。細野はYMOでデニーの「Firecracker」をテクノ・アレンジでカヴァーしています。ヴァン・ダイク・パークスはソロ・アルバムの2枚目と3枚目に当たる『ディスカヴァー・アメリカ』『ヤンキー・リーパー』で、ファースト『ソング・サイクル』で探求した古き良きアメリカ音楽─アメリカーナ、デキシーランド・ジャズ、オーケストラルな映画音楽など─から南下して、テックスメックス(テキサス~メキシコの音楽)やカリブ海沿岸のカリプソ、トリニダード・トバゴのスティール・パンなど、同じアメリカ大陸でも合衆国とは異なる音楽的要素を大胆に取り入れてみせました。
細野晴臣はデニーとパークスに
YMOのデビュー・アルバム『イエロー・マジック・オーケストラ』は1978年11月リリース。しかし当初の評価は芳しいものではありませんでした。あまりにも先進的過ぎて、メンバーのキャリアを知る者にさえ、かなりの戸惑いを与えたようです。その潮目が変わるのは、翌年の1979年にアメリカのA&Mレコードから同作がリリースされ、YMOが渡米して行ったライヴの演奏が大評判になったことでした(これに至るまでには紆余曲折があるのですが、詳しくは拙著や類書をお読みください)。アメリカでの鮮烈なデビューが日本に伝えられると、国内でも人気に火がつき、YMOは見る見るうちに国民的な人気者になっていくことになります。
YMOのブレイクはしばしば「逆輸入」と言われます。日本よりも先に海外で評価され、そのせいで日本でも話題になる、という回路を指す言葉ですが、ではどうしてYMOはアメリカで受けたのでしょうか? 「上を向いて歩こう=SUKIYAKI」と同じことが言えると思います。まず何と言ってもYMOの音楽が当時の世界水準ですこぶる斬新であり、且つクオリティも高かった、ということがひとつ。シンセサイザーをメインに使用するロックはすでに存在していましたし(クラフトワークやタンジェリン・ドリームなどのジャーマン・ロック)、打ち込みを駆使したダンスミュージックもありました(ジョルジオ・モロダーがプロデュースしたドナ・サマー)。しかしYMOほどテクノ(ロジー)を音楽性と密接に結びつけたバンドは未だかつてなかった。3人のメンバーがそれぞれ卓越したプレイヤー(楽器演奏者)でもあったことも大きかったと思います。機械に自動演奏させるだけでなく、自分たちも楽器をテクニカルに操れるということは、特にライヴにおいてはまぎれもない魅力だったはずです。
しかしそれと同時に、YMOが敢えて纏ってみせた仮装=イメージも効果的だったことは間違いありません。アルバム・ジャケットやライヴで彼らが着ているコスチュームは、実際には違うらしいのですが、中国の人民服に見えます。テクノカットと呼ばれた刈り上げのヘアスタイル、曲名にアジア的なワードを多用していること、ファースト・アルバムのUS版のジャケットにあしらわれた「電線芸者(ゲイシャの頭からコードが溢れている)」などなど、西欧から見た東洋のステレオタイプな表象(日本も中国も区別がつかない)を戦略的に戯画化することによって、YMOはオリエンタリズムを戦略的に利用し、アジアのはずれに位置する島国ニッポンから突如として現れた「黄色い魔術=テクノポップ」というイメージを自己演出してみせたのです。
ところで、じつに興味深いのは、ピンク・レディーの「Kiss In The Dark」が1 9 7 9 年5 月1 日、Y M O の『Yellow Magic Orchestra』が1979年5月30日と、同じ年の同じ月にアメリカでリリースされていたという事実です。もちろん両者の世界デビューにはそれぞれのプロセスがあり、何の関連性もない、単なる偶然なのですが。
そして、これも偶然ですが、アメリカの社会学者エズラ・ヴォーゲルが著し、日本語訳もベストセラーになった『ジャパン・アズ・ナンバーワン(Japan as Number One:Lessons for America)』も、1979年5月に原著が出版されているのです(日本語版も同年に出ています)。同書でヴォーゲルは「日本的経営」の特質を分析し、たった30年でアメリカを脅かすまでに躍進した日本の経済成長の秘密を解き明かそうとしています(ちなみにヴォーゲルは東アジアが専門で、中国にかんする著作もあります)。偶然とはいえ、西欧世界における日本への注目が、さまざまな次元で急速に増していた時期だったということは言えるかもしれません。
1963年の「SUKIYAKI」から57年(!)後、BTSが「Dynamite」でアジア人アーティストとして2度目のビルボード「HOT100」1位を獲得、これは英語曲でしたが、同年に「Life Goes On」で韓国語曲で史上初の1位をマークしました。半世紀以上、アジアの誰も頂上まで登り詰めることがかなわなかったわけですが、「Kiss In The Dark」の37位も、けっして悪い順位ではありません。しかし次のことは言えます。坂本九は幸運だった。ピンクレディーは健闘した。YMOは逆輸入された。しかしBTSはおそらく、狙いを定めて的を射抜いたのです。
佐々木敦
ささき・あつし●思考家/批評家/文筆家。
1964年愛知県生まれ。音楽レーベルHEADZ主宰。映画美学校言語表現コース「ことばの学校」主任講師。芸術文化のさまざまな分野で活動。著書に『「教授」と呼ばれた男──坂本龍一とその時代』『ニッポンの思想 増補新版』『増補・決定版 ニッポンの音楽』『映画よさようなら』『それを小説と呼ぶ』『この映画を視ているのは誰か?』『新しい小説のために』『未知との遭遇【完全版】』『ニッポンの文学』『ゴダール原論』、小説『半睡』ほか多数。




