[連載]
第2回 KPOPは世界を目指す
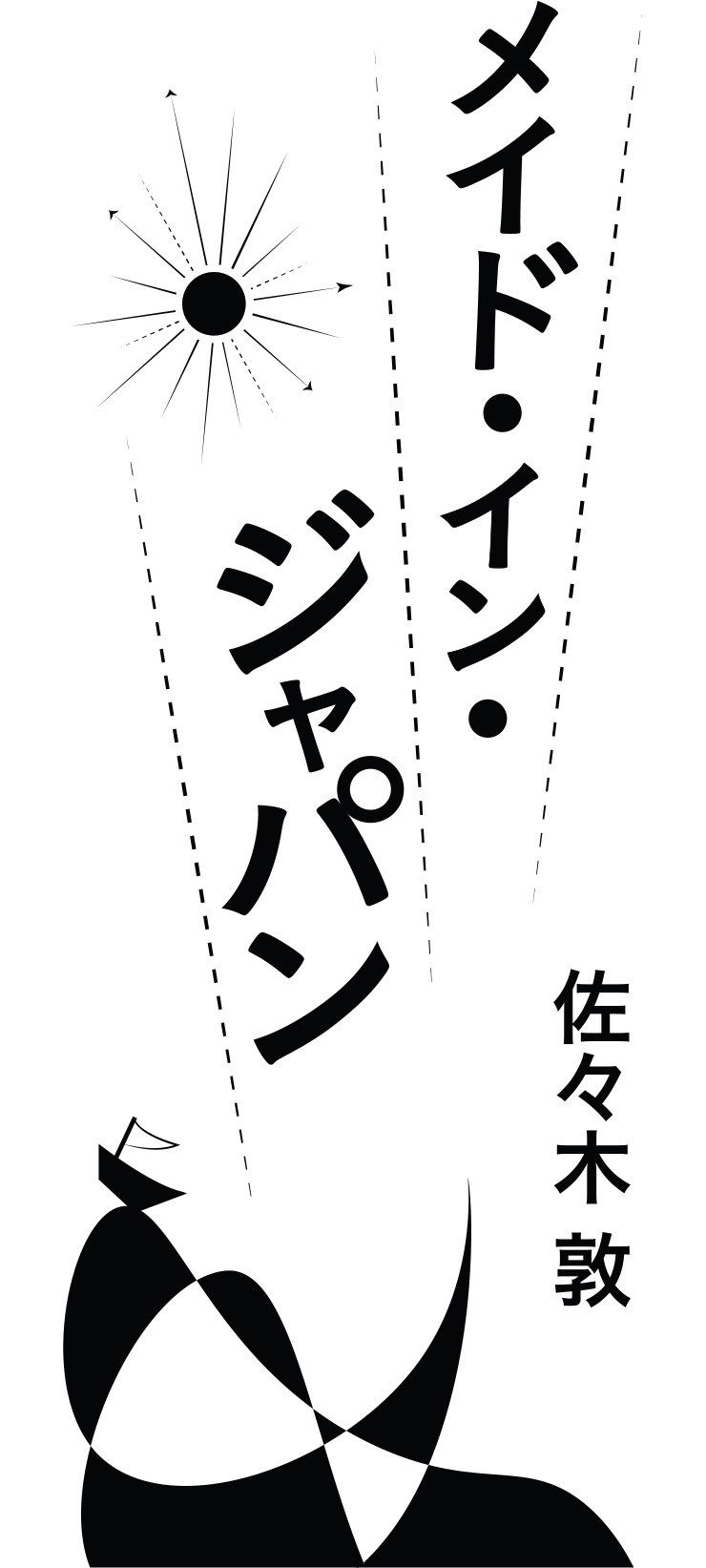
KーPOPの「第四世代」
K‒POPが世界を
2020年代から始まった「K‒POP第四世代」の波(現在はすでに「第五世代」に入っています)は、それ以前に国際的な大成功を収めていたBTS、BLACKPINK、BIGBANGなどのグローバル戦略を踏まえつつ、より洗練された方法論をもって、韓国以外の国々で猛威を振るっています。その中心になっているのは、言うまでもなく日本でも大人気のNewJeans(ニュージーンズ)です。「第四世代」のヨジャグル(女性アイドルグループ)には、その他に、aespa(エスパ)、Kep1er(ケプラー)、IVE(アイヴ)、LE SSERAFIM(ルセラフィム)、STAYC(ステイシー)、Billlie(ビリー)などがいます。「第X世代」という括りはメディアやファンダムによるもので、必ずしも「○○年から○○年までのデビュー組」というように厳密に決められているわけではありません。2018年デビューの(G)I‒DLE(アイドゥル)や2019年デビューのITZY(イッチ)なども「第四世代」と呼ばれることがあります。また、男性アイドルグループ=ナムジャグルで「第四世代」に括られているものには2010年代後半にデビューしたグループも多いです。ここでは主に最初に挙げたNewJeansなどの何組か、すなわちコロナ禍以後に登場したK‒POPのヨジャグルについて述べていきたいと思います。
そもそもなぜ、K‒POPは世界を目指すのか。いや、音楽だけではなく、周知のように、映画、ドラマ、文学などといった他のジャンルでも韓国文化のグローバルな躍進は著しい。日本でも過去に何度も「韓流ブーム」がありましたが、東京の新大久保に行ってみると平日でも昔の原宿の竹下通りを彷彿させるほどの人混みで、特に若い世代に韓国カルチャーは今や完全に根付いている感があります。なぜ韓国文化は「外」に向かうのか? それはまず何よりも、国が小さいからです。韓国の人口は約5156万人(2023年、韓国統計庁による)。日本の約半分です。経済発展のためには、文化産業に限らず輸出を重視せざるを得ません。また、日本と同じく韓国でも人口減少が急速に進んでいます(最近は「非婚」ブームも社会問題化しています)。ポップミュージックは2010年代以降、サブスクリプション(サブスク、定額ストリーミングサービス)が消費のベースになったこともあり、利益を上げ続けるには国内だけでは到底足りない。そこでグローバル戦略が火急の課題として要請されてきたというわけです。すでにBTSとBLACKPINKという直近の成功モデルが存在したということも大きかったと思います。
よく思うことですが、K‒POPのこのような事情はイギリスに似ています。英国も大きな国ではありません(2022年の統計で人口6760万人)。同じ言語を話すアメリカという巨大な国があるものの、ポップミュージックも国内消費だけでは覚束ない。ビートルズという不世出の人気者が出現したことによって、イギリスの音楽は成功モードを学んだ。新人バンド(など)がデビューする際、国内で音楽ジャーナリズムとともにメディアハイプを惹き起こし、すぐさま海外に打って出るという方式です(もともと海賊国家ですからお手の物です)。イギリスにとってのビートルズが、韓国にとってはBTSだったということです。
言語の問題
2020年9月1日、BTSのデジタルシングル「Dynamite」が、米国ビルボードの「HOT100」シングルチャートで初登場1位を獲得しました。韓国人アーティスト(K‒POP)として初の同部門での1位です。「HOT100」はビルボードの数あるチャートの中でも最大の影響力を持つものなので、韓国ではすでに天下を取っており、アメリカでの人気も数年前から急激に高まっていたとはいえ、これは歴史的な快挙であり、韓国内外の音楽専門ではないニュースメディアでも大きく取り上げられました。これをきっかけにBTSはグローバルな音楽市場でのトップクラスの人気を完全に確立することになります。
ただし「Dynamite」はBTSにとって初の完全英語曲でした。同年10月、2度目の「HOT100」1位となった「Savage Love (Laxed-Siren Beat)[BTS Remix]」(ジェイソン・デルーロ、Jawsh 685 とのコラボレーション曲)も英語詞曲でしたが、「Dynamite」も収録されているアルバム『BE』(2020年11月リリース)のタイトル曲「Life Goes On」によって遂に彼らは韓国語で歌った曲で「HOT100」の1位を射止めます。韓国語の曲が同チャートで1位になったのは史上初めてのことでした。快挙と言うならこちらの方かもしれません。なぜならアメリカで非英語詞の曲が売れることは極めて稀なことであるからです。
K‒POPの「英語ヴァージョン」は、もちろんそれ以前から存在していました(「日本語ヴァージョン」も同様)。アメリカ合衆国は非英語圏から来た移民の人々も英語を話さなければ生活していけない国です。アメリカの(特に都市部以外の)多くの人々は英語以外の言語を普段耳にすることすらなく、何を言っているのかわからない言葉で歌われても楽しい歌なのか悲しい歌なのかも不明だし、到底受け付けられない、というわけです。したがって非英語圏のミュージシャンがアメリカを目指す時、英語で歌うことは必須だと長年思われていました。詳しくは次回に触れますが、日本のミュージシャンの海外進出/米国進出の大きなハードルになってきたのも、この問題でした。
ところが、BTSはこの壁を破ったのです。もちろん「Dynamite」という英語曲の大ヒットがスプリングボードになったわけですが、これはやはり非常に重要な出来事だと言えます。BTSの実力と魅力あればこそですが、それだけでなく、私が思うに、この「快挙」には、もっと大掛かりな「変化」が作用しています。
非英語圏ポップスの「発見」
それはインターネット上の各種SNSや動画サイト、サブスクの浸透と拡大です。おおよそ2010年前後から全世界的に広く使われるようになってきた、これらのサービス/メディアは、英語しか解さない人々の非英語アレルギーを軽減する働きをしたと私は考えています。特に音楽にかんしては、ネットやSNSを介して非西欧/非英語のミュージシャンや楽曲、往年のアーティストや名盤などが、その言語がわからない外国のリスナーに「発見」されるということが頻繁に起きています。特に日本のポピュラー音楽は、その現象が顕著です。折しも全世界的に巻き起こったヴァイナル/アナログ盤リイシューのブーム――これ自体、サブスクに至った音楽のデジタル・データ化の流れからの揺り戻しです――も
つまり、ネット経由で「発見」した未知の言語の音楽に盛んに触れることで、何を言っているのかわからなくとも、歌=声もいわば音として楽しむことができる人が増えてきたのではないか、ということです。それに最近ではYouTubeの動画にも自動翻訳(字幕)の機能があったり、歌詞のテキストがあればGoogle翻訳だってかなり使えます。だから実際には「何を言っているのかわからない」ということもなくなってきている。こうして、かつては必須とされていた「英語」化をせずとも、非英語圏の人が母国語で歌ってもグローバルな人気を得ることが不可能ではない状況が生まれてきた。もちろん、とはいえそれが一定以上の大きなヒットになるには楽曲自体の良さやアーティストパワーが必要ですが、少なくともポピュラーミュージックにおける言語的条件が変容しつつあるということは確かだと思います。余談ですが、こう考えてみると、ある意味でかつての日本は現在の世界的な状況を先取りしていたと言えるかもしれません。残念なことに日本はアジアの中でも英語を解さない人が非常に多い国です。最近は変わってきましたが、昔はもっとそうでした。にもかかわらず、およそ30年くらい前までは、日本はいわば「洋楽大国」でした。歌詞がほとんどわからないのに英語の曲を好んで聴く人が大勢いたのです。そこでなされていたのは「英語を音として聴く」ということだった(もちろん歌詞カードなどもありましたが)。今でもアメリカのラップを耳だけでは何を言っているのかわからないのに聴いている人は多いと思います。リリックの内容も翻訳を通じて理解していると思いますが、それ以前に「歌=声を音として楽しむ」ことをしているわけです。
韓国語の優位性
話を戻しましょう。BTSが韓国語曲でビルボード1位を獲れたのは、繰り返しますが、BTSだったからです。しかしこの事実は、BTS以外/以後のK‒POPにとって紛れもない成功モデルとして機能します。つまりしかるべき条件さえ揃えば、韓国語だけでも勝負できるということです。むろん完全に韓国語だけで歌うのは、それこそBTSぐらいの超人気者でないと難しい。だが韓国語と英語をミックスした歌詞ならばいけるのではないか? 以前からK‒POPの歌詞には英語が(J‒POPに比べればはるかに)多く含まれていましたが、これ以降、その傾向が強まっていきます。現在では、二言語の配分がほぼ均等、曲によっては英語の方が多い場合もあり、韓国語オンリーの曲は珍しいくらいです。
韓国語と日本語は文法や語順がかなり近いので、ハングルさえ覚えれば、文章を読んだり書いたりすることは(初等レベルなら)比較的簡単にできます。しかし発音となると─日本語と韓国語はよく似た発音の単語も多いですが─かなり違います。韓国語には日本語にはない子音で終わる発音(パッチム/終声)があります。これは英語によく似ています。また、日本人が英会話を学ぶ際に最初の壁になりがちなLとRの発音の違いも、韓国語では明確に分けられています。こと発音にかんする限り、韓国語は日本語より英語に近い。これは歌詞においても韓国語と英語のミックスをスムーズにします。このことが際立って効果を発揮するのはもちろんラップで、韓国語と英語を自由自在に行き来するリリックを見事にこなすK‒POPアイドルは何人もいます。聞き流していると、二つの言語の混じり具合がわからなくなることさえあります。言語的な条件なので仕方ないのですが、日本語だとこうはいきません。日本語は母音が強く、英語との切り替えはどうしてもギクシャクしてしまいます(とはいえ最近はかなり改善されてきました。たとえば7月にリリースされたばかりのaespaの日本デビュー曲「Hot Mess」の歌詞は日本語と英語がミックスされていますが─韓国語はなし─かなり上手くいっています)。K‒POPは言語の特性上、世界進出に向いていると言っていいと思います。
とはいえ、K‒POPグループの多くは現在も、米国進出、グローバル戦略の手がかりとして、まず完全英語曲をリリースすることの方が多いのは事実です(aespaにも「Life's Too Short」「Better Things」の英語曲があります)。最近の成功例としては、日本でも非常に人気があるLE SSERAFIMが2023年10月にリリースした「Perfect Night」が挙げられます。この曲は世界的な人気を持つアクションゲーム「オーバーウォッチ2」とのタイアップでしたが、米ビルボードの複数部門で10週連続チャートインし、完全英語曲としては極めて珍しく韓国国内の各種チャートでも1位を記録しました。既発曲の英語ヴァージョンを出すことは昔からありますが、人気のK‒POPグループが英語のみの曲をリリースしたら、それはこれから米国上陸に本格的に挑戦するというサインです。そこに韓国語を混ぜるかどうかは、今のところは様子見の印象です。ただし先にも述べたように全体としてK‒POPの歌詞の英語含有率が増加しているので、殊更に英語圏デビューを謳わなくとも韓国語と英語のハイブリッド曲でグローバル・ヒットするケースはもちろんあります。
多国籍グループの戦略
NewJeansは韓国人3人+ベトナム系オーストラリア人+オーストラリア人(韓国人とオーストラリア人のハーフ)、aespaは韓国人2人+中国人+日本人(日本人と韓国人のハーフ)、Kep1erは韓国人6人+中国人+日本人2人、IVEは日本人が1名で他の5人は韓国人、LE SSERAFIMは韓国人2人(デビュー時は3人)+韓国系アメリカ人+日本人2人、STAYCとITZYは全員韓国人、Billlieは韓国人5人+日本人2、(G)I‒DLEは韓国人2人(デビュー時は3人)+中国人+台湾人+タイ人と、K‒POPは多国籍メンバーのグループが多いです(これはナムジャグルにも言えます。特に第四世代以後は必ずと言っていいほど日本人か中国人メンバーが入っています)。これはK‒POPグループがテレビやネットと組んだ、いわゆるサヴァイバル・オーディションによって誕生するケースが多いこと、そうでなくてもグローバル・オーディションやスカウトで研修生を集め、人によっては非常に長い、厳しいレッスン期間を経てデビューさせることが基本であることから来ていますが、日本では考えられない多国籍ぶりは明らかに意図的なものだと思います。韓国人以外のメンバーがいることで、その者の出身国でのプレゼンスや人気を得やすくなるということです。この傾向も近年強まっていて、(G)I‒DLEは外国人メンバーの方が多いですし、今やK‒POPには、韓国人が一人もいないグループさえ存在します。BLACKSWANは、セネガル系ベルギー人、アメリカ人、日系ブラジル人、ドイツ系ブラジル人、インド人の5人組で、デビュー時には3人いた韓国人メンバーが全員脱退してしまって以後、この編成で活動しています。しかし曲は韓国語だし、音楽番組や動画配信で彼女たちが話しているのも韓国語、スタイルも完全にK‒POPです。これはちょっと特殊なケースですが、今やK‒POPは「韓国(人)のポップミュージック」ではなく「韓国出自のポップミュージックのスタイル」を意味するものに変わってきていると言っていいと思います。実際、後で触れますが、K‒POPの方法論による韓国人抜きのグループは、最近次々と誕生しています。
ダンスかロックか
やや
私は数年前から、それまでは有名どころしか知らなかったK‒POPを熱心に聴くようになったのですが、最初に驚いたのは歌以外のサウンドがほとんど打ち込みで、且つベースとドラムス(ビート)がやたらと強調されていることでした。曲によってはヴォーカルを圧するほどの存在感を放っている場合もあり、基本的に楽器演奏者(バンド)がバックを担当し、歌以外はギターがいちばん目立っていることの多い日本の音楽とはまるで違うと感じました(K‒POPにはギターの音が入っていない曲も多いです)。
ここにはおそらく、スタジオ・ミュージシャンの人件費など予算の問題もあるのだと思いますが、結果として一部のK‒POPはダンス/クラブ系のグローバルで幅広いリスナー/ファン層への訴求力を獲得しています(この点も言語の障壁を超えられる要因のひとつだと思います。文字通り「声=歌」が「音」の一要素になっているのです)。特筆すべきはNewJeansでしょう。彼女たちの曲には、ヴォーカルを抜いてしまうとおそろしく音数が少ない、ミニマルなビートと最小限の上もの(シンセなど)のみで構成されているものが多い。その極度のシンプルさは衝撃的でさえあります。
しかし、これは「J」のディスアドヴァンテージのみを意味するわけではありません。たとえば日本が誇る超絶テクニックのバンド・サウンドを武器に世界に打って出ることだって可能です。そう、BABYMETALです。でも、少し話が先走ってしまいました。
ファンダムの効用
韓国には地上波とネットを併せて幾つも音楽番組があります。K‒POPの人気グループは活動期間(楽曲をリリースしてから数週間、期間を限定して集中的に活動すること)中、毎日のように番組に出演して曲を披露します。基本的に歌う曲は同じなので、飽きられないために必然的に番組ごとに衣装やヘアスタイルを大きく変えることが多く、その変化もファンの楽しみになっています。また、ほとんどの音楽番組は最後にその日の1位を発表する形式になっており、その算出の仕方も番組ごとに違うので、ネットやアプリを使った投票が結果に反映されやすい番組では、ファンは自分の推しに1位を獲らせるべく奮闘することになります(それ以外にもYouTubeの動画再生数やCDの複数買いなどで頑張っているわけですが)。音楽番組での1位の回数を「◯冠」と言います。
K‒POPのグループは音楽番組以外にも数多くのイベントやフェスティバル、ファンミーティングに出演します。そして、これも私がK‒POPをチェックするようになった時に驚かされたことだったのですが、そこでのパフォーマンスを観客=ファンがスマホで撮影した動画が大量に動画サイトにアップされているのです。実際には公式に認められているわけでも推奨されているわけでもないようなのですが、人気グループの場合、検索すればさまざまな角度から捉えられた動画を多数見つけられます。この行為は事実上(ほぼ)黙認されており、その結果、そのグループの存在をネットの力によって知らしめ、その人気を拡散・拡大することに明らかに貢献しています。
これはいまだに肖像権で儲けようとしている日本の芸能事務所では考えられないことです(と言いつつ最近は少し変わってきましたが)。一部のファンミーティングや大学祭(韓国の大学祭にはK‒POPのトップグループを
K‒POPのファンダム(公式ファンクラブ)には必ずニックネームが付いています。NewJeansはBunnies(バニーズ)、aespaはMY(マイ)、Kep1erはKep1ian(ケプリアン)、IVEはDIVE(ダイヴ)、LE SSERAFIMはFEARNOT(ピオナ)、そしてBTSはARMY(アーミー)です。ファンダムはグループの人気を高めるためにイベント参加や購買以外にもさまざまな活動を熱心に行います。その中には違法スレスレの行為や、そうでなくとも常識的に肯定し難い「やり過ぎ」もあったりします。一見すると、この感じは日本のアイドル・シーンに近いものがありますが(特にナムジャドルはかなり似ている部分があると思います)、色々と見ていくと、そこにはやはり違いがあるように思います。あくまで私見ですが、日本のアイドルファンは運営側/事務所にシンクロナイズしがちであり(そこには何かしら恩恵にあずかりたいという心情やアイドルに対する「上から目線」のようなものが透けて見えます)、対してK‒POPのファンダムは、自分たちが愛するメンバーが不当な扱いをされていると思ったら、事と次第によっては会社を公然と痛烈に批判することも
JとKのファンカルチャー/ファンビジネスには、それとは別の違いもあるように思います。これまで述べてきたことともかかわりますが、日本は「囲い込み型」、韓国は「開放型」だと思うのです。ファンを閉鎖的な生態系(集金システム)に閉じ込めてひたすら課金させていく方式と、ファンダムを大事にしつつも(実際、K‒POPのアイドルは事あるごとにファンへの感謝と愛情を口にします)、常に「ファン以外」「新たなファン」へと開いてゆこうとする姿勢の違いです。そしてこの違いは、アイドルや音楽に限ったことではないような気がするのです。
(つづく)
佐々木 敦
ささき・あつし●思考家/批評家/文筆家。
1964年愛知県生まれ。音楽レーベルHEADZ主宰。映画美学校言語表現コース「ことばの学校」主任講師。芸術文化のさまざまな分野で活動。著書に『「教授」と呼ばれた男──坂本龍一とその時代』『ニッポンの思想 増補新版』『増補・決定版 ニッポンの音楽』『映画よさようなら』『それを小説と呼ぶ』『この映画を視ているのは誰か?』『新しい小説のために』『未知との遭遇【完全版】』『ニッポンの文学』『ゴダール原論』、小説『半睡』ほか多数。




