[新連載]
輸出商品としての日本文化
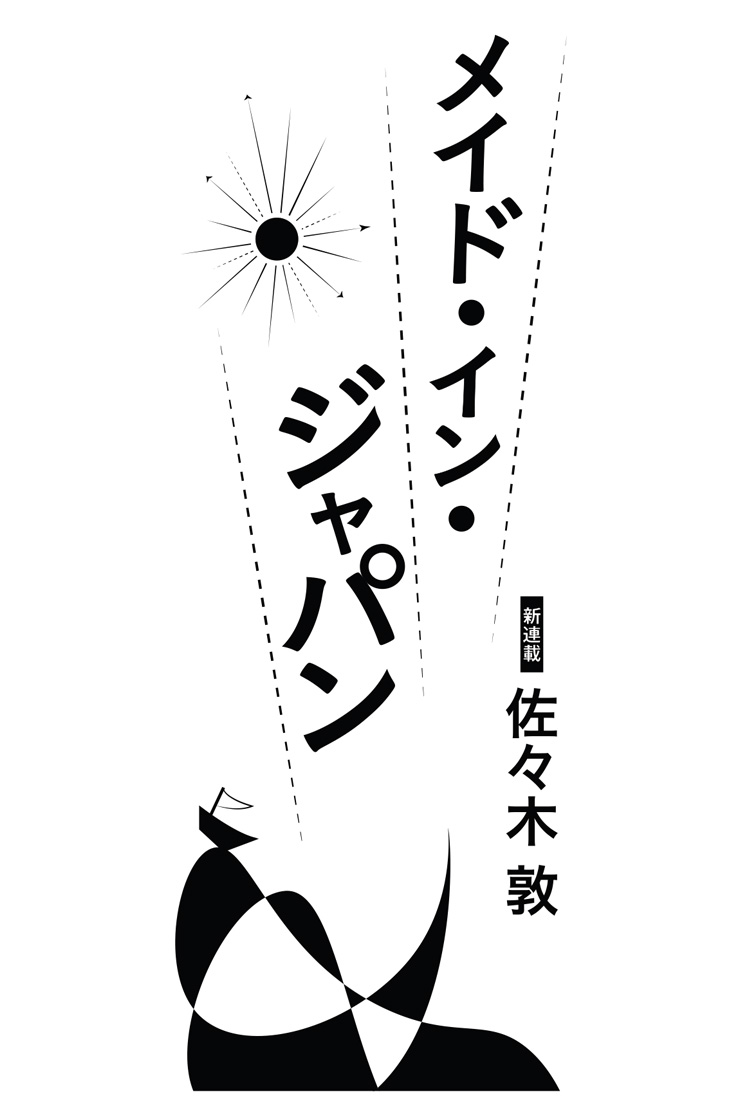
はじめに
本連載は、日本の芸術や文化、サブカルチャーの「海外進出」の可能性について、あれこれ考えてみよう、という内容です。
今これを書いている二〇二四年五月末、1ドルは157円台で推移しています。「歴史的円安」「超円安」などと呼ばれる状況です。円安傾向は、二〇二二年の春頃から始まりました。二〇二二年三月は1ドルの平均値が118円でしたが(それ以前は115円台までを推移)、四月に126円台に跳ね上がり、六月に130円を超えて以後、現在に至るまで一度も130円を割っていません。円安傾向は対ドルだけではなく、対ユーロも同様で、二〇二四年二月に平均値が160円を突破しています。
円安が今後もますます進むのか、それともどこかのタイミングで歯止めが掛かるのか、もちろん私は経済は素人なので何も予測はできませんが、いずれにせよ現在は、輸出業者にとっては非常に好ましく、輸入業者にとっては大変苦しい状況です。為替レートは、めぐりめぐって私たちの日々の生活や人生設計にかかわってきます。この連載で取り上げてゆく様々なカルチャーの分野でも、商品輸入という側面だけでなく、映像や音楽のソフト、印刷媒体などの製造費や流通コストにも影響してきますから、すでにどのジャンルでも市場規模が縮小しているというのに、文化的コンテンツの更なる価格上昇と売れ行き不振を招くことになるのは避けられない気がしてしまいます。
一方、円安のプラス面と考えられるのが、インバウンド消費の拡大です。日本では二〇二〇年に予定されていた東京オリンピックに向けて訪日外国人の増加を見越した大規模な設備投資や(関東に限らない)観光施設の整備などが推し進められました。周知のようにコロナ禍によって二〇二〇年の開催は中止され、一年後の二〇二一年の(かなり無理をした)開催となったわけですが、オリンピック以降、特にコロナが落ちついてからは、海外からの観光客は増えている印象です。
全国各地の観光地はもちろん、東京なら新宿や渋谷といった盛り場(以前から海外客は多かったですが最近はますます増えており、街を歩いていても日本語がほとんど聞こえてこないほどです)、インターネットで情報を得ることが容易になったせいなのか以前なら穴場とされていたようなマニアックな土地にも外国人観光客が押し寄せています。インバウンドの盛り上がりが円安によって拍車を掛けられていることは間違いありません。日本はデフレが長く続いてきたので特に外食産業の価格設定はもともと海外に比べてかなり安かったのですが、円安によって外貨を持っている訪日客には更にお得感が強まりました。その昔は日本人観光客が他国、たとえば東南アジア諸国を訪れて円高を武器に豪遊する、という蛮行が繰り広げられていましたが、現在は完全に逆転しつつあり、経済発展が著しいタイやフィリピン、ベトナムといった国々からの観光客が日本のモノの安さに驚嘆するといった現象も起きています。
インバウンドを狙った商売も色々と出てきていて、最近も観光地で外国人向けに料金を高額に設定したものが「インバウン丼」と
円安は海外展開する(ドル建てで商売をしている)日本の輸出産業にとっては強い追い風になっています。直近だとトヨタ自動車は二〇二四年三月期に売上高45兆円、純利益4・9兆円という「空前の好決算」(朝日新聞の表現です)を記録しました。トヨタの好調は円安のせいばかりとは言えませんが、大きな要因と言えます(「インバウン丼」と同様に値上げがしやすいという点もポイントだと思います)。トヨタのみならず円安による日本のグローバル企業の好調は歴然としており、にもかかわらず国内消費や好況感になかなか結びつかない、もっと端的に言えば私たちのような下々の者に「好調」が実感できないという問題も、しばしば報道されている通りです。いずれにしても輸出を軸にしている業者には「歴史的円安」は千載一遇のチャンスであり、今後しばらくは快進撃が続くでしょう。
さて、慣れない分野の前提の確認はこれくらいにしましょう。日本が海外に売り出せる(かもしれない)モノは自動車などの工業製品、あるいは先端技術だけではありません。「ニッポンの文化」はいかにして「輸出商品」たり得るか、それが本連載のテーマです。
なぜ、このテーマなのか?
先ほど、私は「経済は素人」だと述べました。これはまぎれもない事実ですが、しかし私は「文化」にかんしては、いわば玄人です。芸術文化、カルチャー/サブカルチャーの複数の領域で、気づけば三十六年も(私のライターデビューは一九八八年)色々と仕事をしてきました。主な活動分野は、音楽、映画、小説(文学)、舞台芸術ですが、現代思想やアートにかんする著作もあります。言うなれば私はそれなりの長きにわたって横断的/総体的に「ニッポンの文化」をウォッチしてきました。とはいえ、そんな私が、なぜこうして「輸出商品としての日本文化」論を始めようとしているのかについては、少し説明が要るように思います。
私は二〇〇〇年代=ゼロ年代の終わりから二〇一〇年代=テン年代の半ば過ぎにかけて三冊の新書を上梓しました。刊行順に挙げると、『ニッポンの思想』(二〇〇九年)、『ニッポンの音楽』(二〇一四年)、『ニッポンの文学』(二〇一六年)で、いずれも講談社現代新書からの刊行でした(その後に『増補・決定版 ニッポンの音楽』が二〇二二年に扶桑社から、『ニッポンの思想 増補新版』が二〇二三年に筑摩書房から、それぞれ内容を更新して文庫化されています)。「(現代)思想」「音楽」「文学」とジャンルはバラバラですが、『ニッポンの思想』と『ニッポンの文学』は一九八〇年代以降、『ニッポンの音楽』は一九七〇年代以降の、執筆時点の現在までの歴史を扱っていて、つまり三冊は時代が並行しています。著者としては、そこに面白みを感じてもいたわけですが、もうひとつ、この三つの「歴史書」には重要な共通点がありました。それはいずれも「輸入文化」についての本だったということです。『ニッポンの思想』は八〇年代、ヨーロッパ(主にフランス)のポスト構造主義哲学を日本に紹介した若きアカデミシャンたちがメディアに持て囃されてスター化した、いわゆる「ニューアカデミズム」と呼ばれた流行現象から語り起こされていました。『ニッポンの音楽』は一九六〇年代末に登場したはっぴいえんどというバンドが惹き起こした「日本語ロック論争」(アメリカで生まれて英語で歌われているロックを日本語でやれるのか、という今から思うとナンセンスとしか言いようのない論争)から話が始まっていました。『ニッポンの文学』は一九七九年、村上春樹の出現がスタートですが、春樹がアメリカ文学からの圧倒的な影響下で小説を書き出したことは有名です。つまり三冊とも「海の向こうで生まれた文化を日本にどうやって移植するか」という問いが(必ずしも明示的ではない部分も含めて)主題だったのです。
詳しくは三著を読んでもらえたらと思いますが、輸入文化としての「ニッポンの文化」は、八〇年代という戦後最高の好景気の時代を経て、すでにバブル経済は崩壊していた九〇年代の前半にピークを迎えたと私は考えています。そしてその後は「輸入」よりも(間接的・無意識的な「輸入文化」も含めた)「自国文化」の時代、内向きのドメスティックなカルチャーが主流の時代、時に「ガラパゴス」などと呼ばれもするような状況に入っていく。もちろん文化だけの話ではありません。九〇年代後半から、ニッポンは緩やかな「鎖国」に向かっていった、という言い方もできるかもしれません(「そんなことはない!」とか「それで何が悪い!」などと怒る人もいるかもしれませんが)。そして現在は? それをいま真っ向から問うのはやめておきましょう。
もちろんこれは敢えてかなり単純化した書き方をしています。実際には、かつての日本文化は「輸入文化」というより「翻訳文化」あるいは「(ポジティヴな意味を含む)誤訳文化」だったと思いますし、いわゆる「逆輸入」という現象も本論の重要なキーワードです。しかしまず入り口としては、輸入文化の時代が終わってかなり経った今、輸出文化としての日本のカルチャーの可能性を考えてみたいのです。過去数十年の「輸入文化」の蓄積のうえに現在の「ニッポンの文化」があるとして、それらが今や自閉的(鎖国的?)な鎧を身にまとっているように見えたとしても、そうなるに至った歴史性やそうなるしかなかったメカニズムも全て踏まえて、あらためて海の向こうに出てゆくことはできないか? それは絶対に不可能なのだろうか?
そんなことはないし、そんなことはあるまい、と私は考えています。だからこの連載は基本的にとても前向きな話になります。大きな商いのことはわかりませんが、私は自分がそれなりによく知っているつもりのニッポンのカルチャーにかんして、海外進出の未来を占ってみたい。「歴史的円安」が進行する今こそ、それを本気で考え始めるのにふさわしい時期だと思います。
けれども、やはりここで断っておく必要があると思いますが、かといって私は歯の浮くような現実離れした話、安倍政権下で
日本の三つの条件
どれも「そりゃそうだろう」と思われるようなことばかりですが、私は日本には少なくとも三つの特殊条件があると思います。
(1)島国であること
(2)日本語というマイナー言語を使用していること
(3)日本人という「単一民族幻想」が支配的であること
以上の三点です。日本国は陸上に国境が存在しない、周りを海に囲まれた島国です。日本人の大半は日本語というほぼ日本国内でしか使われていない言語を使っており、英語などの外国語を日本語と同じように使える人は、国際化が進んだとされる現在もごく一部です。日本には実際には多くの在日外国人が生活していますが、今なお「日本人=単一民族」という「幻想」は根強い。このような地理的・言語的・人種的な条件=制限が、日本の文化の土台を規定しています。
これらの三条件は「文化」の輸入/輸出という観点からも極めて重要な意味を持っています。(1)は現実的・具体的な輸出入、商品の運搬や送付にかかわってきます。インターネットがまだ一般的ではなかった九〇年代半ばまでは、海外の情報を得ることや海外の商品を買うことには具体的な困難が伴いました。テレビやラジオといった旧来の放送媒体か、雑誌などプリントメディアでしか海外カルチャーの動向は知れないし、海外のショップから商品を買おうにも、送料は高いし、かといって飛行機をやめて船便にするとすごく時間がかかる。それは逆もまた真なりでした。音楽や映画などの文化的コンテンツがアナログからデジタルに移行し、この三十年ほどのあいだに、インターネット~常時接続~検索エンジン~スマートフォン~ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)~サブスクリプションといった流れによって、文化のトラフィックやタイムラグの問題は大幅に解消されましたが、今でも空を飛ぶか海を泳ぐ(?)かしなければモノやヒトを日本の内外に移動させることはできません。このことはやはり大前提と言えると思います。
(2)は三つのなかで最も重要な条件です。先に日本の「輸入文化」は「翻訳文化(誤訳文化?)」だったと言いましたが、音楽がいちばんわかりやすい。はっぴいえんどが見舞われた「日本語ロック論争」は英語の音楽を日本語でやるという「翻訳」の問題だった。それはのちに「日本語ラップ」でも繰り返される議論です。また、字幕もしくは吹き替えがないと日本の観客が外国映画を観られないように、日本(語)映画は英語なり何なりの字幕を付けなければ(あるいは吹き替えをしないと)日本語を解さない観客─実質的にそれは海の向こうのほぼ全ての人々です─には観てもらえない。日本語で書かれた本も外国語に翻訳されなければ読まれない。単に輸出すればいいわけではない。そこにはどうしても「日本語」というマイナー言語を外国語に翻訳するというプロセスが必須となる。翻訳は知的な作業であると同時にそれ自体が一種の事業であり、商行為でもある。では「日本語の作家」は日本語で書いている限り、けっしてグローバル化できないのか。そんなことはありません。村上春樹という「日本語作家なのに外国語翻訳の読者の方がはるかに多いニッポンの小説家」が存在しているからです。しかし春樹の話はもっとあとに取っておきましょう。
(3)はかなりデリケートな問題を
というように、これら三つの「日本が日本であるがゆえの条件」が、この連載の出発点です。この三点を素直に受け入れつつポジティヴに反転させることが、本論の目標と言えます。
ニッポン人になるか? ガイジンになるか?
ニッポンのカルチャーがグローバル化する方法は、もちろんひとつきりではありません。これからジャンルごとに、その可能性を検討していきたいのですが、その前にあと少しだけ述べておきたいことがあります。
日本で生まれた日本人で、日本語を母語とする芸術家、アーティスト、クリエイターが、世界に出て行こうとするとき、すでに述べた三つの条件が様々な局面で立ちはだかります。それらは基本的に、やはりディスアドバンテージです。だからこそ「反転」の必要と可能性があるわけですが、かつては、それでも日本から海外に活動の拠点を移そうとするならば、そこで選べる道は二通りしかありませんでした。それは「日本人であることを武器にする」か、あるいは「日本人であることをやめる」かです。前者は要するにジャポニズムであり、オリエンタリズムです。詳しくは後の回で述べますが、古典芸能から連なるような日本の芸術文化(ある時期までのサブカルチャーも含む)は、日本独特の意匠を過剰に打ち出すことによって、歴史的経緯や文化的背景を共有しない海外の人たちから注目され、外部の視線に映る、いわば「年季の入った新奇さ」によって評価されたり人気が出たりした。芸妓や相撲、能や歌舞伎、比較的新しいところではアングラ演劇や暗黒舞踏などは、意識的であるかどうかにかかわらず、明らかに「日本の日本性」が(敢えてこういう言葉を使いますが)セールスポイントだった。たとえて言えば、ニューヨークをキモノで歩くみたいなことですね。日本ではむしろ古臭かったりダサかったりするような振る舞い、いでたちでも、それを異国の地で毅然としてやり続けることには意味や効果がある(場合もある)。要するに日本人なのに「ニッポン人」になる、ということです。
後者は明白だと思います。「日本人であることをやめる」とは、日本を出て行って、外国に居を定め、生活の
でも、ここで問わなくてはならない。ニッポン人になるか、それともガイジンになるか、この二択しかないのか? 第三の選択は考えられないのだろうか? 「日本の日本性」が前提条件であるとして、過度な日本らしさの仮装でもなければ、日本的なものの完全なる抹消でもない、三つ目の道。それはやはり「日本の日本性」を何らかの仕方で利用(逆利用?)することになるのだと思いますが、ではどういう手段が、いかなる戦略が、そこにあり得るのだろうか?
それをこれから考えていきたいと思います。「日本製=メイド・イン・ジャパン」のカルチャーの行き先を、幾つものジャンルや領域を経めぐりながら、ここまで述べてきたような問題意識のもとに、じっくりと探っていきたい。その果てに、いったいどんな光景が見えてくるでしょうか?
それはまだわかりません。でも、とにかく始めてみましょう。
まず最初は、音楽の話です。
(つづく)
佐々木敦
ささき・あつし●思考家/批評家/文筆家。
1964年愛知県生まれ。音楽レーベルHEADZ主宰。映画美学校言語表現コース「ことばの学校」主任講師。芸術文化のさまざまな分野で活動。著書に『「教授」と呼ばれた男──坂本龍一とその時代』『ニッポンの思想 増補新版』『増補・決定版 ニッポンの音楽』『映画よさようなら』『それを小説と呼ぶ』『この映画を視ているのは誰か?』『新しい小説のために』『未知との遭遇【完全版】』『ニッポンの文学』『ゴダール原論』、小説『半睡』ほか多数。




