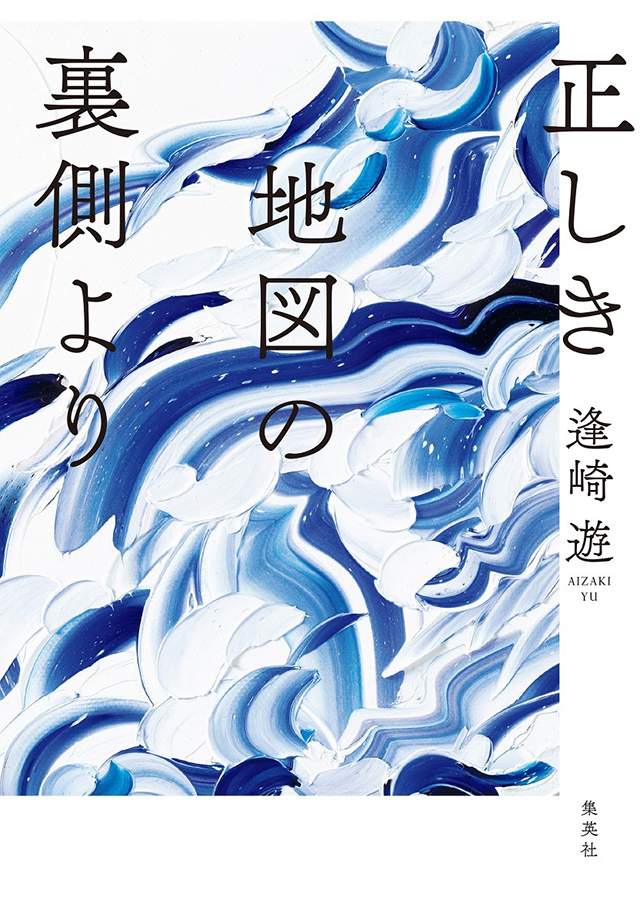[インタビュー]
自分に近い主人公に
旅をさせたいと思った
物心ついてから父と二人暮らし。生活のために定時制の高校に通いながら働く
『正しき地図の裏側より』(「遡上の魚」改題)で第36回小説すばる新人賞を受賞した逢崎遊さんは25歳。読み始めたら止まらないリーダビリティと先の読めない展開、社会からドロップアウトした主人公に寄り添って書き切った筆力は、これからの活躍を大いに期待できます。受賞作品について、これまでの歩みについて、逢崎さんにお話をうかがいました。
聞き手・構成=タカザワケンジ/撮影=大槻志穂

―― 逢崎さんは十八歳の頃から小説すばる新人賞への投稿を始められたそうですね。
はい。最初の作品が最終選考に残ったので、それ以降、七、八作くらい投稿してきました。
―― そもそも小説を書こうと思ったのはなぜですか。
高校二年の夏休みに、読書感想文か、創作文のどちらかを書けという課題があって創作文を選びました。その創作文が思ったよりもいい成績をもらって、創作って面白いかもと思ったのがきっかけです。
―― どんな内容だったんですか。
これを話すのは恥ずかしいんですけど、バンドをやる話なんです。十代の頃って、なぜかバンドをやりたくなるじゃないですか(笑)。それで仲間と楽器を集めて軽音部に乗り込んだことがあるんです。剣道部のくせに。もちろん軽音部との実力差を見せつけられて、仲間たちととぼとぼ帰りました。その経験をレポート風に書いたんです。この経験をとおして小説にすれば失敗も成功に変わるんだなと知って、書くことの心地よさを感じました。
―― 創作の喜びを知ったんですね。でも、夏休みの課題と、小説すばる新人賞の応募規定にある原稿用紙二百~五百枚という分量とはだいぶ差がありますよね。
課題は原稿用紙十枚くらいだったと思います。まず短いものから書き始めて、三十枚くらいになったところで、友達に読んでもらいました。僕は推薦で進学先が決まっていたんですが、周りは受験生だったので迷惑だったと思います(笑)。読んでくれた友達から「賞に応募しないの」と言われて、初めて文学賞の存在を知りました。せっかくだからめざしてみようと思ったんですが、いきなり長編は書けなかったので、短編を五つ書いて出したのが最初の応募作です。
―― 連作小説だったんですね。内容は?
章ごとに主人公が替わるタイプの青春群像劇でした。とある学校に有名な生徒がいて、五人それぞれの視点でその子について語るという、まるまる朝井リョウさんの『桐島、部活やめるってよ』パターンでした(笑)。それがなんと最終選考に残ってしまったんです。十八歳でいきなり最終選考まで行ったので、俺って才能あるんだって思ってしまいました。それから書き続け、応募し続けたんですが、箸にも棒にもかからずという状態になって苦しい時期がありました。
―― 受賞作の『正しき地図の裏側より』は、これまでの作品と取り組み方に違いはありましたか。
書き始める前に、いつも僕の小説を読んでくれている彼女から「あなたは自分の話を書いたほうがいい」と言われました。それまではエンタメ系の賞だからと、推理ものに手を出してみたり、ハードボイルドを書いたり、恋愛ものや企業ものを書いたり。沖縄出身なので、沖縄の話を書いたこともあります。でも、自分らしさはなかったかもしれないです。彼女の一言で、たしかに今の自分なら自分に近い主人公を書けるかもしれないと、この作品を書き始めたんです。それまで書いてきた作品とは少し違って、憑きものがすとーんと落ちたように感じたのがこの作品でした。なので、ちょっと特別な感じはありましたね。
――『正しき地図の裏側より』は、父を殴り雪の中に放置した青年が都会に出て、逃亡しながら自活していく話です。プロットはあらかじめ立ててあったのでしょうか。
新人の自分が言うと、おまえごときがと言われそうですが、小説は構造的な小説と感情的な小説とに分けられると思います。僕は感情的というか、人間の内側にあるものや、人間模様を小説で書きたい。まず、それらを最後まで書き切れそうな土台となる設定をつくって、先がどうなるか分からないまま書き進めていきました。『正しき地図の裏側より』でいえば、細かいところは決めずに主人公に旅をさせた感じですね。
平成初期にここで暮らしていたら
――『正しき地図の裏側より』の舞台は平成初期、一九九〇年代初頭です。逢崎さんはまだ生まれていませんよね。知らない時代を書こうと思われたのはなぜでしょうか。
父の影響があると思います。父は自分のことをあまり話さないんですが、若い頃に上京していろいろな仕事をしていたという話をしてくれたことがあるんです。父は父と同世代の人たちと価値観がちょっと違っていて、いい大学に入って大きな会社に就職して定年まで勤め上げる、という生き方ではなく、仕事があるならどこへでも行きます、みたいな人なんです。それは若い頃の経験から来ているのかなと思いました。自分の力で生きていた若い頃の父親を想像すると、すごく魅力的に感じたんです。
それと、自分に近い主人公を書こうと思ったときに、現代の日本よりもゆるくて土臭さの残る都会で、隙間を見つけて逃げていくような主人公を書きたいなと思いました。
想像ですけど、あの時代って、人と人とのつながりが今よりも強いと思うんです。今のように簡単につながれない分、一度つながったら簡単に離れられないというか。主人公に感情を揺さぶられるような旅をさせたいと思ったときに、自分と父親のちょうど間ぐらいの世代がいいだろうと思って、物語の年代を決めました。
―― 時代背景を詳しく書き込んでいるわけではないので、意識せずに読んでも面白いと思いますが、あの時代を知る読者にとっては登場人物たちに懐かしさを感じると思います。ホームレスの三浦さん、主人公に転機をもたらす相葉のおっちゃんなど、何とも言えない味があります。
ありがとうございます。具体的にこの人はこの人をモデルにしたというのはないんですが、自分自身がそういう人たちに出会ってきたんだと思います。話をしてみて「こんなことを考えているんだ」と見た目の印象とのギャップを感じたり、「この人の常識はこうなのか」という驚きだったり。出会いと別れの中で経験してきたことがヒントになっていると思います。
主人公が送るホームレス生活についても、僕自身はホームレスになったことはないですが、ある程度調べたうえで、これまでアルバイトや日常生活の中で経験したことをもとに想像して書きました。たとえば、主人公とホームレスの人が縄張りを巡ってトラブルになる場面がありますが、主人公はがんばった分だけ稼ぐのは当然だと思っている。でも、ホームレスの先輩たちは、一人が稼ぎ過ぎるとほかの人たちが生活できなくなると思っている。お互いの価値観がぶつかってもめ事になる。それはホームレスの世界でなくても、同じようなことがあると思うんです。
―― 小道具の使い方も印象的ですね。タイトルにもなっている地図もそうですし、時計とか自転車とか、人が思いを託したモノが重要な役割を果たしています。
自分ではまったく意識していませんでした。そのときにこの人に必要なものは何だろうと考えて時計が出てきたり、このときにはこれがほしいだろうと地図が出てきたり。想像で膨らませて書いたものが、意外なことにのちのち大きな意味を持ってきました。
たとえば自転車ですが、最初は主人公が空き缶拾いをすることだけを決めていて、歩いて空き缶拾いをするのは効率が悪いから、自転車が必要だなと思ったんです。でも自転車を買うお金はないから、人からもらうか、捨てられていたものを拾ってくるしかない。もらうのは難しいから拾ってくるだろう。きっと壊れたまま放置されているから、自分で直すしかない。自分で直したことで思い入れが強くなり、あのエピソードが生まれました。筆が進んで自然と書いてしまったという感じです。
―― 自転車をどう扱うかに、彼の性格や考え方が表われています。また、スマホのない時代に街を知ろうと思ったら地図は必須です。私も一九八〇年代末に上京してきたとき、まず地図を買ったことを思い出しました。
ご自身の経験を思い出してもらえるというのはうれしいです。読んだ資料には、当時の人達が地図を買っていた、とはどこにも書いてないんですよね。でも、想像力で補完していった先に地図が出てきました。応募した原稿では、地図は一カ所か二カ所しか出てこなかったんですが、単行本化にあたってタイトルを変えてくださいと言われたときに、地図が象徴しているものに思い当たりました。主人公が街の裏側に入ってしまう話なので、彼は地図の裏側に行ったんだなと。そこから地図が出てくる場面を追加しました。
―― 地図は想像で出てきたんですね。
そうなんです。実際に僕がそこで暮らしていたらどうするだろうかと考えた結果です。読み終えた雑誌をコインランドリーで回し読みするエピソードがありますが、あれも雑誌を買っても捨てるのは面倒。だったら周りに恩を売っとこうとコインランドリーに置くんじゃないかと考えました。ここで実際に生活したら、こういうことが起こるんじゃないかという想像力の働かせ方をしていたと思います。作品の中の時代を自分の足で歩いている感覚がありました。
「余白」を意識した文章
――『正しき地図の裏側より』には複数の側面があります。いろんな人たちと出会って主人公が成長していく教養小説であり、彼自身が自分がどういう人間かを知っていく物語でもありますね。
これは何作か書いてきて思ったことなんですけど、僕は根が真面目らしいんです。でも、文学って、ちょっとふらふらしているような人を描いたものが多いですよね。太宰治の『人間失格』とか。僕も一時期、そういう人たちを書こうとしていたことがあったんですが、根が真面目過ぎて外れられないんです。くずになり切れないといいますか(笑)。
『正しき地図の裏側より』では、逆に真面目な主人公を書いて、今回、受賞という結果が出ました。真面目な主人公のほうが自分の性質に合っているのかなと思いましたね。
―― たしかに令和の青年が平成初期の都会を漂流しているようなところがあって、それも、今、書かれた小説として面白いと思いました。逢崎さんご自身のこともうかがいたいんですが、子供の頃から本を読んだり、物語に触れるのが好きだったんでしょうか。
小説よりも漫画や映画でしたね。小説を読んだ冊数は、同世代の人たちとあまり変わらなかったと思います。クラスに一人か二人いる、ずっと本を読んでいる子たちのレベルではなかったです。どちらかというと教室の端っこでよく分からないことではしゃいで、椅子壊しちゃうようなやつでした(笑)。
―― 記憶に残っている本はありますか。
ケストナーの『飛ぶ教室』が好きでした。物語で泣いたりしないほうなのに、なぜかあの作品では泣いてしまいました。中学生のときに読んだんですが、学校生活の風景に近かったこともありますし、仲間たちが助け合うようなシーンがあって「めっちゃいいじゃん!」って、ぐっと来ました。
―― 小説を書くうえで影響された作家、好きな作家はいますか。
影響を受けたのは、最初に賞に応募するきっかけになった朝井リョウさん。僕らの世代は朝井さん、辻村深月さんの影響が大きいと思います。小説を書き始めてからいろんな作家さんの作品を読むようになりましたが、どちらかというと尊敬よりも闘争心をかきたてられてしまって、生意気な発言なんですけど、目標にしたいというよりは乗り越えたいと思ってしまいます。作家としてのあこがれは北方謙三さん。あんなすごい作家になれたら、と思います。
―― 桑沢デザイン研究所で学ばれていますよね。デザインへの興味があったんですか。
桑沢に行ったのは、高校が沖縄の伝統工芸を学べる科だったのと、もともとものをつくるのが好きだったからです。でも、デザインに興味があったというよりも、東京で一人暮らしがしてみたかったことのほうが大きいですね。入学した矢先に小説すばる新人賞の最終選考に残ったという連絡があったので、そのときに小説家になろうと決心しました。それでデザイナーになろうという気持ちはなくなったんですが、小説を書くときに、デザインのときに使っていた脳の使い方をしているなというときはあります。
―― それはどんなときでしょう。
いいデザインって余白が多いんですよ。きちきちに詰まっているよりも、白の中にぽんと一つ置くみたいなデザインのほうがいい。でも、そのぽんをどこに置くかがすごく難しいんです。桑沢で余白をつくることを徹底的に鍛えられたので、文章においても余白をつくろうと意識しています。余白をつくって読者に想像力を発揮してもらいたい。そのために文章が説明的になり過ぎないようにしているつもりです。
―― 今回、デビュー作が出版されますが、作家は二作目が大事だとよく言われます。次はこういう小説を書こうというイメージはありますか。
今はまだ少しずつ書きながら考えているという感じです。今までは自分の好きなものを書いていましたが、小説家として世に出て行く以上、読者にとって面白いものを書かなくてはならない。これが二作目、と自分で思って書いたものでも、出版社から見ればダメだという可能性もあるので、まずは担当してくださる編集者の方と話し合いながら、どんな作品を二作目にするかを探っていきたいと思います。

逢崎 遊
あいざき・ゆう
1998年沖縄県生まれ。「正しき地図の裏側より」(「遡上の魚」改題)で第36回小説すばる新人賞を受賞。