[イベントリポート]
去る一月七日、茅ヶ崎市民文化会館大ホールにおいて《ふるさとと文学2022 開高健の茅ヶ崎》(企画監修:一般社団法人日本ペンクラブ/主催:公益財団法人開高健記念会/共催:茅ヶ崎市/協力:公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団)が開催された。
日本ペンクラブでは、二〇一五年の創立八十周年を機に、作家と作品に〈ふるさと〉と〈歴史〉と〈現代〉の光を当て、映像と音楽と語り、朗読と討論でライブ・ステージ化するシリーズ企画《ふるさとと文学》を立ち上げ、今回はその第八回となる。開高健は、一九七四年に茅ヶ崎市東海岸南に居を移し、以後亡くなるまでこの地を拠点に活動を展開した。その住まいは二〇〇三年、開高健記念館として開設。往時の書斎、原稿や愛用の品々が展示され、一般公開されている。
当日は、地元茅ヶ崎の住民をはじめ、多くの人たちが集い、没後三十三年となる現在もなお読者を魅了し続ける開高健文学の秘密に迫るパフォーマンスと語らいに熱心に見入り、耳を傾けた。


中村敦夫氏
茅ヶ崎市長・佐藤光氏と開高健記念会理事長・永山義高氏の開会挨拶の後、第一部の映像ライブ「戦争という原郷あるいは現況、そして幻境~開高健の人・作品・世界」が始まる。映像制作は映像作家の四位雅文氏。脚本は日本ペンクラブ前会長で、ベ平連(ベトナムに平和を!市民連合)で開高健と活動を共にした作家の吉岡忍氏。
一九三〇年十二月に大阪で生まれた開高健の生涯が、多彩な映像を背景に、活動写真弁士・声優の片岡一郎氏の力強い語りとヴァイオリニスト・佐藤久成氏の躍動的な演奏で綴られていく。
戦時中の父の死と勤労動員の苦労。戦争末期の大阪への大規模空襲。戦後の飢えと闇市。大学に進んでからの文学への耽溺、妻となる牧羊子との出会い、
専業作家になってからのノンフィクションへの挑戦、朝日新聞社臨時特派員としてベトナム戦争を取材。現地の戦争の模様が、ベトナムからの生々しい電話の声などを交えて伝えられていく。そして、ベトナムでの経験を凝縮した「闇三部作」(『輝ける闇』『夏の闇』『花終る闇』)の第二作『夏の闇』の最後の一行「出発は『明日の朝、十時だ』」で終わる。

竹中直人氏
続く第二部は朗読劇「
開高健との出会いを語る

桐野夏生氏
第三部はシンポジウム「開高健の茅ヶ崎」。司会はドリアン助川氏。パネリストは日本ペンクラブ会長・作家の桐野夏生氏、学際情報学の研究者で早稲田大学教授のドミニク・チェン氏、『長靴を履いた開高健』『開高健名言辞典』などの著者で作家の滝田誠一郎氏、そして開会の挨拶を述べた、『週刊朝日』に連載された『ずばり東京』『ベトナム戦記』の担当編集者でもあった永山義高氏。
最初に、開高健とどのようにして出会い、何が印象的だったのかが語られる。
滝田さんは、二十代で読んだ文庫本の『オーパ!』の解説で、

ドミニク・チェン氏
ドミニク・チェンさんは、米国のUCLAを経て東大の大学院に進んだとき、ドリアンさんに、目をキラキラさせながら「開高健というものすごい作家を見つけた」といったという。「今回、開高健の作品を読み直している中で、書き方がほかの同時代の日本人作家とちょっと違うところがあると気づいた。修辞の使い方、フレーズの長さとか、フランスの作家の文体を読んでいるような感触」を覚えたという。中でも印象に残っているのは、『輝ける闇』と『夏の闇』。「私の祖母がベトナム人で、祖父がベトナムの歴史を研究する台湾人だったということもあり、ベトナム戦争を生きた家族がいる身からして、あの作品を読むと、今起こっているロシアのウクライナ侵攻とも重なってくる」。
桐野さんの若い頃は「開高健を読まなければ人ではない、一人前の学生ではないみたいな、そのぐらいすごい存在」だったという。それにはやはりベトナム戦争が大きかった。「大学があった吉祥寺には、立川から米兵がジャズ喫茶などによく来ていた。その頃、おそらく吉岡(忍)さんは脱走した米兵を逃がすという運動をやっていたと思うのですが、そうした時代だったので、『輝ける闇』は本当にショッキングな作品」で、同時に「当時は文学がものすごく力を持っていた時代で、文学によって世界が変わる、あるいは自分の世界観が変わるみたいな絶大な力があった」とも。

永山義高氏
唯一開高健と仕事をしたことのある永山さんが最初に会ったのは、開高健が作家デビューしてから五、六年経った頃で、永山さんが『週刊朝日』編集部に配属されたとき。「当時開高さんはスランプに陥っていて、純文学が書けなくなっていた。そこで、先輩作家からノンフィクションをやったらどうだということで、ノンフィクションの世界へ入っていく。その代表作が『週刊朝日』に連載した二つの作品です。一つは東京オリンピックを機に変貌していくメガロポリスを活写した『ずばり東京』、そしてもう一つが『ベトナム戦記』です」。
また『ずばり東京』の取材先から帰ってきたとき、編集長に向かって「どないしてくれますんや。これで日本の文学が十年遅れまっせ」といっていたという。自ら望んでノンフィクションの世界に飛び込んだものの、やはり純文学に対する想いがそんな冗談をいわせたのだろうと。「なぜ小説が書けないのか」という問いに、「ぼくの心の中にごっつい批評家がいるのや」と答え、苦しみながらも純文学に取り組んでいる姿を伝えてくれた。
開高文学の源泉とは?
次に、開高健の文学の源泉について。
桐野さんは、ドミニクさんが『輝ける闇』にフランス文学的な修辞を感じるという発言を受けて、「開高さん自身もかなり悩まれて、作為的に文体をつくっておられると思います。『輝ける闇』の文体は一種の発明だったのだと思っています」と。
滝田さんは、開高健の文学は基本的に行動する文学だとして、「なぜ行動するのかというと、あらゆるものが既に書き尽くされてしまったという思いが開高さんの中にあって、ならば自分は書かれていないものを書くしかないだろうと。今現在の移り変わる世界や自然、そういうものを現場に行って見聞きして書けるのは今生きている作家だけですから、そういうところに開高さんは注目されて行動されたのだろうと。ベトナム戦争もそうですし、釣りもそうです」。
永山さんは、「開高さんは純文学もノンフィクションも言葉の選択という点で最終的には同じだという考えですね。開高さんが愛読していたのは『言海』という分厚い辞典で、これは記念館にも飾ってありますが、辞典を読めば汲めども尽きぬ興味が湧いてくるし、そのことを楽しんでおられたように思います。たとえば、食べものの味を伝えるときでも単に美味しいとか旨いではなく、絶対に言葉にしてみせる、言葉に表現できなければ書き手の恥だというぐらいの決意でもって文章を書いていました」と。
続いて、本日のテーマである「茅ヶ崎」について。小学館の『開高健電子全集全二十巻』の企画・構成・編集を担当した滝田さんによると、全エッセイを「茅ヶ崎」というキーワードで検索をしたところ、茅ヶ崎という言葉そのものにヒットしたのは一件しかなかったという。それは茅ヶ崎に仕事場を設けた四年後に書かれたもので、そこには茅ヶ崎を
永山さんは「ずばり東京」の前に『週刊朝日』で最初に連載した「日本人の遊び場」の中で、茅ヶ崎の良さについて数行触れていたことを示し、かなり早くから茅ヶ崎への関心があったと。また、香川屋という肉屋のメンチカツが好物で、それを頰張りながら、サーファーが行き交うラチエン通りをえぼし岩を目指して闊歩するという、地域になじんだ茅ヶ崎ライフをしっかり楽しんでいたとも。
最後は、開高健にとってベトナム戦争は非常に大きな存在だったが、今まさにロシアがウクライナに侵攻しており、パンデミックにも襲われている。この時代に開高健が生きていたら、どういう言葉を紡いだろうか――。

滝田誠一郎氏
まずは滝田さん。「今お元気であれば、間違いなくウクライナへ行って、『ベトナム戦記』のウクライナ版みたいなものを書いたり、それを発展させて『輝ける闇』のような作品を書いたりしたかもしれない。場合によってはベ平連のようなものを組織して率先して平和活動をしたかもしれない。期待を込めてそうあってほしいと思う。
開高さんが好きでよく色紙に書いていた言葉で、『たとえ世界が明日滅んでも、私は今日リンゴの木を植える』というルターの言葉があります。この言葉は、今こそかつてよりも重みを持つ言葉になっていると思う。もし開高さんが存命であれば、この言葉を言い続け、書き続けているのではないか」。
永山さんは、「開高さんは非常に複眼的な思考をされる方だから、ロシアがウクライナに攻め入ったり中国が世界一強欲な資本主義国家に変わるということにも驚かないと思う。
むしろ、開高さんが今の八方塞がりの世界でもっとも心を痛めるのは、気候変動ではないか。彼は釣りを通して自然がどう変わっていくかということを観察していた。だから、気候変動、温暖化というものに対して彼がどういう行動に出たか、それが私の一番知りたいところです」と。
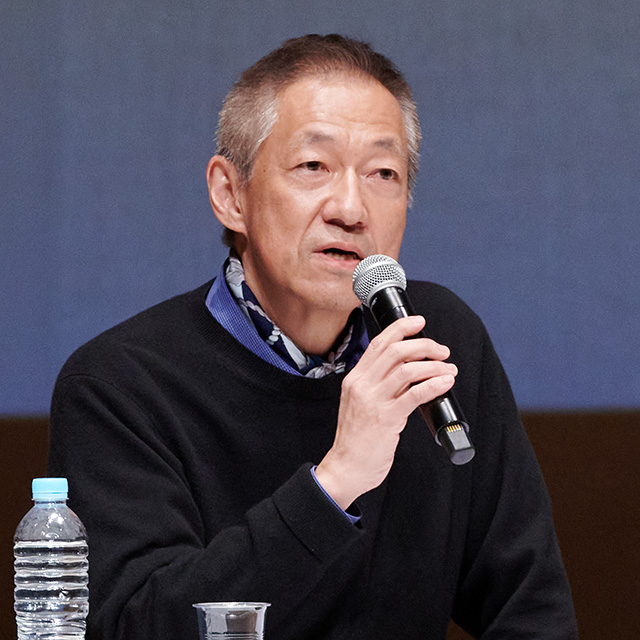
ドリアン助川氏
開高健が提起した重要な問題は「文学は現実をどう描くか」だという桐野さん。「その難しい問題を、開高さんはずっと体現していたような気がする。『輝ける闇』という作品をお書きになったけれども、多分それでは物足りずに、ご自分の中でいろんなものが内在化していたのではないか。九十二歳というお年でもしご存命だったら、ぜひ文学においての今の状況、気候変動やウクライナで現実に起きている戦争についてどういうふうに文学として書かれるのか。それを見たかった」。
最後にドミニクさん。「『輝ける闇』、『夏の闇』、『花終る闇』の闇三部作にはすごく不思議な読後感がある。フィクショナルだと知りつつも、開高さん自身がベトナムですさまじい戦闘を体験されたという事実もわかっている。だから、これはフィクションなのかノンフィクションなのかと読者自身がすごく揺さぶりをかけられるという、非常に面白い作家と読者の関係性も生まれる。
実地で行動する作家だったからこそそういう現象が起こっていると思うが、今、ウクライナで戦争が起こり、他の場所でも戦争が起こっている中で、インターネットやSNSを通じて、我々はつい事実は全部わかっていると思ってしまう。それは開高健が切り開いた文体とはかなり遠い世界の知り方なのではないか。そんな反省も改めて思った」と。
最後にドリアンさんは、「私はもしご存命だったらというふうに申し上げたのですが、開高さんは実際に生きておられるのではないかという気がしている。ゲーテが亡くなる数年前に一番若い弟子のエッカーマンに、私は肉体をやがて失う。しかし、別の形で生き残る。つまり、書物として、言葉として生き残るんだということを伝えるシーンがあります。まさに私たちは、没後三十三年の今、開高さんの本を改めて読み直して、その作品が生きていることを実感し、いまだにこれほどの情熱をもらえる。そんな稀有な体験をさせていただいた気がいたします」と締め括った。
構成=増子信一




