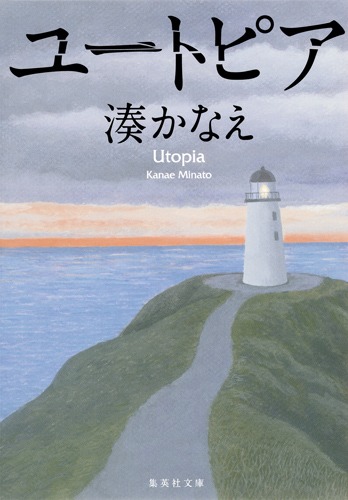[インタビュー]
『カケラ』文庫化&作家生活十五年記念
『カケラ』でイラっとする部分があったとしたら、
きっと身に覚えがあるからです
湊かなえさんの長篇小説『カケラ』が文庫化されました。ドーナツに囲まれて自死した少女をめぐって、さまざまな人間が彼女と自分自身について語っていくうち、謎が深まっていく物語です。単行本刊行から二年。今あらためて本作に思うことや、すでに集英社文庫に入っている『白ゆき姫殺人事件』『ユートピア』について、また、二〇二三年、作家生活十五年を迎えることについてもお聞きしました。
聞き手・構成=タカザワケンジ/撮影=祐實とも明

どこかの誰かの話ではなく
―― 『カケラ』の文庫化にあたって思うことから聞かせてください。
『カケラ』は、太っているとか、一重まぶたとか、コンプレックスになりやすいことを入口に、より多くの人が自分ごととして感じてほしいと思って書いた作品です。どこかの誰かの話ではなく、自分が美容整形を受ける機会があったらどうするかとか、自分はどう生きたいかを考えてもらえる物語になればいいなと思いました。
『カケラ』を書いていた当時と比べると、多様性という言葉が浸透してきましたよね。それぞれがなりたい自分になっていいんだという流れになってきていると思います。自分のなりたい自分ってなんだろうとか、今までこうありたいと思っていた姿は、実は自分がなりたいのではなく、他者の目を通した理想だったんじゃないかとか、多くの人が自分自身に問える時代になっているのかなと思います。
―― 美容整形外科医の
亡くなった
それに、語り手たちそれぞれが、彼女について語ることで、自分が容姿について悩んだことや、彼女と同じ年頃を振り返ることができる。
有羽は鏡みたいな存在です。その子のことを語っているようだけど、実は自分の価値観をその子にぶつけて、はね返ってきたものを語っています。語り手たちは、精神的に余裕のない人や、自己顕示欲が強い人、自己肯定感が高いのか低いのかわからない人だったり、それぞれ偏りがあるんですね。そういう人たちがもういない女の子を語ることによって、彼らの歪みを表せるのではないかと思いました。
自分語りを混ぜたモノローグ
―― 語り手たちから感じるのは、誰もが語らずにはいられない現代人の
久乃は有羽のことを聞きたくて会いに来ているのに、喋るのは八割方自分のこと(笑)。そういう自分語りをしたい人がとても多いからSNSがこんなに盛んになっているんだと思います。匿名で発信しているのに、なんとなく自分のことを織り交ぜて書くのが好きな人たちが多いなあ、と思います。
―― いきなり自分語りを始める。聞いてないのに(笑)。
悪口を吐き出したいだけなら自宅で日記に書けばいいことで、SNSに載せるというのは、やっぱりそれを誰かに見てほしい、聞いてほしいと思っているからですよね。テレビのコメンテーターになった気分なのかな。世の中に物申したいんでしょうか。
―― 『カケラ』の登場人物たちも物申したい人たち。モノローグをお書きになっている時の湊さんの意識はどんな状態なんですか。
その人になりきって、目の前に先生がいて、自分は何ひとつ間違っていないんだという状態で書いていましたね。セルフ突っ込みは絶対入れずに。「久乃先生、私の話をお聞きください!」という感じですね。
―― セルフ突っ込みを入れないのは、冷静になってしまうからでしょうか。
そうです。自分が正しいと思い込んでいる状態ですね。口では「私は間違っていたのです」と言ったとしても、それはその言葉を言えるようになった今の私をすてきだと思っているんです。
―― たしかに! 百パーセントの自己肯定感ですね(笑)。だから読んでいるとそれなりに説得力があるんですよね。
それぞれ間違ったことは言ってはないんですけど、読者は、なんか嫌だって思うんじゃないでしょうか。
―― 嫌だなって思いますが、もしかすると、客観的に見たら、同じようなことを言っている自分がいるかもしれないですよね。
自分もこの登場人物と同じようなことを言ってないか、こういう見方をしてないかと思ってほしいです。自分の成功体験を押しつけてくる人とか、自分の基準とか価値観を正しいと押しつけてくる人とか。仲がいいから言ってあげているんだみたいなのとか。言われるほうは嫌だと思うんですけど、言っているほうは自覚していないかもしれない。特に身内だと「こういうことを言ってくれる人がいることをありがたく思いなさい」みたいなことを言ったりしますよね。
『カケラ』を読んでいて、イラっとする部分があったとしたら、きっと身に覚えがあるからだと思うんです。自分が言われたことがあるか言ったことがあるかだと思うので、客観的に振り返る糧にもしていただけたらと思います。
―― 聞き手の久乃も興味深い人物ですね。彼女のモノローグもありますが、基本的には聞き役に徹しています。読者としては、久乃が語り手の言葉をどう受け止めているのだろうかと想像してしまいます。
モノローグの語り手本人はもちろん、聞き手の久乃先生だったり、亡くなった女の子が見えてくるように、ということは意識しました。久乃先生はなりたい自分になれていて、きちんと自分を持っている人。自分の仕事がみんなを幸せにしていると思っていたら、亡くなった人がいてショックを受けているんです。だから原因を知りたい。努力をして成功してきた人だから、すぐ動いて、徹底的に原因を探りに行く。自分の判断は正しかったのか、と。語り手たちの話を聞いている間は、この人こんなこと言っているよ、みたいな呆れる瞬間もあったかもしれませんが、きっと自分でも気づいていなかった気づきがあったと思います。
時代の変化と変わらないもの
―― 『カケラ』のモチーフが美容整形ということで、思い出すのが『白ゆき姫殺人事件』です。化粧品会社に勤める美貌の女子社員が殺され、地味な容姿の同期が疑われるという物語です。二〇一二年初版刊行なので、もう十年以上も経つんですね。
『白ゆき』は私にとってちょうど十冊目にあたる単行本でした。書き始めたのはツイッターが
―― 作中にマンマローというSNSが登場し、重要な役割を果たしています。
ほかの作家よりも早くSNSを採り入れたいなと思ったんです。それにごく普通に生きてきた人が、会ったこともない人たちの勝手な臆測で疑われたり、思い込みだけでどんどん犯人扱いされていく話を書きたかったので、ぴったりだなと。
見た目の印象で「ああ、あの人は陰湿そうだから、いかにもやりそうだよね」と思われて、本当に犯人扱いされたらどうなるだろう。美を商売にしている化粧品会社で、殺された人がすごくきれいな人だったら、嫉妬した女子社員が殺したと思われるんじゃないかなと考えていきました。
この十年間を振り返ると、当時よりもSNSが発達しましたよね。パソコンを開かなくてもスマートフォンでいろんなウェブサイトを検索できるようになり、簡単に誰でもSNSに投稿ができるようになりました。
―― 携帯電話の利用者のうち、二〇一二年当時は、スマートフォンの普及率は二二・九%。今は九四%だそうです(モバイル社会研究所調べ)。マンマローはPCでアクセスしていた人が多かったでしょうね。
あと、YouTube も十年前はまだ業界の人がスピンオフみたいな作品を上げる場で、今のようにYouTube 出身の人気者はいませんでしたよね。SNSが発達したことによって、誰でも簡単に情報を発信・受信できるようになった分、ためになるものから怪しいものまですごく幅が広がりました。その一方でSNSでの誹謗中傷で亡くなる方が出たりと、『白ゆき』の頃よりも問題が深刻になっています。
―― 今読み返すと、SNSの闇を描いたという点では先駆的な作品でしたし、偏見や思い込みが広がっていく社会の本質は変わっていないように感じます。本質が変わっていないという点では『ユートピア』もそうですね。地元民と移住者の地域へのまなざしの違いや、考え方の違いが浮き彫りにされていましたが、コロナ以降、都会を離れてリモートで仕事をする人も増えたので、あらためて読んでほしい作品です。
『ユートピア』は、移住ってそんな簡単じゃないよと思って書いた作品なんです。最近、よく言われているワーケーションとか、夏休みを別荘ですごすくらいならいいと思いますが、そこに住んで、しかも町をいい方向へ導こうと考えるのはどうなんだろう。
「祭りがあるのでおみこしを担いでくれませんか」と町内会からお願いしたら、「それは義務ですか」という言葉が返ってきた、なんて話を、当時聞いていたんですよ。私は地方に住んでいるので、みこしを担ぐ気持ちのない人にはあまり来てほしくない(笑)。地方への幻想、勝手な憧れだけを持ってきて、その土地のものを否定するような人たちの話を書いておきたいなと思ったんです。
――理想と現実のギャップですよね。湊さんの作品には、しばしば理想に振り回される人たちが登場します。でも現実は思い通りにはならない。
人間ってそんなに美しいものではないと思うんです。でも、どこかで折り合いをつけながら、どうにか生きていければいい。それはどの作品を書く時にも思っていることです。
―― それが社会の中で生きるっていうことでもありますよね。登場人物それぞれに言い分があって、それなりの理屈がある。でも、それが人とは違うから対立してハレーションが起きる。読者は登場人物たちの言動を見ながら、じゃあ、自分はどうしようかと考える。
まったく同じじゃなくても、この要素は自分の中にもあるなあ、と思ってもらえたら。まず気づくことが大事なのかなと思っています。みんなが平等に幸せになるのは無理だと思うんですけど、誰かの不幸せの上に幸せが成り立つんじゃなくて、ちょっとずつみんなが譲り合えたらいいんじゃないかなと。でも、そう思いつつ、私の小説の登場人物たちは自己主張するから、なかなかそうはならないんですけど(笑)。でも、そういう気持ちを持っていることを前提にしたほうが、生きやすい社会になるんじゃないかなと思います。
次の十年のために休筆した一年
―― 最後にお聞きしたいんですが、二〇二三年は作家生活十五年です。どんな感慨をお持ちでしょうか。
あっという間でしたね。三十五歳でデビューしたんですけど、「あれ、もう五十歳になってしまう」という感じです。作家としての自分はぜんぜん歳を取った感じがしない(笑)。でも、小一だった子供が成人式を迎えたので、プライベートでは明らかに年月が経ったことを日々実感しています。日常生活があったからこそ、きちんと時が流れていることを意識して生活を送れてきてたんじゃないかなと思いますね。
―― 二〇二二年は休筆されましたが、どのような一年だったでしょうか。
休ませてもらったのも、このままのペースで走り続けたら、体力的にあと一、二年で潰れてしまうなと思ったからなんです。次の十年、長距離を走るために一年休もうと思って、本を読み、演劇やミュージカル、映画をたくさん見に行くことができました。最初は純粋にほかの人たちの創作物を楽しんでたんですが、だんだんと「やっぱり書きたい」と思うようになりました。じっくり充電できたので、この一年の経験が創作への糧になったと思います。今年、執筆を再開しますので、期待して待っていてください。