[インタビュー]
小説すばる新人賞
受賞作刊行記念
シャチは謎が多いからこそ、
イマジネーションが膨らんだ
第34回小説すばる新人賞を受賞した『コーリング・ユー』は、シャチたちの会話から始まる驚きとスリルに満ちた海洋冒険小説です。ロシアの海で捕獲されたシャチのセブンには、他動物とコミュニケーションできる特別な能力があった。訓練中、セブンのその能力に気付いたアメリカの研究者・イーサンらとともに、地球環境を救うかもしれない重大なミッションに挑むことになる。
人間と、「海の王者」とも「冥界からの魔物」ともいわれるシャチ。種を超えた交流と絆を描いた小説はどのように生まれたのでしょうか。「書くことは生活の一部」という永原皓さんの受賞までの道のりもうかがいました。
聞き手・構成=山本圭子/撮影=冨永智子

なぜ「シャチ」だったのか
―― この度はおめでとうございます。受賞の知らせを聞かれたときのお気持ちからうかがえますか。
本当にびっくりしました。その前に見た占いに「今年は趣味が仕事になるかも」と書いてあって、しかもラッキーデーが選考の日。でも「まさかね」と思っていたんです(笑)。
―― 受賞作『コーリング・ユー』は、すぐれた能力を持つシャチのセブンが、海洋研究所の研究員・イーサンや飼育員・ノアの訓練を受けてあるミッションに挑む過程を、シャチと人間両方の目線で描いた物語です。どういうところからシャチと人間の話を考え始めたのですか。
最初のきっかけは、水産関係の仕事をしている知り合いから、シャチの捕獲に関する話を聞いたことです。私個人はシャチの捕獲には賛成しませんが、高いスキルを駆使しつつ、そうした仕事で家族を養っていた人たちもいるはずなので、解決が簡単ではない状況も織りまぜながら、物語を作ることができたらと思いました。
もうひとつは“ナガスクジラが五頭いれば、太平洋横断の伝言ゲームができる”と本で読んだことです。すごく素敵だな、意思の疎通ができるクジラたちは何を伝えあうんだろうと考えたとき、長距離を移動するのだから「僕はここにいるよ」「私はここよ」ということを伝えあったりするんじゃないかと。互いの存在を認め確認しあいたい気持ちは人間にもあるから、個々がつながることには種を超えた大切な意味があると思って、少しずつ話を作っていきました。
―― シャチやクジラなど海洋哺乳類の生態と捕獲法、発電菌など新たな資源とそれらに対する海洋哺乳類の活用、海軍をとりまく国際情勢……と、海をめぐるディテールは読みごたえがありますが、専門知識がおありでしたか?
いえいえ、私は根っからの文系人間なので。さきほど申し上げた知り合いの水産会社で魚やプールを見せていただいてから関連書籍を読んだり、海洋哺乳類のドキュメンタリー番組やユーチューブを見たりするうちに、興味を持つようになりました。
ただ、小さい頃、家にあった生き物の図鑑を繰り返し見ていたんです。長野県出身で海が周りにない環境で育ったせいか、海中の世界が描かれた魚の図鑑は特に興味深かったですね。繰り返し同じものを見る。そういう経験が根っこにあって、そこから出てきたものが何かあるのかもしれません。
―― そんな環境でお育ちになったとは思えないくらい、海の描写には迫力と神秘性があって、臨場感にあふれていました。
海を知らずに育ったので、海に行くことがあると、そのぶんショックが大きかったんです。海の美しいだけじゃないところ、たとえば波の強さや水の冷たさに恐怖を覚えたり。魅入られると同時に、畏おそれを抱くというか。海が身近な人とは違った感じ方をしたんだろうと思いますが、自分にとってこう見えた、という海を書きました。
様々な職場を経験して知った専門性と普遍性
―― 舞台はアメリカなどすべて海外で、登場人物もすべて外国人ですが、そうすることに迷いはありませんでしたか。
私にとっては、舞台が外国でも日本でも構わなかったんです。軍が絡んでくることなどから、外国にしたんですが。
―― 読んでいる間じゅう、洋画を観ているような感覚になりました。物語にスピード感があって、場面転換が鮮やかで、登場人物の会話が洒落ていて。
ありがとうございます。洋画が大好きなんです。海外を舞台にした以上、あまり日本的な発想はしないほうがいいと思って、仲間同士や男女間の会話を書くときは洋画のようなテンポ感を心がけました。昔から読んでいた翻訳小説とか、最近ではアマゾンプライムなどで観ているアメリカのドラマの影響もあるかもしれません。会話はあまり苦労せずに書けた気がします。
―― 主人公のイーサンをはじめ、多くの登場人物はアメリカの国家組織や企業の専門家やトップです。そういう人を描く難しさはありましたか。
私は会社員を二十年ほどやったあと、契約の形で三年ぐらいずつ、いくつかの職場で仕事をしてきました。そのなかに国の防衛に関わるところや医学部の大学院などがあったんです。そこで働くことで、研究者の世界はこういう感じなんだとか、トップの人の考え方はこうなんだとか、もちろん私が研究をするわけではありませんが、各々の組織特有の空気や、視野みたいなものを感じ取ることができました。一方、いろいろ渡り歩くことで、何に一所懸命になるかとか、何に喜ぶかといった人間の感情は、どんな組織で働いてもあまり変わらないんだということを知ったんです。
だから、自分が知らない世界を書くからといって、変に構えなくていいだろうと。もし自分がここで生活をしていたらこう思うだろうという心の動きを大事にして書けばいいんじゃないかと思って、下調べはしましたが、結局は「同じ人間の世界」というスタンスで書いていきました。
―― 勝手な想像ですが、職場を探す際は小説のための取材意識がなきにしもあらず、だったとか?
興味がある業界を見てみたい、できればそこの「専門家」の発想や「常識」を知りたいという気持ちで探していましたが、半分は小説のためだったかもしれません(笑)。
シャチの「会話」を書く
―― シャチのセブンには人間とコミュニケーションをとる能力があり、イーサンはシャチを利用するミッションをある企業から依頼されますが、刻々と期限が迫るなか、その難しさとセブンを大切に思う気持ちの間で苦悩します。セブンと出会ったことで、イーサンは少しずつ変わっていきますね。
イーサンはあまり人を頼らないタイプで、辛かったり悲しかったりしてもそれを表に見せてこなかった。でもセブンとのミッションに苦悩するなかで、徐々に恋人や友人に本心をさらけ出すようになっていきます。少しずつ素直になって、自分を労わることを覚えていくのは彼の変化ですね。
―― 一方セブンは、イーサンたちの訓練を受けながらも、自分のせいで群れから離れた従姉のシャチを思い続けています。シャチやクジラなどの海洋哺乳類に人間と同じような会話をさせるのは、かなりの挑戦だったと思いますが。
もちろん現実的には無理のある設定だとわかっていましたが、シャチは個体数が少なく、確保も難しい上に対応が大変――そういった理由で、たとえばイルカほど研究が進んでいない動物です。複雑にコミュニケートをしているに違いないのにいまだ謎が多いと資料で読んで、イマジネーションが膨らみ、物語として創造する余地があると思いました。
シャチの
―― 人間が上から目線でシャチたちを見るのではなく、人間もシャチたちも同じ地球に共存している生き物。そんな永原さんの姿勢や思いが物語全体から伝わってきました。
この小説は群像劇で、いろいろな価値観の人間や動物が登場します。シャチを愛するイーサンはじめ、良心と闘いながらシャチを獲る人、水族館の意義など、世界にはいろんな事情があるんだということを踏まえた上で、根底には普遍的なテーマを置きたいということは考えていました。共存は、とても現実的で大事なこと。それを読む方にも一緒に感じていただけたらという気持ちはありましたね。
子育てを卒業して作った
「死ぬまでにやりたいこと10のリスト」
―― 小さい頃は生き物の図鑑がお好きだったとうかがいましたが、その後はどういう本を読まれてきたのですか。
小学生の頃は、子ども向けの海外SFの翻訳シリーズがたくさん出ていたので、それを端から読んでいました。大人向けのものを読むようになると、光瀬龍さんとかレイ・ブラッドベリとか。アイザック・アシモフもちょこちょこ読んでいましたね。がちがちなSFというよりSF的なイメージが好きというか、ロマンとサイエンスの融合みたいな世界観が好きだったのだと思います。
―― その世界観は本作にも通じるように感じます。小説はいつ頃から書き始めたのでしょうか。
初めて書いたのは小学生の頃で、高校時代までは友だちが読んでくれていましたが、その後はずっとひとりで、趣味で書いていました。書くことは生活の一部になっていたんですが、形にしようとか、書き上げるという意識はあまりなくて。
―― 今回、新人賞に応募されたのは、何か心境の変化があったのですか。
実は長い間書いていた話があって、それが『三国志』より多いくらいの文字数になったんです。これではいけない、ひとつの世界として収まるものを書く練習をしなければと思って、数年前いくつかの賞に応募しました。私の力不足でそこでの評価はあとにつながらなかったのですが、改めて「本を出したい」という思いが強くなって。そんなとき、本作のテーマに出会ったんです。
心境の変化という意味では、娘が独立して子育てが終わったことが大きいですね。なぜか突然「残りは余生だ」と思ってしまって。よし、これからはもっと自分を大事にして生きようと思って作った「死ぬまでにやりたいこと10のリスト」のうちのひとつが、「本を出すこと」でした。それから私はかなりの母親っ子だったんですけど、その母が亡くなって、向こうに母がいると思うと死ぬのが怖くなくなったんです。同時に、あと何年かわからないけれど、生きているうちにやりたいことをやっておこうという気持ちが芽生えてきました。
同世代の友人には五十代で初めて結婚した人もいれば、転職して海外に単身赴任した人もいます。「体力と気力さえあれば何をしてもいいんだ」と、刺激をもらっています。
―― 次作について考えていらっしゃることはありますか。
まだまだ話のタネを培養中で、主人公のキャラクターが立ち上がってくれるのを待っているところです。ずっと趣味で小説を書いてきて、書くことが嫌になったことはないんですね。でも、自分が書いたものは他の人にとっては面白くないかもしれないとか、このニッチなテーマを面白いと思うのは自分だけかもしれないという不安を感じることはありました。だからいまだに今回の受賞を驚いていますが、やっぱりこれからも自分の興味があることしか書けないと思う。それを小説という形にしていくことの難しさもつねづね感じながらも、挑戦し続けたいと思っています。
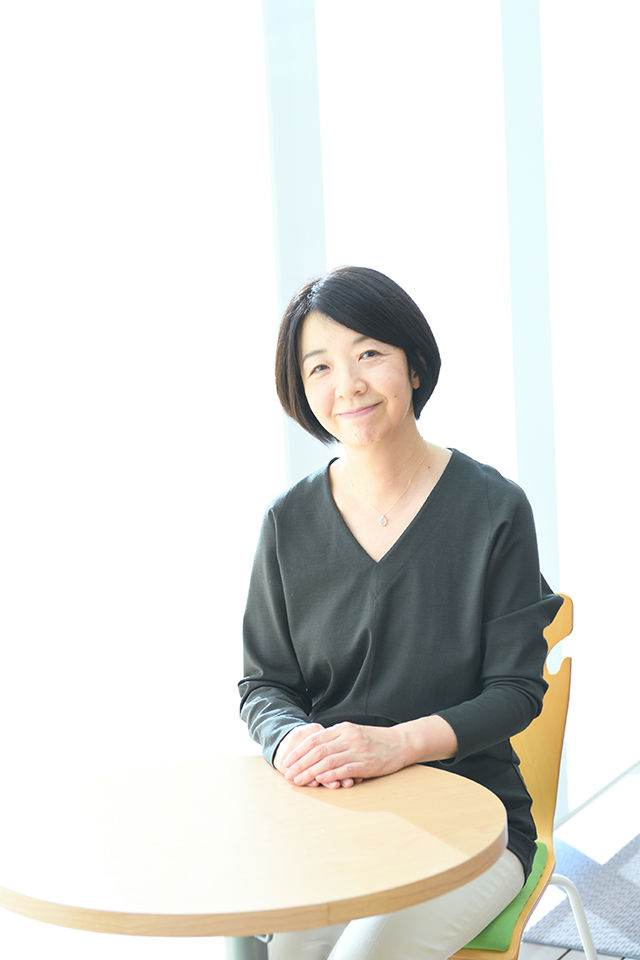
永原皓
ながはら・こう
1965年、長野県生まれ。中央大学文学部卒業。「コーリング・ユー」で第34回小説すばる新人賞を受賞。





