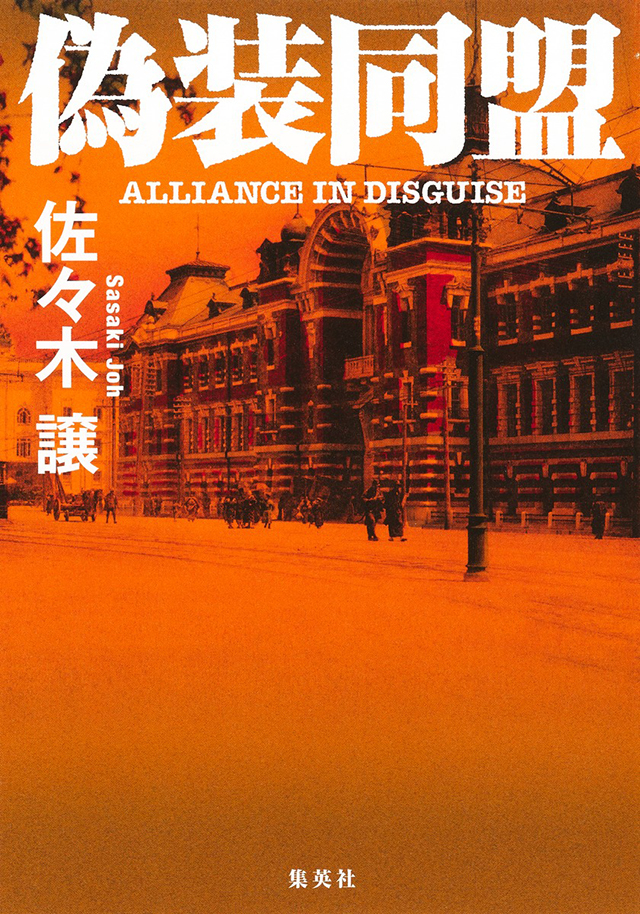[特集対談]
社会の歪みを映し出す
改変歴史警察小説
佐々木譲さんの新刊『偽装同盟』は、日露戦争に「負けた」ロシア統治下の東京を描いた改変歴史警察小説『抵抗都市』の続編です。
前作では、日露戦争終結から十一年経過した一九一六年、西神田警察署管内で発見された身元不明の変死体の捜査をする警視庁刑事課特務巡査の
ロシア二月革命を背景として、二重帝国の
構成=増子信一/撮影=山口真由子

日露戦争の“イフ”を題材にした理由
佐藤 『偽装同盟』は多層的な読みができて、大変楽しませていただきました。もちろん当時の日露の関係で読むこともできるし、ロシアをアメリカに置き換えて、現在の日本を読み込んでもいい。また、実際に日露戦争というのは、勝ったか負けたかよくわからないようなところがありますから、この小説にあるように、日本が負けてロシアの占領下に置かれるという可能性も十分あったと思います。もちろん、警察小説、ミステリーとしても面白い。
佐々木 そういっていただけるととてもうれしいですね。改変歴史小説ではありますけれど、私としては警察小説のヴァリエーションというつもりでもありますので。
佐藤 ロシアの占領下にあって、警察権を完全に持ち得ていない中で日本の警察がどういうふうに動いていくのかが興味あるところですね。そうした状況は、一九四五年から五二年までの独立が回復する前のアメリカ占領下の日本の警察の感じと重なります。
それから、この『偽装同盟』においては、一九一七年の十月革命ではなくて、二月革命に焦点を当てたのはよかったと思います。というのも、十月革命は、二月革命後に起きたボリシェヴィキのクーデタみたいなもので、二月革命と十月革命は比較的近接しているから、みんな十月革命の中で二月革命を捉えがちなんです。しかし、二月革命の後にもし十月革命がなければ、ロシアには別の発展の道があったと思います。
佐々木 このシリーズは、実は全三部作で考えていまして、今度の第二部で二月革命、次の第三部で十月革命を扱おうと思っています。
佐藤 この時代に焦点を当てて、しかも日露戦争がああいう終わり方になっているという“イフ”を入れるという構想は、どういうところから考えられたのですか。
佐々木 ひとつは、今の日本の未来に対する不安があって、その問題意識をストレートに書くよりは、過去のイフの話にしたほうがエンターテインメントとしては面白いかなと思ったんですね。もうひとつは、日露戦争前後の時代であれば、そこに何が
たとえば、これを秀吉の朝鮮出兵の話にしてしまうと、今の時代との関連性を読んでもらえない。近・現代史を題材にしていれば、私が持っている問題意識は間違いなく伝わるだろう、と。
それから、太平洋戦争を扱った三部作(『ベルリン飛行指令』『エトロフ発緊急電』『ストックホルムの密使』)のようなものも書いてきて、その時代に対する関心がとても強いというところもあります。この辺の時代であれば、ある思いを託して暗喩として書ける。それで、満州事変から第二次大戦にかけての近代史を題材に書いているんです。
また、改変した歴史の中での警察小説ということでいえば、先行例がいくつもあります。たとえば、四年ぐらい前にテレビドラマシリーズにもなったレン・デイトンの『SS–GB』という、ナチスに占領されてしまったイギリスが舞台の警察小説がありますが、そうした小説にかなり影響を受けています。
佐藤 最近の日本の小説では、古川日出男さんの『ミライミライ』がソ連の占領下にある北海道を舞台に描いた実験小説ですね。
佐々木 東日本がソ連に占領されたものとしては、小林信彦さんの「サモワール・メモワール」とか矢作俊彦さんの『あ・じゃ・ぱん』。それから、私と同じ北海道出身の作家、東直己さんがベルリンのように東西に分断された札幌を描いた『
佐藤 その中でも佐々木さんの作品は、東西冷戦下の状況ではなく、日露戦争の頃に時代を持っていったことで、それらとは違った独自の面白さが出てきたのだと思います。
それから、本郷通りがクロパトキン通りという名に変わったり、御茶の水のニコライ堂(東京復活大聖堂)を中心にロシア人街ができたり、その辺の構想力が非常に面白いですね。佐々木さんが昔の東京の地図を片手に、プーシキン通り、マカロフ通りといった通りの名前を楽しそうに配置している姿が思い浮かびました。
佐々木 ええ、とても楽しみました。
私の場合、警察小説でもハードボイルドでも、舞台にしている土地に対する興味をついつい描写し過ぎてしまうのですが、ミステリーの謎解きよりも、その土地を書きたいという欲求がまずあるんです。
小説の中で映える
ロシア文化と時代背景
佐藤 歴史的な事実からしても、日露戦争の後、日本とロシアは協商体制を取っていて、実は準同盟関係だったんです。ですから、ロシアとは非常に近い関係にあったことは間違いありません。その後ロシア革命が起きるので忘れ去られてしまっているのですが、日露の関係が一番よかったのは、実は日露戦争が終わった後だったんです。
そういうことを考えると、ここで描かれているのは歴史のちょっとしたずれという感じで、決して荒唐無稽な話ではない。それだけに逆にぞっとするところがあって、そこがまた面白い。
それから、細部が非常によくできていると思いました。たとえば、
その他、食べものなどでも細かいところが正確に書かれていて、ああいう描写は小説の中ですごく映えますね。
佐々木 ありがとうございます。
佐藤 ところで、ひとつお伺いしたかったのは、東京のロシア語学校に通って、ゆくゆくは新聞社に勤めたいと思っている
佐々木 基本的には、薩長史観ではない、攘夷思想ではない、ある程度ロシア文化に対しても許容度のあるバックボーンということで静岡出身にしました。
佐藤 なるほど。静岡の学生って非常に勤勉ですね。私は京都の同志社大学で教えているのですが、静岡県からも割と多くの人が来ていて、他の県の人に比べると静岡出身の人は割と伸び伸びとした感じがある。
佐々木 一般的にもそういうイメージがありますね。
佐藤 だから、自立を目指している彼女が静岡出身だというのも腑に落ちます。日露戦争の頃には、高等女学校を卒業している女の人も結構増えてきますが、彼女たちが就ける職業はまだまだ少なくて、それこそ有島武郎と心中した波多野秋子のような雑誌の編集者とか、新聞社の校正係とか翻訳係とか、あったとすればその辺りですね。
佐々木 彼女はロシア語を将来へのひとつの足がかりと考えたわけですが、主人公の新堂もまた、ロシア語を学ぶことでなんとか戦後を生きていくことはできるだろうという思いがあったのですね。彼は日露戦争で怪我を負い、復員後、支給された
ただ、圧倒的な国力の差で負けた敗戦国の兵隊であったという事実の重さを身をもって知っている。ですから、同盟といいながら事実上の属国であることに対する素朴なナショナリズムも抱いているんですね。だから、冒頭の事件とは別にアメリカ国籍のポーランド人の運動家が殺される事件が起きますが、そうした対ロシア独立運動に対しては無条件に共感するところがある。といって、警察官として何か具体的にやるわけではないのですが。
佐藤 結局、新堂は統監府保安課からその事件捜査を阻止されてしまうわけですね。その辺の複雑な思いはよく伝わってきます。
事実に即していうと、第二次大戦前の日本ではロシア語の実用価値が今よりはるかに高かったんです。だから、キャリアパスとしてのロシア語は大きな意味があったわけです。ニコライ堂の中にあったロシア語の専門学校のニコライ学院もかなり大きなものでしたし、昭和に入ると、今度は満州に国立ハルビン学院をつくって本格的なロシア語の要員を養成していた。
佐々木 「命のビザ」の杉原
佐藤 ええ。陸軍などは、ロシア語研究生という形で現在の東京外国語大学に学生を送っていました。だから、ロシア語の実用性というのはキャリアパスの中ですごく高かったんです。現に、戦前のロシア語の教科書のほうが今より比較にならないほど難しいですし、実用性も高い。それが、戦後の反共政策の過程でロシア語を勉強する人が少なくなったんです。
だから、ここで書かれているロシア語のウエートの高さというのは、創作ではなく、当時の等身大の世界だともいえます。
作品に反映された
今の時代の空気
佐々木 先ほど、これを書いたのは今の日本の未来に対する不安からだといいましたが、その意味では、ここで書いているのは改変された歴史の過去の話ではなく、同時代の話なんです。さらにいえば、近未来小説のつもりで書きました。
私が近未来小説として書いた部分というのは、実は日露戦争の経緯の中で、日本からロシア帝国に対して戦争を仕掛けてしまったというあの辺りの無謀さがひとつありました。日本が勝ったというのは日本海海戦のような奇跡があったおかげであって、普通なら勝てる見込みがない。ところが、最近の日本を見ていると、ひょっとしたら、あの時代の無謀な試みが繰り返されてしまうのではないだろうかという思いがあるんです。
佐藤 最近の東京では、このコロナ禍の中で、一人五万円くらいする高級ホテルのレストランの個室が、ほとんど一杯なんです。なぜかといえば、ここ二、三年で年収二千万から三千万ぐらいの中産階級上層部が明らかに増えているからです。その一方で、子供にだけは食事を作ってお母さんはもやしを食べているというような家庭も出てきている。このままほうっておくと、東京はエッセンシャルワーカーと中産階級上層部以上の富裕層だけの街になっていく。要するに、ひとつの国の中に別の国があって、それを束ねていくわけですから、ここで描かれている「二重帝国」と同じ状況なわけです。
コロナ禍の状況での大きな変化は二つの面で生じていて、ひとつはグローバリゼーションに歯止めがかかったことです。それに伴い、各国の国家の壁が高くなってきた、つまりナショナリズムの台頭ですね。作品の中ではロシアと日本ですが、
もうひとつは格差です。まず国家間の格差。先の三好という女性は、いつかサンクトペテルブルクに行きたいと憧れているのですが、それはロシアのほうが豊かだからです。二番目は国内の地域間格差。三番目が階級間格差。そして、四番目はジェンダー格差。奇しくも、この作品にはそれらのことが反映されていて、コロナ禍によるこの二年間の変化がよく出ているなと思いました。
エンターテインメント小説というのは、まずは面白くないといけないのですけれども、優れた小説家というのは、その上で時代の空気を作品に正確に反映するんですよね。
佐々木 そういわれると、ちょっと照れてしまいますが、連載しているときにはそこまでは時代の空気を分析的には意識していませんでした。でも、ゲラになった段階で改めて読み返したときに、一作目の『抵抗都市』のときの時代認識とは変わってきているなというのは感じました。そうした認識が反映されていると読んでもらえたのはとても光栄です。
佐藤 次の第三部は十月革命を扱うということですが。
佐々木 佐藤さんのお話の中にもありましたけれど、それこそ十月革命はボリシェヴィキ革命で、その影響はこの『偽装同盟』の中にも部分的に出ています。呼応という形ではないにせよ、十月革命とほぼシンクロしたように日本国内でも同じ問題が出てくるだろうと思います。
実際、十月革命を背景にして警視庁の刑事が扱う事件は、
佐藤 楽しみですね。実は、第一次世界大戦が終わった後の日本の大衆小説は、ほとんど日米決戦もので、ソ連の拡張をモデルにした小説ってないんです。つまり、大衆小説の世界ではソ連の脅威よりも、近い将来アメリカとの決戦になるだろうという予測が主流でした。
ソ連自体も一九二二年くらいまではいろいろな発展の可能性があり、さほど警戒されていなかった。ところが、一九年にコミンテルン(共産主義インターナショナル)ができ、その後中国共産党、日本共産党がつくられるという形になって、あの辺りを境に世界中がソ連を警戒するようになってきたんです。そうした世界革命という路線を志向せずに一国だけで社会主義国家をつくるという路線――結局、スターリンでそこに戻るわけですが――で最初からやっていれば、全然違ったでしょうね。
警察官のハイブリッド性
佐藤 お伺いしたいのは、こうした小説を書くときには、構想と資料集めの両方がありますが、具体的にはどのようにされたのですか。
佐々木 まず、長い時間をかけて資料を読んでいくうちに、題材やストーリー、プロットなどの構想が見えてきます。必要となる資料はさらに集中的に読み、そこで編集者と話をするという形ですね。
佐藤 資料に吞み込まれていないところはさすがですね。中途半端な形でやると、必ず資料に吞み込まれてしまって、エンターテインメントとして成立しなくなってしまう。
佐々木 こういう改変歴史もそうですし、歴史小説もそうですけれど、私は主人公がその立場で知り得た情報以外のものは書かない、できるだけ神の視点では書かないようにしています。「この頃世界はこうでした」みたいな解説はしない。
佐藤 解説がなくてもさまざまな描写で物語の背景が透けて見える形になっています。『偽装同盟』でも、いきなり「統監府」とか出てくると、前作を読んでない人は、「あれ? 朝鮮半島の話かな」と思うかもしれないけれど、読んでいくうちに自然にわかってくる。
多くの資料を読まれた上で、余分なものは捨てるというやり方というのは、熟練した小説家にしかできないなと感心しました。
佐々木 ありがとうございます。
佐藤 最後にもうひとつ。警察小説にこだわられるのはどういったところなのでしょうか。
佐々木 警察小説というのは、今の社会の抱えている問題点、歪みを書くのにとても有効な様式なんです。社会の歪みはまず犯罪として表れますから。
佐藤 今回読んで強く感じさせられたのは、警察官にはハイブリッド性があるということです。警察官は権力の末端機構を担っているとともに、民衆からのたたき上げでもあるので、一人の警察官の中に国家の声と民衆の声の両方を持つというハイブリッド性があるんですよね。これが外交官小説になると、民衆の声がなくなってしまう。
佐々木 それこそ外交官やスパイが主人公の小説では、背負っているのは国家だけになってしまう。たしかに警察官というのは、生活者としての自分と公務員としての自分、その両方の価値観の中で現実に対処していっている。そこは警察小説を書く上での面白さだと思います。
佐藤 二つの価値観の狭間にあって、自分の筋を一〇〇パーセント通せるわけではない。しかし新堂のように、抗議だけはしておこうとか、あるいは、上層部が逮捕を許可するかどうかはともかく、請求だけはしておこうと、自分のやることに歩留まりをつけておく。
結局、最後は人なんですよね。新堂だったら新堂で、どこで線を引くかというのは全部自分が決めていく。そこはサラリーマンたちに訴えるものがあると思います。会社で無理させられるときも、これ以上はやらない、あるいはこの辺ぐらいまでは一所懸命やらないといけないんじゃないかというのは自分で決めないといけない、と。
佐々木 そこまで読んでくださって、本当にうれしいですね。ありがとうございました。

佐々木 譲
ささき・じょう●作家。
1950年北海道生まれ。著書に『鉄騎兵、跳んだ』(オール讀物新人賞)『エトロフ発緊急電』(山本周五郎賞・日本推理作家協会賞長編部門)『武揚伝』(新田次郎文学賞)『廃墟に乞う』(直木賞)『ベルリン飛行指令』『制服捜査』『警官の血』『警官の条件』『回廊封鎖』『抵抗都市』『雪に撃つ』『帝国の弔砲』等多数。2016年、第20回日本ミステリー文学大賞を受賞。

佐藤 優
さとう・まさる●作家。
1960年東京都生まれ。85年、同志社大学大学院神学研究科修了の後、外務省入省。95年から外務本省国際情報局分析第一課の主任分析官として、対露外交の最前線で活躍。著書に『国家の罠―外務省のラスプーチンと呼ばれて―』(毎日出版文化賞特別賞)『自壊する帝国』(新潮ドキュメント賞・大宅壮一ノンフィクション賞)『新世紀「コロナ後」を生き抜く』等多数。