[インタビュー]
つらかった時代と
向き合うことで書けた小説
高校二年生になって間もなく、学校に行けなくなった
「ものすごく難しい気がしていた」と語る初めての青春小説はどのように生まれたのか。お話を伺いました。
聞き手・構成=佐久間文子/撮影=中野義樹
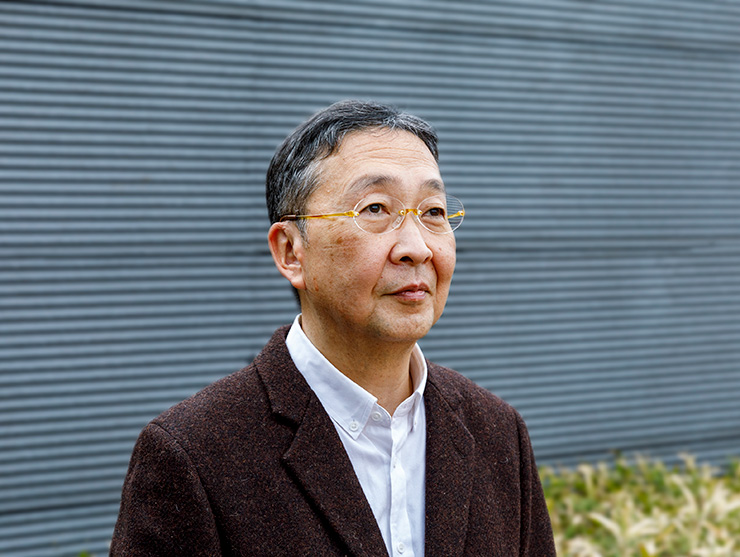
自分の行き先をコントロールできない「泡」
─ 『泡』という小説には、通っている高校に行けなくなってしまった薫という少年が、太平洋岸の町に住む大叔父のもとで過ごしたひと夏が描かれます。どのようにして、この作品はできていったのでしょうか。
「すばる」に小説を書くという約束はずいぶん前からしていて、じゃあ何が書けるかと考えたときに、自分がこれまでやってこなかったことをしようと思いました。いわゆる青春時代を、十代の子がどう生きているのかを書いてみよう、と。
青春小説って、ものすごく難しい気がしていたんです。『泡』は、ぼくの私小説ではまったくないですけど、十代のころどういうことを感じたり、学校や周囲とどういう関係を結び、あるいは結べなかったり、といったことは、どうしても自分の経験を軸にして考えるしかなくて、記憶を総動員して、そこからフィクションに変換していきました。ぼくの通っていた高校は柔道と剣道が必修で、小手の内側のずるりとした感触が気持ち悪くて嫌だったことなんかを思い出したりして、何かに復讐するような気持ちで(笑)、書きました。
─ 主人公が東京生まれであることや、はっきりとは示されていませんが時代設定も、ご自身とほぼ同じになっていますね。
それは、そうですね。ただ、ぼくは中野区出身なんですけど、中野を舞台にして書くタフさはなかったので、出てくる土地は、思い切って東京から遠くに離したんです。
─ 薫がひと夏、過ごすことになる温泉と海水浴の町ですね。砂里浜(SARIHAMA)という地名は白浜(SIRAHAMA)のアナグラムでしょうか。
言葉の響きからも、とくに和歌山の人は、これは白浜だろうって思うかもしれないですね。そう思われて別にかまわないんですけど、やはりここはあくまでフィクションの中の場所ということです。
─ 舞台が海辺であるということも含めて、『泡』というタイトルはいろんなイメージを喚起します。薫は、空気の吸い過ぎでからだの中にガスがたまる
この小説を書く前から吞気症は知っていたんですけど、小説で描いている時代にそう呼ばれていたかは調べました。こういう症状に苦しんでいる人は結構多くて、女性により多くみられるようです。それがなぜかはわかりませんけど。
─ 青春小説の主人公と、吞気症に悩んでいる設定とは、どうやって結びついたんでしょう。
ぼくにとって、青春期のめんどくささというか、二度とあの時代に戻りたくないという気持ちの芯にあるものは、やっぱり自分のからだとのつきあいかたが、なかなかうまくいかない時期だったから、というのが実感としてあります。一時期、十四歳という年齢が犯罪との関連で取りざたされましたが、そうしたことにも、自分のからだが思うようにならない、というのはいくらか影響しているのではと思います。
ただ、大人になってふり返ってみると、ちょっと滑稽な気もするんですよね。現に悩んでいる当人に滑稽なんていうと申し訳ないですけど。はたから見るとちょっとおかしみもあるけれども、本人はとても苦しい、それを象徴するものとして、書き始めてから頭に浮かんだのが吞気症のことでした。
─ 「もの言わぬは腹ふくるるわざなり」(「徒然草」)を思い出したりして、すごくしっくりくる設定です。思いを言葉にできない、というのは松家さん自身も感じることだったりしますか。
それはもう、まったくそうです。人とのやり取りをふり返っても、言葉で伝えられることなんてほんとうにごく一部に過ぎなくて、仮に伝わったとしても、じき泡になってパチンとはじけて消えてしまうような気がしています。他人の経験や考えを理解しあうのはかなわないことだ、というあきらめが泡という言葉には含まれているかもしれません。
泡のイメージが自分の中に生まれたその瞬間をよく覚えていないんですが、泡を違う言い方で言えば「うたかた」ですし、しゃぼん玉だって、風に乗ってどこかに流されていって、家の軒にあたれば一瞬で消えてしまう。自分で自分の行く先をコントロールできないものの象徴かなと思います。
─ そうしたはかなさや耐えがたさが、深刻にではなく、軽やかに、風通しよく書かれていると感じました。
泡って、はかなくて、とてもきれいですよね。子どもがシャボン玉に夢中になる気持ちがすごくわかるというか、あれがいつまでも消えないものだったらあんなに面白がらないと思うんです。はかなくて美しいから心ひかれる。そのことを思いついてからは、逆に泡のイメージが小説を引っ張っていってくれるようになりました。
「過去」を持つ大人たちと出会って
─ 短い青春の時期そのものが、泡みたいでもありますね。
ときどき中学や高校時代、あるいは大学時代のことを、あの頃は最高だった、みたいな話をする人がいるじゃないですか。ぼくはそういう話を聞くと、何か置いていかれる気がするんです。ポール・ニザン『アデン・アラビア』の、有名な冒頭の一行(「ぼくは二十歳だった。それがひとの一生でいちばん美しい年齢だなどとはだれにも言わせまい」篠田浩一郎訳)がありますけど、自分にとっても、ずっと蓋をしておきたい時代でした。
七〇年代にはまだ不登校や引きこもり、発達障害という言葉もなかったけど、もしそういう言葉があのころあったら、ぜんぶ自分のことだと思ったんじゃないかな。言葉があるがゆえに苦しんでいる人、救われた人、両方あると思いますが、当時はとにかく死んだ気になって学校に行くしかなかったですから。
ぼくの場合は、中学高校だけでなく、大学に入ってもまだつらさは続いて、八〇年代に出版社に入ってはじめて、溺れる寸前に水面に顔を出して息ができた気がしました。いま、現役でやっている編集者の
この小説は、そのすごくつらかった時代と向き合うことで書けたので、当時の自分に、とりわけ十代の自分に、こうして書いたよ、と合図を送りたい気がします。
─ 青春小説の中で、主人公が誰と出会うかは重要な要素だと思います。砂里浜で薫が出会うのは、大叔父にあたる兼定と、兼定が営むジャズ喫茶にふらりと来て、そのまま働くことになった岡田、世の中から少しはぐれたような二人です。
狭い世界に閉じ込められたように感じている薫の前に現れるのはどういう人がいいだろう、と考えたとき、まず思い浮かんだのが兼定でした。
戦争に行った話が出てきますから兼定は七十代半ば、薫にとってはおじいさんの世代にあたります。兼定は戦争で特異な経験をしていますが、戦後の日本に戻ってきてからは、親族とも離れて、知らない土地で、自分の好きなように、好きな仕事をして、適当に、まあまあ機嫌よく生きています。
いま困っている少年のそばに、実は過去に生死の境をくぐり抜けてきた人が、直接、指導するわけでもない、相談に乗るわけでもないけれど、絶妙な距離でいる。そういう年長者がいたらいいんじゃないか。
それだけだと何かが足りない気がしたんですね。六〇年代の後半から七〇年代前半にかけて何らかの強烈な経験をしたのち放浪していた青年なら、薫にとっても話しやすいんじゃないかと思い、兼定の相棒になる岡田がどこからかふらりと現れた。
岡田がどういう経験をしてきたのか、じつはぼく自身にもよくわかっていません。七〇年代には、学生運動だったり新左翼運動に参加したりして、岡田のようにいったん世の中の外に出た後にもう一度、戻ってきて、だましだまし何とかその日を生きている若者は結構いたと思うんです。
そういう背景は、兼定の店で彼ら三人が日常的にやりとりしているところだけ見ても、まったく見えてこないでしょう。けれども、追い詰められて夏の間だけ砂里浜に避難して来た薫にとっては、周りにいる大人とはまったく違う二人の生き方に触れるのは、意味のあることだったと思います。
─ 家族から傷つけられて東京から砂里浜に移った兼定が、親族の一員である薫を拒まず受け入れるのは、ゆるやかに関係を結び直そうとするようです。
兼定が薫を一方的に助けるというのではなく、薫がやって来ることによって、いったん切り離された場所から改めて自分が求められることに、兼定自身、ちょっとした喜びもあるはずなんです。はっきり意識していないとしても、二人はたがいに与えあう関係になっていると思います。
─ 戦争が終わって四半世紀ぐらいしかたっておらず、兼定のように重い記憶を背負った人もいるのに、多くの人はそのことを忘れていく。すごいスピードで時代が動いていたんですね。
六八年にはあちこちの駅や路上で一種の内戦みたいな騒ぎになっていたのに、潮が引くように消えてしまい、七〇年に入るといきなり万博が開かれています。あの変わり身の早さはすごかった。もうひとつ、いまと違っているのは、あのころ、未来はどんどん良くなるというムードがあって、よけいにぼくなんかにはキツかったのかもしれません。
─ 改めて、小説で描かれる一九七〇年代は、高度経済成長期ということもあって、いい大学を出ていい会社に入ってという同調圧力がかなり強かったのではないかという気がします。
他の時代と比べてみるのは難しいですけど、そういう空気は確かにありましたね。七〇年代後半の大学生って、結構まだ髪が長かったりしたんですけど、就職シーズンになると一斉に髪を切ってスーツを買って、みたいにがらっと変わっちゃったんですよ。断頭台に送られるような感じにどうにもなじめず、ぼくは一時、ニューヨークの貧乏旅行に逃げたりして、大学も一年留年したんですけど。
運命共同体のロックバンド、出入り自由のジャズ
─ 兼定の店がジャズ喫茶だということもあって、今回の小説では、そこで流れる音楽が、世代を超えてつながることのできるものとして書かれています。
つらかった時代にぼくが何に救われたかというと、音楽であり、本であり、映画であり、演劇であり、美術であって、ぜんぶ、ひとりで楽しむことができるものばかりです。中でも音楽は、いまだに自分の中で最上位にある大事なもので、音楽の力っていうのはやっぱりすごいと思っています。
今回、小説に出てくる音楽としてジャズを選んだのは、たとえばロックバンドだと、ちょっと運命共同体みたいなところがあって、途中で何かややこしくなって解散、みたいなパターンですけど、個人が集まってトリオやクインテットで演奏するジャズは出入り自由なんですね。
周りとうまくやっていくことができない薫という少年にとっては、究極のところはひとりだけど、そのときどきで、いろんな相手と組んで演奏するジャズに触れることに意味がある気がします。
この小説自体、これまでのようにいろんなことを準備して、ある部分はきちんと調べて書く書き方ではなく、ジャズのアドリブみたいに、出たとこ勝負で書き進めることが何度もありました。自分の苦しかった思いがベースにあるので、逆に自由に展開させていくことができたように思います。
─ 泡ということで言うと、たまったものを、ガス抜きのようにして外に出すことも大事、と教えられた気がします。
岡田が吞気症の薫に、おならは我慢しなくていい、ぶーぶーおかまいなしにすればいい、ということを言います。ため込む一方だとほんとうに逃げ場がなくなってしまうので、あれは岡田なりの励ましだったと思います。
ため込んだものがエネルギーに転化することもきっとあるんでしょうけど、そんなものを抱え込んでいても何にもならないんじゃない? と言ってくれる他者がいたら、若い人はそれで救われることもあるんじゃないでしょうか。
─ これまでの松家さんの小説と少しトーンが違っていて、兼定がたまに使うあやしい関西弁を含め、そこはかとないおかしみが漂います。薫が自分のことを「おなら仕掛けの奇妙な人間」だと思い悩む場面では、本人がいたってまじめなだけに思わず笑いがもれてしまいました。
笑いに関しては自分の中で苦手意識があって、笑いを上手に書ける人ってうらやましいなと思います。今回の小説では、少年の抱える苦しさを、ただ苦しいというだけで書いていくのはちょっとキツイので、薫の肩を軽くたたくような気持ちで、笑えるところも入れたくなったのかもしれませんね。

松家仁之
まついえ・まさし
1958年東京都生まれ。編集者を経て、2012年に発表した長編小説『火山のふもとで』で第64回読売文学賞を受賞。2018年『光の犬』で第68回芸術選奨文部科学大臣賞、第6回河合隼雄物語賞を受賞。その他の小説作品に『沈むフランシス』『優雅なのかどうか、わからない』。共著に『新しい須賀敦子』。








