[特集インタビュー]
誰もが、灯台のように光を届ける瞬間 がある
一年にわたって各地方紙に連載された、宮本輝さんの新聞小説『灯台からの響き』が刊行されます。小説の主人公は、東京・
物語の発端は、本の間から見つかった亡き妻宛ての古い葉書。葉書に書かれた「灯台」という言葉と、どこかの岬らしい線画の謎が解き明かされていく仕掛けも、読み手を引きつけて離しません。夫の康平さえ知らなかった妻の一面が明らかになる、最後の
聞き手・構成=宮内千和子/撮影=山下みどり
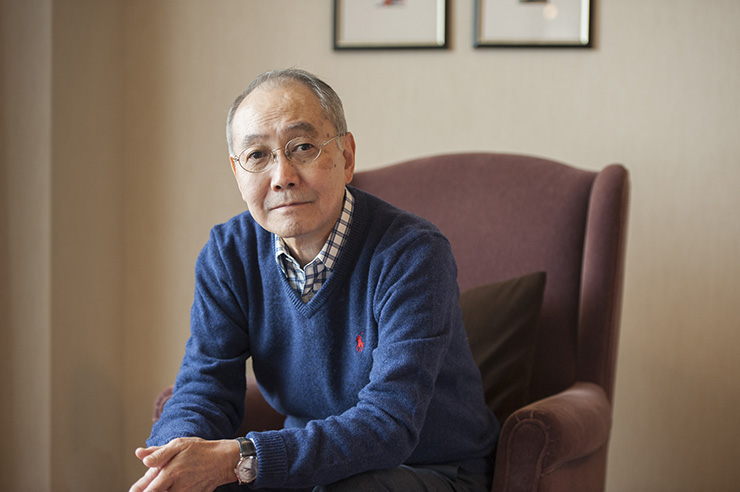
灯台を主人公にした
小説を書きたい
─ 今回の作品では、灯台のある風景が主人公の心象風景として大きな意味を持ちますが、灯台を物語の軸に据えようとしたきっかけは何かあるのでしょうか。
今文庫になっている僕の小説『草花たちの静かな誓い』の中に、ウクライナ系アメリカ人の大男の探偵が出てくるんです。ニコライ・ベロセルスキーという男で愛称ニコ。そのニコという男が灯台が好きなんです。「(夜の)灯台のライトがぐるっと一周して俺のいるところを照らす瞬間が好きなんだ」とか、「世界中の灯台を夜中に眺める旅に出たい」と言わせている。そのときは何のたくらみもなかったのだけれど、あれは、僕の気持ちなんです。僕、灯台が好きなんですよ。
─ 前々から灯台がお好きだったんですね。
そう。だけど、そのことをずっと忘れていたの。で、あるときふと、僕が一番好きな灯台ってどこかなと考えた。僕も世界中、灯台のあるところばかり行ったわけではないけれど、考えてみると心に残る灯台って、やっぱりヨーロッパ、アメリカあたりの灯台で、日本よりも風情があるんですよ。それでもう一ぺん行ってみたい灯台ってどこかなって考えたら、イタリアのカプリ島にある灯台が浮かんできた。そんなに大きな灯台ではないんですが、レンガ造りの風情のある灯台でね。ああ、あそこにもう一度行きたいなというのが頭の片隅にあった。そんなときに、各地方紙と提携して、新聞連載をやらないかと声をかけていただいたんです。そのときにね、ふっと、どんな筋立てとかいうことも関係なく、灯台を主人公にした小説を書こうと思ったんですよ。
ただのパッとした思いつきだけなんです。だけど、そうなると、まさかカプリ島に行くわけにもいかんしね(笑)。灯台だけは決まったものの、どういうプロットにしようか、どういう登場人物を出そうかと、いろいろなものが頭の中で重なってきてね。ちょうどそのとき、島崎藤村の『夜明け前』を読んでいたんです。ご存じのように、この小説は信州
─ 「風景の中から物語が動き出していく」ということを、たびたびおっしゃっています。今回もそうした啓示的な閃きがあったのですね。
そうですね。そこから、細かいところは決まっていないけれども、書き出したらなんとかなるだろうと。というか、もう時間がなかったんですよ。
─ 『田園発 港行き自転車』のときも、連載開始まであと三カ月と時間がなくて、急いで取材に出かけられましたね。
あれも時間がなかったですよ。時間がないほうがいいものができるのかもわからない(笑)。それでまず板橋の宿を取材しようと出かけたわけです。今は商店街ですが、現地に立ってみると、昔ここにはずらーっと旅館が並んでいたんだなとか、北陸、信州や飛彈からも、たくさんの飛脚がここから江戸市中へ散っていったんだなという風景が浮かんできてね。ああ、やっぱり主人公はこの板橋の商店街に置こう、じゃあここで何の商売をさせようかな、そんなたいそうな店じゃなくて小さなラーメン屋というのはどうだろう……というように、小説の設定や構想がふくらんでいったんです。
やはり作家は
現場に行くべきだと思う
─ 取材で全国いろいろな灯台を回られたというお話も聞いています。
はい、たくさん行きましたよ。小説にはちょっとしか出てきませんが、たとえば四国の
千葉の房総半島も
─ 楽しそうですね(笑)。ボタンを押すシーンは小説にも出てきますね。
そうです。そうしてたくさんの灯台を見たんですが、でも灯台が主人公といっても、やはり主人公は人間なのでね。主人公の康平が灯台巡りをする必然性というものを、小説の中で作り上げていかなければいけない。さてそれをどう読ませていこうかというのはありましたけど、今回はわりと楽しみながら書けました。新聞小説っていつも苦しみながら書くんですけど。
─ 新聞連載を始めると、いつも寿命が縮むとおっしゃっていますよね。
これで十四作目なので、もう五十年くらい縮んだかな(笑)。灯台の取材ではね、最後にどこの灯台に行こうかというのが大きな問題だったんです。そこがこの小説の大きなカギとなるので。小説には、その方向(灯台)に向かっていく流れを作るカギが必要です。そうでないと単なる「お小説」になってしまうのでね。そこで、
─ 実際に島根の日御碕灯台をご覧になっていかがでしたか。
やはりすごいものですね。日本海に向かって、実に威風堂々として。あの白亜の灯台を夏のセーラー服を着た蘭子の背景に置きたいという強い思いは、実際に日御碕灯台を見なければ思いつかなかったでしょうね。やっぱり作家は、現場に行かなきゃいけません。
ひとりの人間の一生に
どれほど多くの人が関わるのか
─ 妻の蘭子に先立たれた康平は、店を続ける気力を失って引きこもっていたが、幼馴染みのカンちゃん(
康平というのは、もともと引っ込み思案な男で、高校のときもクラスの女子に「臭い」と言われただけで引きこもりになってしまうんですね。そういう引きこもり傾向のあるままに、中華そば屋のオヤジをずっと続けてきた。でも、内面には人知れず熱いものも抱えていたりする。そんな康平を、あるときカンちゃんが非常に侮蔑的な言葉で罵倒するんですね。「お前と話していてもちっとも面白くない。お前には何にもないんだよ。その理由を教えてやるよ。読書なんかしたことないだろ。だからお前は人間の中身がカスカスなんだよ」と。
その言葉に最初は腹を立てたものの、それをきっかけに康平は読書家になっていくんですね。店の常連さんを師匠にして、次々と難解な本を読破していく。辞書を引き引きね。そうやって苦労して読んだ本の中で、彼が一番感銘を受けて、永遠の名作だと考える本が、森鷗外の『澁江抽斎』(大正五年)です。それはまた僕も同じなんです。僕も若いときに読んで、どうしてもわからなかった。もう退屈で退屈でね。よくもこんな小説書きやがったなと(笑)。ところが何度も読み返して時間が経つうちに、だんだん非常に味わい深くなってくるんです。
─ 鷗外の『澁江抽斎』は、ある意味で、『灯台からの響き』に呼応したテーマを持っている気がします。
そうそう。澁江抽斎という、さして有名でもない弘前の医官に鷗外が心を惹きつけられて、その人生に関わった人々を克明に調べ上げて、抽斎という人間を浮き彫りにしていく。すると、澁江抽斎というひとりの人間が育つために、どれだけの人が絡んできたか、その絡んだ人の周りにもどれだけの人が関わっていたかが、つぶさに見えてくるんですよ。
それは、ひとりの人間が生きていくのに、いかに莫大な宇宙的エネルギーがそのひとりひとりに注がれているかということでもある。だからね、ひとりの人間というものが、どれほど尊貴な存在であるかということ、それが今回の僕の小説の大きなテーマだったともいえます。
─ だから、『澁江抽斎』を苦労して読み切った康平が、「ひとりの人間が生まれてから死ぬまでには、これほど多くの他者の無償の愛情や労苦や運命までもが関わっているのかと、粛然と身を正すようになっていた」という感想を抱くわけですね。
うんうん。それは同時に僕の感想でもあるんですよ。
それとね、今回の小説を書いているときに知ったのですけど、鷗外の『澁江抽斎』も新聞連載小説だったんですよ。ということは、いかに当時の読者の質が高かったかということです。あんなの今新聞小説でやったら、誰もが三日で読むのをやめるよ(笑)。
僕が『澁江抽斎』を出したのは、小説の中のひとつのスパイスみたいなものです。鷗外が多分書きたかったのであろう、ひとりの人間が育っていくために、一体どれほどの人間が関わっているのかということを、僕は『灯台からの響き』で書きたかった。もちろん鷗外を超えることはなかなか難しいけれども、そこには蘭子の一生というものがあり、幼馴染みのカンちゃんやトシオ(
─ そうした感慨を、還暦を超えた康平が、灯台を巡る旅の中で再発見していくんですね。
うん、ただね、主人公が灯台を見に行く旅をすることで、ロードムービーみたいにはしたくなかったの。そうなるとちょっと陳腐でしょう。だから、なるべくそういう雰囲気を小説から感じさせないようにどう書くかということには気を配りました。たとえばどこかの灯台を見に行っても、絶えず板橋の自宅に戻るとかね。まあその辺は小説を書く上での技術的なものですけれどもね。
灯台のように
誰かを照らすときも
─ 康平は自分の息子やカンちゃんの息子と一緒に灯台を巡ることになりますが、今までまったく話のできなかった不器用な父親世代と息子の若い世代が、灯台のある風景の中で初めて心を通わす会話ができる。それがとても印象的でした。
自分の経験からしても、やっぱり親父と息子というのは、ある時期まったく背中を向け合うときがあるんですよ。でも、実際心の中では父は父であり、親父は息子のことを絶えず背中についている目で見ている。だけどそれをなかなか言葉に出せないんですよね。それが父と子というものの、永遠のテーマのような気がします。
なんでこのときもうちょっと機微にふれる言葉を言ってやれなかったんだろうとか、なんであのとき怒るのを我慢して黙って見といてやらなかったんだろうとか、親父にしてみれば後悔することがいっぱいあるんです。それを一生恨みに思っている息子もいる。でもね、それはわかるもんですよ。大きな慈愛の中で冷たくしてるのか、あるいはまったく不器用でどんな言葉をかけたらいいのかわからなくて知らんふりしているのかね。それがわかる人間だからこそ、今日の康平があるわけでね。
─ 小説時間の中で、縮こまっていた魂が解放されていくというか、どんどん康平の心境が変化していきますね。
還暦を過ぎた男が、さらに人間として、成長していく。人間は、そこからまだ成長していけるんだということです。そういうことも含めて、人間ってすごいなあ、人間って深いなあというものを感じていただければ、書いた甲斐があったということです。
─ ネタバレになるので詳しくは言えませんが、最後の日御碕灯台で蘭子の秘密が明かされる場面は圧巻で、胸に迫りました。
康平の妻・蘭子という人は、もうすでに死んでいますから、実際には出てきません。だけど最後の康平の旅の中で、一見ごく平凡だった板橋の中華そば屋の奥さんの人生に、あれほどの大きな深い出来事があったんだということが解き明かされる。夫も知らなかったし、子どもたちも知らなかった。でも、周囲には平凡に生きていたように見えたある女性によって、人生の窮地を救われた人たちが何人もいる。実はみんなそうやって生きていっているんじゃないのかなあと思いつつ、あの場面を書いていました。
まるで灯台のように、みんなが寝ているときに、陽が昇ってくるまで海を航行する船に光を届けている。そんなふうに、気がつかないけれど、みんな灯台のようなことをしているときがあるんじゃないかと……。そういうことを読んだ人が感じてくれればなあと思います。
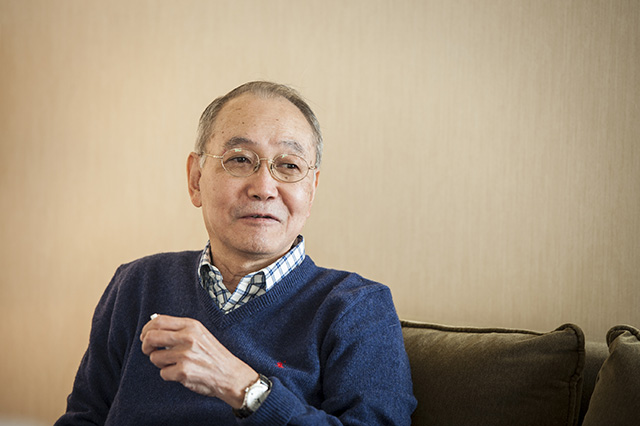
宮本 輝
みやもと・てる●作家。
1947年兵庫県生まれ。77年「泥の河」で太宰治賞を受賞しデビュー。著書に『螢川』(芥川賞)『優駿』(吉川英治文学賞)『約束の冬』(芸術選奨文部科学大臣賞文学部門)『骸骨ビルの庭』(司馬遼太郎賞)「流転の海」シリーズ(毎日芸術賞)『錦繡』『青が散る』『水のかたち』『田園発 港行き自転車』『草花たちの静かな誓い』等多数。2010年紫綬褒章、2020年旭日小綬章受章。





