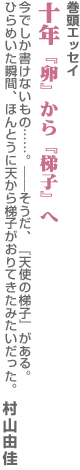
その翌年だったか、〈高校講演会〉という催しのために沖縄へ行った時、万座のあたりの海の上に、雲の間からクリスタルの柱のような光が幾筋も射しているのを見た。それまで見た中で、一番美しくて巨大な光の束だった。
「ねえ、知ってます?」私は、同行していた担当編集者のSさんに言った。「ああいう雲間の光のことを、欧米では〈天使の梯子〉っていうんですって」
「あら素敵」
「でしょ? 私、いつか、もしももしも『天使の卵』の続編を書きたいなんて気持ちになる時がきたら、タイトルはそれにしようって今から決めてるの」
デビューの時からの担当であるSさんは微笑を浮かべ、
「いいじゃない」何度かゆっくりとうなずいて言った。「うん、すごく象徴的でいいわよ。でも、書くのはまだ先ね。うーんと先。それまでは、もっといろんな作品にチャレンジして世界をひろげていかないと」
そのとおりだ、と私も思った。その時点ではストーリーも何も考えていなくて、かろうじて、天使が雲間から地上へとおろす梯子――という絵柄から連想する〈救い〉や〈赦し〉のイメージがあるだけだったし、それに映画でもなんでも、一作目の評判がそこそこ良かったからといって、二匹目のドジョウを狙ったら見るも無惨に終わったなんて例は無数にある。
そんなわけで、このとき私はただ漠然と思っているだけだった。もし本当に自分が『天使の梯子』を書く時がくるとしても、たぶん10年くらいは先だろうな、と。
それっきり、ほとんど忘れてしまっていた。正直言って、当時の私にとっては10年先のことなんかよりも、まずは次の年までこの世界で生き残れるかどうかのほうが切実な問題だったのだ。
| * |
もう20年以上も前の『音楽の手帖』に、村上龍氏がこんな文章を寄せている。
| (略)だから、武満徹の作品では、「弦楽のためのレクイエム」が一番印象に深い。 「レクイエムが一番好きです」僕はある時、武満さんにそう言ったことがある。 「処女作が一番好きだなんて、それは表現者に対する侮辱ですよ」武満さんは、そう言われた。その時は、言われた意味が、わからなかった。 今は、よくわかる。(『音楽の手帖武満徹』1981年10月) |
書かれたのはそんなに昔だが、私がひょんなことからこれを目にしたのは97年の春だった。ちょうど、長編小説としては6作目にあたる『翼』を書いている時だ。
――身につまされた。
なぜなら私自身もデビュー以来ずっと、会う読者会う読者から「『天使の卵』が一番好きです」と言われ続けていいかげん落ち込んでいたからだ。
最初の志のとおり、一作ごとに前とは違う世界にチャレンジし、少しでも深いところ、少しでも高いところに到達しようと、そのつどひとつずつハードルを越えてきたつもりでいたのに、なんでみんなあの最もシンプルで、ある意味何も考えずに書いた『天使の卵』を好きだと言うのか。まるで、その後のお前の仕事には価値がないと、何も進歩などしていないと、処女作がまだ一番マシだったと、そう言われているようなものではないか……。まあ、根が脳天気だから落ち込むと言ったってたかが知れているが、それでもけっこうしんどかったことは間違いない。
でも、今になって思うと、結果的にそれは私にとって――えてして易きに流れやすい私にとって――大きなプラスの作用を果たしてくれた気がするのだ。『天使の卵』が一番好き、という意見がもしあんなに多くなかったら、それに対してナニクソと奮起する気持ちにはならなかったろうし、だとしたら、その後のいくつかの小説が今とは全然別のものになっていた可能性だって大いにあるのだから。
そして不思議なことに、いつの頃からか(たぶん99年に『海を抱く』を書き上げた頃だったのじゃないかと思うけれど)、ふと気がつくと、この〈『天使の卵』コンプレックス〉は嘘みたいに消えてなくなっていた。なんというか、激流に逆らって必死に泳ぎ続けているうちに、いつのまにやら静かな湖に出ていたような感じだった。
いいじゃないか、と思った。『天使の卵』の文庫本が、毎年新しい読者に読まれて、私の書いたほかの小説への入口になってくれている。本を読まないといわれる若い世代の人たちからも、「こんなに泣いたのは初めてです」なんて手紙がもらえる。それだけで、物書き冥利に尽きるってものじゃないか……と、ようやくそう思えるようになったのだ。
そうして2003年、デビューからちょうど10年目の年に、長編小説としては10作目にあたる『星々の舟』でひとつの大きな区切りを迎えることができた時、私が何よりも感じたのは解放感だった。賞という名のわかりやすい〈印〉が与えられたことで、なんだかものすごく楽になった気がした。今までだって好きなものを好きなように書いてはきたけれど、これからはそれに輪をかけてヤンチャができる。そう思ったらわくわくした。
何を書こう。今でしか、書けないもの。この機会だからこそ、書けるもの……。
自慢じゃないが、子どもの頃からグズと言われ続けて育った私だ。毎日馬や鶏をはじめとする動物たちの世話をし、農場作りの愉しみにうつつを抜かしながらも考えて、考えて、ようやく答えにたどりつくのに丸一年かかってしまった。
――そうだ、『天使の梯子』がある。
ひらめいた瞬間はまるで、ほんとうに天から梯子がおりてきたみたいだった。
| * |
『天使の卵』の主人公は、19歳の〈僕〉――美大をめざす浪人生で、名を一本槍歩太という。物語は、彼が朝の電車の中で年上の美しい女性、春妃に一目惚れするところから始まって、紆余曲折ののちに結ばれたものの、彼女を失うところで終わっている。
その10年後の物語として『天使の梯子』を書こうと思い立った時、私がまず決めたのは、どうせ書くなら単なる続編にはするまいということだった。二匹目のドジョウは小さかった、なんてことには絶対したくない。だから、書いている間じゅう何度も頭の中で自分に言い聞かせていた。
一つ。『天使の卵』を知らない人が読んでも、ひとつの作品として独立して楽しめること。
一つ。『天使の卵』を知っている人が読んだら、もーたまらん! というくらいの内容を盛り込むこと。
一つ。『天使の卵』の涙を超えること。
結果として、『天使の梯子』は、一作目よりもかなり長い物語となった。登場人物それぞれにとっての〈救い〉と〈赦し〉を書ききろうと思うと、どうしてもそれだけの長さが必要だったのだ。
語り手も、一作目とは違って、20歳の大学生・古幡慎一という青年である。彼が今付き合っている相手が、かつて『卵』のほうにも登場した春妃の妹・夏姫。慎一は、この夏姫を通して歩太という男の存在を感じとり、嫉妬に駆られて彼のことをさぐらずにはいられなくなり、そうするうちに否応なく、彼らに流れた10年の重さを知っていくのだ。
〈予想は裏切りつつも、期待は裏切らない〉
この10年、どんな小説を書く時でもそれだけは自分に課してきたつもりでいるけれど、中でもとくに、歩太や夏姫に流れた10年をきちんと描くには、やはり私自身にもそれ相応の歳月が必要だったのだと思う。
ほんとうに10年たった今、この物語を書けたというそのことが、ひたひたと嬉しい。