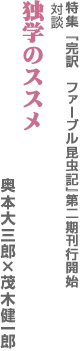
五歳のときに近所の大学生に虫捕りを指南されて以来、捕虫網を手に埼玉県春日部の野原を駆け回っていたという大のムシ好きの茂木健一郎さん。第二期にとりかかり始めた奥本大三郎さん。お二人が交わす楽しいムシ談義です。
■標本にもお国柄
茂木 いよいよ第二期が刊行されましたが、いつ終わるご予定なんですか。
奥本 それを聞かれるのが一番困る。そういう話はやめましょうよ(笑)。
昔々、北海道の日高山脈で、登山中の北大生たちがヒグマに襲われて逃げたという話があるんです。クマがずっと跡をつけてくるので、学生はリュックの中の食糧をぽんと捨てる。クマはそれをしばらく食べているんですが、食べ終わるとまた追いかける。少しずつ食糧を捨てては逃げ、捨てては逃げている、そういう感じの進行状況です。出来上がった原稿を渡すと、すぐに刊行というクマが追いかけてくるわけです。で、学生たちは全員クマに食べられたんでした。たしか(笑)。
茂木 今回改めて読み直してみたんですが、この『昆虫記』というのは、やはり奥本先生じゃないと訳せないなと思いました。フランス文学者としての学識があると同時に心から昆虫を愛しているという、この二つの掛け算というのがなかなかないですよね。
奥本 昆虫学者のような、理系では、そもそもフランス語をやる人が少ないんです。国立大学のドイツ語の教師の数は、フランス語の教師の倍ですし、理学部も、工学部も学生はほとんどがドイツ語を取りますね。
茂木 ぼくは物理学をやったんですけれど、やはりドイツ語選択でした。今ごろになって、フランス語をやっておいたほうがよかったなと反省するんです。
奥本 少し話はずれますけれども、金沢でフランス文学会という学会があったんです。ちょうど隣でドイツ語の学会もあったんですが、会場の外にいると、出て来る人が、もうひと目見ただけで、この人は仏文、この人は独文とわかるんです。挙措動作、服装の感じとか。
茂木 おもしろいですね。ぼくは昨日、フランスのピエール・エルメのもとで修業していたクロエというチョコレート鑑定家の方にお目にかかったんですけれども、話を聞いていると、フランス文化というのはすごく細かいニュアンスを感じ取ってそれにのめり込んでいくみたいなところがあるんだなと感じたんですけど、それはファーブルの書いているものにも感じるんです。
奥本 パリの博物館、ロンドンの大英博物館、それからドイツのシュツットガルトの博物館、それぞれ昆虫の標本が展示されているんですが、おもしろいことにお国柄で展示の仕方がみんな違うんです。
茂木 それはどう違うんですか。
奥本 標本箱の中にチョウを飾るときに、フランス人は波打ったように並べるとか。日本の博物館であんなことをしたら叱られると思いますけど、ソライロコガネという小さいコガネムシが大きな台紙にいっぱい張りつけてあって、その台紙の雲みたいな形がまさにアンリ・マチスなんです。フランス人は、そういう展示をする。
茂木 ぼくは、子供のときに『昆虫記』を夢中になって読んでいましたけど、大人になって、またちょっと別の意味でファーブルというのは偉い人だなと見直しました。一つは独学の人だったということですね。たしか十四歳かそこらで働き始めて、学校を中途退学する。そこから独学して教員として採用されるわけですね。当時のフランスでは、そういうことが可能だったんですか。
奥本 ちょうどその頃一般に教育が普及し始めるんです。そうすると、教員が大量に不足して師範学校をつくるわけです。で、ファーブルは師範学校の給費生募集に応募して合格する。それ以前にも、カトリックの神学校でギリシャ語、ラテン語をたたき込まれていましたから、それがしっかり頭に入っていたんです。