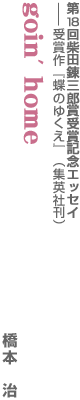
「あっちはよくて、こっちはだめなの?」というような感じ方は、もう四半世紀も前にやめていて、「自分と小説の賞は無縁だ」と思っていたので、受賞の知らせを受けての第一声は、「え?! なァに?」です。なんか感じることは一杯あったのかもしれないけれど、こっちは当座の原稿を書くのに手一杯で、不思議にも「判断保留」の状態が長く続きました。もちろん、「よかった。じゃ、俺は小説家やっててもいいんだ」という実感は、すぐに生まれましたけども。でも、そのややこしい実感の「内実」がどんなものかというとかなり曖昧で、説明に困るようなもんでもありました。「人に言っても混乱させるだけだろうから、黙ってよ」というのが、本当のところでもありました。そうしたら、授賞式の一週間前になって、私の一番古い担当編集者が「死んだ」という知らせがあって、これまた「え?!」ということになった。
「一番古い担当編集者」というのは、私がポストに放り込んだ『桃尻娘』の応募原稿を読んだ人で、普通だったら活字にならない佳作が雑誌に掲載されたのは、彼のおかげかもしれない。一番最初に会った時、「僕が推したんですよ」と言っていた。
新人作家と編集者というと、どうしても「編集者が育てる」で、ましてや私なんか選外佳作なんだから、そういうことがあってもいいはずなのに、育てられた覚えがまったくない。逆に私が、「編集者って、作家を育てるもんじゃないの」と言って、私より年下の彼は、「ま、いいじゃないですか」と言って笑っていた。おかげで私は、「編集者が作家の原稿に赤を入れる」とか「勝手に直す」ということが、今でも信じられない。そんな経験が一度もない。「なんて尊大なんだろう」の前に、「へのカッパだから意味がない」である。おかげで私は、編集者というものがどういうことをする人なのか、いまだによく分からない。「一緒にくだらないこと言って遊んでる以外に、なにすんだろう?」と、実のところ、今でも思っている。「だって、俺なんて佳作じゃん」とか言って、「佳作のくせに」とか言われて、佳作をネタにして一緒に笑っていた。
そんな彼と最後に会ったのは、倒れてそのまま意識不明になって死ぬということが起こる、2日前だった。しかも、一緒に食事をするなんていうのは、10年振りくらいのことだった。「柴田錬三郎賞受賞」を知ってすぐに電話で「おめでとう」を言ってくれて、「たまにはメシでも食いません?」と言った。私は仕事のスケジュールが一杯で、「今、無理だよ」と言って、結局、意識不明になる2日前に、そんな未来があるとも知らずに会った。そして死なれて、「え?!」と思っているところに、「告別式で弔辞を言ってもらえません?」と頼まれて、あれこれと彼のことを思い出した――「彼のことを」というよりも、「彼とのことを」だけれど。
| (一部抜粋) |